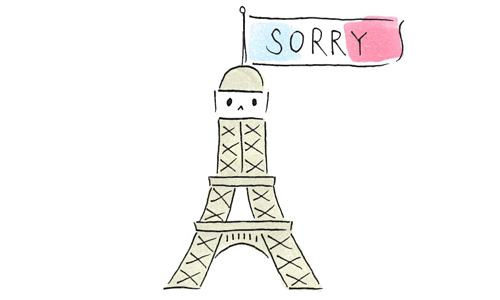台湾から東京に来た、チャン・チェンを訪ねて。
インタビュー
2015年に釜山映画祭で発表された「アジア映画ベスト10」に選ばれた『牯嶺街少年殺人事』。鬼才エドワード・ヤンが1991年に監督し、世界を唸らせた傑作が、4Kレストア・デジタルリマスターで蘇った。物語の舞台は1960年代の台北。夜間高校に通う小四(シャオスー)の青春が時代のうねりのなかで切なく震える。

photo : KOHEI KANNO
当時14歳だったチャン・チェンは、このマスターピースの主人公・小四役で鮮烈な俳優デビューを飾った。ウォン・カーウァイの『ブエノスアイレス』(97年)、ホウ・シャオシェンの『黒衣の刺客』(15年)など、並みいる巨匠と話題作で組み、いまやアジアを代表する男優となった彼が、早逝したエドワード・ヤン没後10年を記念した『牯嶺街少年殺人事件』の日本上映に駆けつけた。
——『牯嶺街少年殺人事件』には、お父様の俳優チャン・クオチューさん、お兄さんのチャン・ハンさんも出演されていて。そんな主演作について、どんな想いがありますか。
チャン・チェン(以下、Z): 「当時、まだ演技がどういうものかわからず、家族と一緒に演じることに混乱したのを憶えています。でもこの映画がなければ、僕は役者になっていなかった。それほど特別な映画です」
——この映画の撮影中に、演技の面白さを知ったということですか。
Z:「撮影前半は、まだ小四という役に入り込めなかったけれど、主役ということで出演シーンも多いので、後半になると徐々に撮影現場が自分にとっての生活空間のように思え、役に没頭できるようになった気がします。いちばん印象に残っているのは、ラストの小明(リサ・ヤン)とのシーン。意味とか動機とか何も考えず、身体が動いて、小四が彼女にした行為を僕自身のものとしてリアルに感じることができた。小四との一体感を得られたその瞬間が、僕の役者に対する興味の原点になったと思いますね」

『牯嶺街少年殺人事件』 © 1991 Kailidoscope
——役者という仕事への面白さを知った現場で、エドワード・ヤン監督の演出で印象に残っていることがありますか。
Z:「映画は、ヤンさんの青春時代に起きた実在の事件をもとにしているので、現場に監督の友達が来て、当時の不良がどんな格好をしていて、どんな喋り方をしていたか、スラングや流行語を教えてくれたりしました。一方で、ヤンさんから撮影前に小部屋に呼ばれてガンガン怒られたこともありました。そうして役者をとことん追いつめた上で、カメラの前にこわばった表情の僕らをパッと出して撮影したり。ヤンさんは役者から自分の欲しいものを引き出す、役者を自分の思う方向へもっていくさまざまな手段を持っていましたね」
>>天国のエドワード・ヤン監督について、そして将来の台湾映画のためにしたいこと。
---page---

『牯嶺街少年殺人事件』 © 1991 Kailidoscope
——製作から25年経ちますが、その間に映画を見直して、何か新しい発見がありましたか。
Z:「『レッド・クリフ』の撮影中に、久しぶりにこの映画を見直したことがあるんです。そのとき、自分の台詞も他の人の台詞も全部憶えている自分自身に驚いて。それほど決定的な体験だったんだなと気づきました。
また、この映画は今回を含め3回修復されていて、5、6年前の前回の修復時に上映した際、音の速度が違っていて。役者の声が甲高いんだけれど、皆そのまま見続けていたら、30分ぐらいして突然映画がブツっと止まって。プロデューサーの余為彦さんが「天国のヤンさん、音の速度が違うじゃないか!って怒ってるよ」と言って、一同笑ったことがありましたよ」
——そのヤン監督が亡くなって早10年。最初に訃報を聞いたときのことを憶えていますか?
Z:「亡くなる2年前ぐらいからヤンさんからの連絡が途絶えて、誰も(癌の)病状を知らなくて。だから訃報は突然でした。ちょうど撮影が終わったところだったので、LAの告別式に飛びました。この業界で働いていると、普段は会わないけれど、悲しみの席で懐かしい映画人に再会するという皮肉なことが起きます。ヤンさんを慕う多くの人が集まって、同窓会のようでした。『牯嶺街少年殺人事件』以降は映画から遠ざかっていた小明役のリサ・ヤンともそのとき再会しました。
あれほどに映画というものに対して深く考え、執着し続けるヤンさんのエネルギーというか、強さというか。それらに触れたことで、僕自身の映画に対する情熱にも火を灯してもらった。本当に大切な人でした」

『牯嶺街少年殺人事件』 © 1991 Kailidoscope
——『グランド・マスター』(13)では役作りから八極拳をマスターし、2012年の全国大会で優勝したり、14年には短編映画『尺蠖』で監督デビューしたりと、役者以外の活躍も伝わってきています。
Z:「八極拳は続けているけれど、いまはあまり練習時間が取れていなくて。初めての監督業はプレッシャーが強くて、自分には役者の方が向いているなと思いました(笑)。新鮮でしたが、役者という本業に立ち返って、将来的に台湾映画に何か貢献したいと思っているんです。ヤンさんやホウ・シャオシェン監督たちは、若い映画人と切磋琢磨して台湾ニュー・ウェイブを生み出しました。当時に比べて、いまの僕らはそれぞれに努力しているけれど、横の連携が少ない。もっとコミュニケーションを密に取っていかなきゃと感じますね」
——40歳を迎え、俳優として今どういう地点にいると思いますか。
Z:「さまざまな先輩俳優を見ていて、35歳から45歳の10年間は男優にとって充実した時期だと感じていて。これからの5年間が、僕にとっても大切な時期だと思うんです。いまは幸いなことに、リラックスして自在に演技ができる状況にある。ただこの先、やたらと出演するのでなく、丁寧に仕事をしていく中で、自分の中にどんな演技の情熱があるか探っていく鎮静時期に当てたいと思っていて。この時期を通して、また次の新しいステップに行けるように努力してみたいんです」
『牯嶺街少年殺人事件』
●監督・共同脚本/エドワード・ヤン
●出演/チャン・チェン、リサ・ヤン、チャン・クオチュー
●1991年、台湾映画
●236分
●配給/ビターズ・エンド
●角川シネマ有楽町、新宿武蔵野館ほかにて全国公開中。
www.bitters.co.jp/abrightersummerday
Zhāng Zhèn
1976年、台北生まれ。14歳の時、父と兄が出演する『牯嶺街少年殺人事件』(1991年)の主演に抜擢され、演技の道へ。『カップルズ』(96年)に続き、『グリーン・デスティニー』(2000年)『2046』(04年)、『黒衣の刺客』(15年)など、アジアの名だたる監督の名作に出演。今年のベルリン映画祭で話題を呼んだSABU監督『ミスター・ロン』が今秋公開予定。
texte : REIKO KUBO