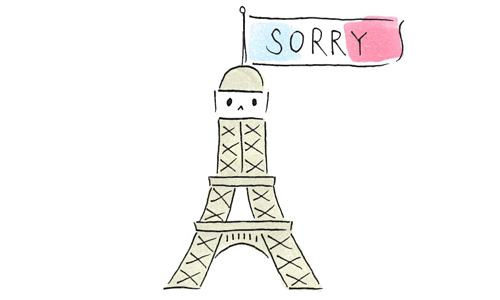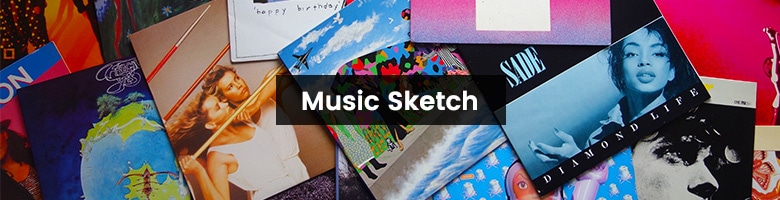
新世代の音楽シーンを牽引するハイエイタス・カイヨーテに直撃取材!(前編)
Music Sketch
今、音楽通のみならず、ファッション界などからも最も注目されているバンドとして先ず名前が挙がるのが、ハイエイタス・カイヨーテ。R&B、ロック、ジャズ、ビート・ミュージック等のあらゆる要素を取り入れた最新型ミクスチャー・バンドであり、紅一点のヴォーカリスト、ネイ・パームのファッションも象徴的なオーストラリアのメルボルン出身のバンドだ。メルボルンは、私が面白い音楽が続々と誕生している都市としてここずっとチェックしているエリアのひとつで、世界各国のレストランが立ち並ぶストリートがあるようにマルチカルチャーな地域。その街から生まれたハイエイタス・カイヨーテには、多様な音楽背景を持つ才気溢れるミュージシャンが結集し、グラミー賞で2年続けてノミネートされるほど評価が高い。来日中に運良くメンバー全員に話を聞くことができたので、興味深い内容を2回にわたって紹介したい。
メルボルンでは特に北部のミュージックシーンが盛り上がっていて、そこで4人は知り合ったという。シドニーに次いでオーストラリアでは2番目に人口の多い都市メルボルンは、観光名所が多いシドニーに比べて地方色が強く、ローカルバンドが根付いたライヴハウスが多々あって活躍しやすい環境が揃っているそうだ。

(写真左から)ネイ・パーム(Vo,G)、ポール・ベンダー(Ba,G,Key,Prog)、サイモン・マーヴィン(Key,Per)、ペリン・モス(Dr,Per,Key,Ba)。
■ それぞれが頭の中で違うものを見ているから面白いものが生まれた。
― メンバーはどのようにして集まったのですか?
サイモン・マーヴィン:「メルボルンには世界中からミュージシャンが集まってくるし、支え合うようなシーンもある。例えばメタルをやっていてもジャズやフォークミュージックのプロジェクトのところに顔を出すなど、音楽そのものの交流があるんだ。僕らも全員が違うバックグラウンドを持っている。もし同じ音楽学校に行ったら同じような音楽になるけど、それぞれが頭の中で違うものを見ているから面白いものが生まれたんだと思う」
― 曲作りはどのようにしてやっているの? 例えば「ラピュタ」はどうだったのでしょう?
ネイ・パーム(以下、N):「それこそ、どの曲も違う書き方をしているの。『ラピュタ』はサイモンがローランドのJX-3Pというシンセサイザーを手に入れて新しい音を探していたら、映画『天空の城ラピュタ』のヴィジュアルイメージが浮かんできて。ちょうど宮崎駿監督の引退のニュースが入ってきたので、トリビュート曲にしようということになったの」
「Nakamarra」ハイエイタス・カイヨーテが多くの人に知られるきっかけとなったヒット曲。
■ より多くの活力が吹き込まれていく過程が大好き。
― 「Breathing Underwater」はどうなんでしょう?ネット上にはネイが弾き語りで歌っている動画が先にアップされていました。
N:「これは曲から始まったわ。でも、いろんな感触があるのよね。例えば、アルバム・ヴァージョンの音の感触は凄く濃密でシネマティック。スタジオ入りした際に私が最初に思いついてワクワクしたのは、これがスティーヴィー・ワンダーからインスピレーションを得た曲ということ。このシンセベース・サウンドは “スティーヴィーだったらどうするかな、やっぱり弾くのはシンセベースだな?”って、サイモンが思いついたの。そこで、あのリフ、つまりサビ部分が生まれたの。この曲のサビ部分全てで歌っている訳じゃないけどね。それから、ペリンが西アフリカのリズムへの理解が深かったことも大きかった。この曲の循環的な性質には西アフリカのリズムが不可欠だったから。リズムが動き回ったり、押したり引いたりするから、テンポがメトロノームのように規則正しくはないの。楽曲はマリ出身のトゥマニ・ジャバテ、それからスティーヴィー・ワンダーから参考にしたのよ」
― トゥマニ・ジャバテはコラ奏者(アフリカン・ハープ)ですよね。私、大好きなんです。
N:「そうなの?(笑)。このバンドはメンバー全員の音楽的影響が多岐に渡るから、“あぁ、それだったら、こんなのはどう?”っていう感じで各自の音楽知識のカタログからアイディアを持ち寄ることができるの。曲を持ち込んでメンバー全員で共作していく上で、より多くの活力が吹き込まれていく過程が私は大好き。クリエイティヴな幅広さがあるっていうのは、困難なこともあるけど、やり甲斐と開放感があるわ」
Nai Palm (Hiatus Kaiyote) 「Breathing Underwater」ネイのソロ・パフォーマンス。
Hiatus Kaiyote 「Breathing Underwater」第58回グラミー賞でR&Bパフォーマンス部門にノミネートされた楽曲。
---page---
■ 聴き手側のイマジネーションを喚起させたいだけ。
― 歌詞について聞きたいのですが、南米の怪奇小説のような、神秘的で不可思議な歌詞が多いのは何故なんでしょう? そういう小説や世界観が好きなんでしょうか。
N:「必ずしもそういう訳じゃないけど、そういえば、私の親友の何人かはコロンビア人ね。ペリンの奥さんも私の仲良い友人なんだけど、コロンビア人ね。作家だと、チリの詩人パブロ・ネルーダが好き。本だと『アルケミスト』(パウロ・コエーリョ著)とか。ペルーの歌手のスサーナ・バカや、コロンビアのトト・ラ・モンポシーナといった南米出身の歌手も好き。彼らの音楽には何か儀式的なものが存在していて、それって重要なことだと思う。楽曲内容は個人的なことだろうと、そうじゃなかろうと、空想の世界であろうと、複数の状況に解釈することができれば何でもいいの。例えば“日曜日のBBQは〜”なんて歌詞じゃなくて、歌詞内容を十分に重ねていくことで、単なる自分の経験談に限定せずに広がりを持たせることができる。私たちの歌詞の内容を理解するのに正誤は存在しないからこそ、私たちの楽曲はより多くの聴き手に共感してもらえるんだと思う。ただ、聴き手側のイマジネーションを喚起させたいだけなのよ。でも確かに、南米からは素晴らしい芸術作品がたくさんあるわよね」
「The World It Softly Lulls' (Live at 3RRR)」
■ ライヴは儀式。カタルシスやデトックスの要素も。
― 儀式(リチュアル)は具体的にどう捉えたらいいのでしょう?
N:「スピリチュアルな、『セレモニー』としての儀式ね。癒しのセレモニーのような。演奏する側も癒されるのよね。というのも、音楽はカタルシスのようなものだから、デトックスのような目的があるの。だって、現代の音楽って完全にエンターテインメントを目的としているから、内容的には空っぽでしょ?私がこのツアー生活に耐えられるのは、ライヴという活動をオーディエンスと自分自身への儀式の奉納(献納)として捉えるようにしているからだと思う。例えば、凄くイヤな日があったら、歌うことで何か強く感じる心の内を外に吐き出すことができるから。それって重要だと思うのよ」
「Shaolin Monk Motherfunk」
― その昔、デビューした頃のアラニス・モリセットは「ステージでは自分の内なるものを全部吐き出して無の境地に達するので、それこそライヴは儀式のようなもの」と、話していました。
N:「アラニスってそうなの?!」
ポール・ベンダー(以下、Pa):「うん。みんなそうだね」
ペリン・モス:「そうじゃなかったら、ライヴ活動を違う目的でやっているとしか思えないよね。人間として、その方が自然なんじゃないかな」
Pa:「理想としてはそうだね。自分が大好きなライヴ活動をやっていると、そこまでは考えないものだけど。どのライヴも毎回若干異なるし、他のバンドで演奏することが、また違った体験になる。つまり、自分、他のバンドメンバー、そしてオーディエンスのために創り上げていく感じ。頭、心、そして身体のカタルシスのようなものだよね」

サマーソニック2016 8月20日東京公演出演時の模様。写真:古渓一道
■ スティーヴィー・ワンダーの泣きながらの演奏に感動して。
N:「オーディエンスとしての視点で話すと、畏怖の念に打たれるようなライヴを観た後に、そのアーティストが非常に辛い体験を経ていたことを知ったりすることが多いの。例えば、観客としての自分はアーティスト側に何が起きたかも知らずにステージを見ているわけだけど、実はそのアーティストの母親が他界してしまった後のライヴだったりして……。ライヴ活動はアーティストにとってセラピーのようなものだから、アーティストの苦しみが激しいステージへと反映されることが非常に多いと思う。例えば、マイケル・ジャクソンの葬儀で演奏したスティーヴィー・ワンダーの映像を見ると、スティーヴィーは泣きながら演奏している。涙が出てしまった時に演奏するのは大変なのよね。演奏中に悲しみが増してきて、場合によっては泣き崩れてステージを去ることも有り得たと思うけど、5分間の演奏中にスティーヴィーは泣きながらも完奏し、その空間が……、とても美しかったわ。毎回ライヴでそこまで持っていく必要はないけど、単に『楽器を演奏する』以上の力強さがそこには存在したの」
ネイの止まらない熱いトークは、後半も続きます。

最新アルバム『チューズ・ユア・ウェポン』
Amazonで見る≫
*To be continued