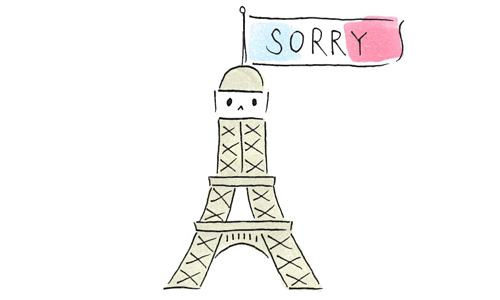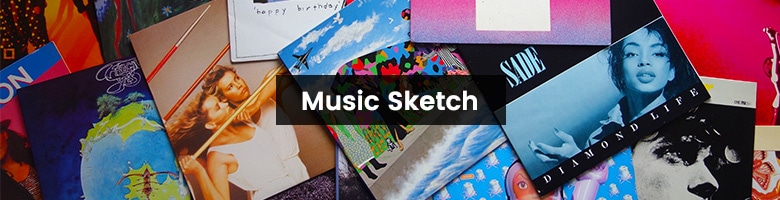
オダギリジョーが語る、初長編監督作品『ある船頭の話』
Music Sketch
オダギリジョーが10年前から温めていた構想を、初の長編監督として作品にしたのが『ある船頭の話』だ。『宵闇真珠』(2018年)で主演と監督という関係で現場をともにしたクリストファー・ドイルに背中を押してもらい、ようやくそれが実現した。撮影監督には特別な映像空間を作り上げることで知られるそのドイルが参加し、音楽はアルメニア出身のティグラン・ハマシアンが、衣装はアカデミー賞衣装デザイン賞を受賞したこともあるワダエミが担当。オダギリ作品にこの組み合わせだけでも心躍るが、細野晴臣を筆頭に船に乗る客に豪華キャストが登場し、強く印象に残る作品に仕上がった。オダギリ監督に話を聞いた。

オダギリジョー。俳優として国内で数々の賞を受賞しているほか、海外作品の出演作も多い。監督作品としては『さくらな人たち』(2009年)ほか。写真:根本絵梨子
■戦った末にできた作品、という印象が持てるものにしたかった。
――私はティグラン・ハマシアンさんの音楽がとても好きで、クリストファー・ドイルさんも昔から好きとあって、冒頭の素晴らしいロケーションから引き込まれていきました。すでに2回観たのですが、観るたびに深みの加わる映画でした。クレジットで編集のところにもオダギリさんの名前が載っていましたが、作業は大変だったのではないでしょうか?
オダギリジョー(以下O:)実はいちばん好きって言っていうくらい編集作業が好きなんです。だから、大変だとしても、絶対に自分でやりたいんですよね。

写真手前からオダギリジョー監督とクリストファー・ドイル撮影監督。
――脚本の構想は10年ほど前からあったそうですが、実際に撮るようになって、ロケ場所が決まるなどしてから、どこか変更した部分はありましたか?
O:いちばん大きかったのは、当初船頭の役は自分で演じるつもりで台本を書いていたので、設定が大きく変わりましたね。柄本(明)さんになった時点で、年齢を上げて書き換えました。
――なぜ変えたのですか?
O:いろんな理由があったんですけど、自分で演じるのをやめたのは、監督業に専念しないと乗り越えられないとも思いましたし、まずその姿勢がよくないんじゃないかと思って。かといって僕と同世代の方だと、仲間意識が出てきてしまい、甘えが生まれちゃうような気がして。ちょっと年齢を上げてでも、厳しい先輩と戦った末にできた作品なんだなっていう印象が持てるものにしたかったんです。
――そうすると、船頭と少女との関係性は大きく変わりますよね。
O:当初はどちらかというと、年齢も親子ぐらいの違いというのか、いい例かどうかはわからないですけど、『レオン』とか、ああいうものに近い物語でもあったんです。少女がちょっと背伸びをして船頭と一緒に生活を始めるみたいな、淡い少女の目線みたいなものも描いてはいたんですけど。でも柄本さんだと年が離れ過ぎて成立しない部分も出てきたので、描き方として事件性に重きを置く方向で書き換えていきました。
---fadeinpager---
■チャレンジのひとつは、主役を柄本明さんに変えたところ。
――設定が変わっても、変わらず伝えたかったことは何になるのでしょう?
O:利便性の裏で失っていくものや、お金や時間で損得が測られる社会において、自分の人生にとって何が大切なのか、もしくは幸せなのか、とか、そういうことを一度考えてみませんか?といったことでしょうか。それらは、どうストーリーが転がっても描けると思っていたので、そこは特に心配はなかったです。
――アレゴリー的(寓意的)なものがいくつか登場しますが、たとえば草笛光子さんが演じる女性が「狐を見ると孤独という字を思い出す」といった台詞や、主人公が木像を彫る姿など、自分自身を見つめさせるようなシーンも印象的でした。
O:孤独に関しては、僕の世代が演じるよりも柄本さんが船頭を演じることで、より深まったのかもしれないですね。表現として、その重ねた年齢の分だけ、孤独の大きさも増すんでしょうし、そういう意味では柄本さんにお引き受けいただいて、この映画が大きく膨らんだ部分もあったと思います。

近代化で橋の建設が進む川辺の村で、船頭を営むトイチ(柄本明)と客(草笛光子)。
――チャレンジのひとつが柄本さんに主役をお願いしたところ?
O:そうですね、でも(作品が)絶対によくなると思ったので。確信はあったと思います。あれだけの人生を重ねたトイチという男が、消えゆく運命を背負うということが、この物語のキーになるというのは、やっぱり柄本さんに変わったところで生まれたものなんでしょうね。
---fadeinpager---
■亡霊と木像の意味。
――亡霊のような少年の存在は何を意味していたのですか?
O:輪廻とか、そういう考え方って、いまやとてもアジア的だったりするじゃないですか。クリスチャンの人にとっては、なかなか輪廻の捉え方とか難しいのかなって思って。それで、ああいう存在が説明を担う役割としても、ひとつ効果的に物語にエッセンスを与えてくれることを期待しました。
――クリスチャンについても少し描かれていますよね。対比ではないですが。
O:生と死を描くにあたり、仏教的でアジア的な考え方と、それとはまったく違う、西洋的なキリスト教に関しては少し描いておきたいと思っていました。せっかく作るなら、世界中の人に見てもらいたかったので、その対比にも興味を持ってもらえればという思いがありました。

トイチ(柄本明)、少女(川島鈴遥)、源三(村上虹郎)を中心にストーリーは展開。
――ネタバレになるので、ボカしながら伺いますが(笑)、終盤の少女と源三のシーンですが、やっぱりああいうものは必然的に描かないとならないのでしょうか?
O:あれは、源三がああなってしまうことが、あのシーンにとって必要だったんです。
――すごく変わってしまった源三ということも含めて?
O:そうですね。必然なのかと聞かれると、それはいろいろな表現方法の中で描かなくても表現できることもあるかもしれないですね。ただ、僕の作品の中ではあのシーンは重要な意味を持っていますし、必然だと思っています。あのシーンがあるから、いくつかの合点がいくように作っているつもりです。
――そうなんですね。それから最後のトイチの表情が、すべてを捨て去っていて清々としているようなふうに感じたんです。
O:なるほど(笑)。その辺りはさすが、柄本さんですね。
――ラストの表情に意味はないのですか?
O:いや、僕は柄本さんに表情までは注文はしなかったので、もう本当にほとんどお任せで。ちゃんと答えを出してくれる方だと思っていましたし、長い時間ひとつの役として生きていると、監督の演出を超えた部分で役者が醸し出すものもあるんですよ。あの最後とかは、特に僕も演出をつけてないんじゃないんですかね。動きとか、表現の大小はたぶんお願いしたと思いますけど。終始、柄本さんには任せっきりでした。
---fadeinpager---
■最後まで迷った、いちばん最後の台詞。
――心に残る台詞も多いのですが、監督の思いが特に強く入った、みんなに伝えたかった台詞というとどれになるんでしょう。
O:(しばし沈黙)それぞれのシーンになんとなくありますけど、いま思い出すのは、いちばん最後のトイチの台詞は「どうせここにいても何もない人間だ」みたいなことなんですけど、実は別パターンもあったんです。だけど結果的にあの言葉に落ち着いたということはありました。
――それは柄本さんと話して?
O:柄本さんにはふたパターン録音させてもらって、で、編集の時も悩んでいたし、最終的に音作業する時まで確か悩んでいたんですよ。
――なんという台詞だったんですか?
O:もうひとつの方は、「俺はお前を守ってやらなきゃいけないんだ」みたいな、彼女に言っているのか、自分に言っているのか、どちらにも取れる、そういう台詞だったと思うんですけど。どっちかで悩んだ時に、いろんなスタッフと話し合って、「どうせここにいたところで何もねぇ人間だ」っていう言葉に落ち着きました。

夏場も冬場も過酷な撮影が続いたという。
――「俺はお前くらい守ってやりたいと思ったんだ」という台詞はありましたよね。
O:そうなんですよ。言葉としては似ているんですが、それぞれの状況で、明らかに伝わり方が違うという、いい例なのかもしれません。
――タイトルバックも意味深です。
O:あれは脚本には書いてあったんですが、映像としてはなくてもいいのかもしれないという思いもあったんです。でも、ワダエミさんから「あれは絶対に残してね。あの描写から少女の赤い衣装をイメージしたんだから」と言われて、残すことにしました(笑)。言葉にするのは嫌なんですが、簡単にいうと、この世界観というか、少女の存在ですね。トイチの人生を蝕むと言えばいいのか、トイチの中で広がっていく少女の存在感とか、そういうことを表しているんだろうと思います。
『ある船頭の話』予告編
---fadeinpager---
■いままで僕は、監督を困らせたタイプだと思うんです。
――最後に、役者として演じる時に、役に対するこだわりというのはもちろんあると思いますが、脚本や監督を担当されて気付いたこだわりはありますか?
O:悪い意味で、自分は本当に台本にこだわるんだなと思いましたね。もともと台本を書くのが好きなのですが、書き上げた時点で1本の新しい物語を生み出したという、大きな満足感があるんです。ところが、映像化する時に、その満足感からどんどん難しさに変わっていくので、それが苦しみに変わっていく。
――台本に書いたものをなかなか具現化できないから?
O:はい、その生みの苦しみがどんどん高まっていくんです。でもそれって、脚本に固執しすぎているせいだと思うんですよ。あまりにそれを表現しようとすると、そういう苦しさが出てきて。自分で自分の首を絞めているような感覚ですね。

時間を気にせず、とても気さくに話してくれたオダギリ監督。写真:根本絵梨子
――でも、俳優としては、脚本の上を行こうとする場合や、即興による演技を楽しむ時もありますよね?
O:タイプとしてはそういうタイプだし、そういうふうに即興的に芝居を作り上げる楽しみを知っているくせに、監督としてはそうではなかったですね。もちろん、作品のタイプや世界観にもよるとは思いますが、自分が作り上げた脚本をできるだけ忠実に具現化したいという欲求を消すことはできませんでした。今回は時代や場所を明確に描かない、という設定があったので、仕方ないんですけどね。
――では今後、演技も変わってくるかもしれませんね。
O:そうかもしれませんね(笑)、監督の苦しみってやっぱり理解もできるし、いままで僕、そんなことを考えもせず、好き勝手に芝居をしてきたことが多かったので、監督を困らせたタイプだと思うんですよ。
――それもオダギリさんの魅力のひとつで。
O:よく言うとそうかもしれませんが。本当に監督が苦しまないように芝居をしてあげるということも、たぶんこれから出てくると思うし……。
――それを聞くと、「え~!」って驚くファンがたくさんいると思いますよ。
O:(爆笑)。なんか、本当に難しいですよね、関わり方って。
●衣装:
ジャケット¥140,400、シャツ¥59,400、パンツ¥86,400/以上すべてイッセイ ミヤケ シューズ/スタイリスト私物
●問い合わせ先:
イッセイ ミヤケ tel:03-5454-1705
●監督・脚本/オダギリジョー
●出演/柄本明、川島鈴遥、村上虹郎、伊原剛志、浅野忠信、村上淳、蒼井優、笹野高史、草笛光子、細野晴臣、永瀬正敏、橋爪功
●撮影監督/クリストファー・ドイル
●衣装デザイン/ワダエミ
●音楽/ティグラン・ハマシアン
●配給/キノフィルムズ
●9月13日(金)より新宿武蔵野館ほか全国公開
http://aru-sendou.jp
©2019「ある船頭の話」製作委員会
※この記事に掲載している商品・サービスの価格は、2019年9月時点の8%の消費税を含んだ価格です。
*To Be Continued
stylisme:TETSUYA NISHIMURA, coiffure et maquillage:YUKI SHIRATORI (UMiTOS)