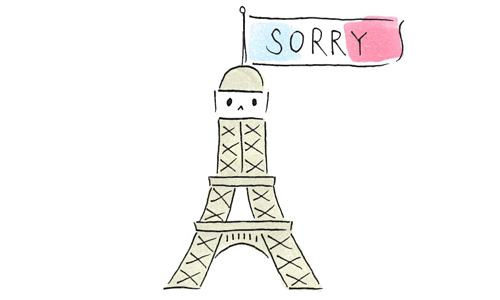パリ・オペラ座バレエ団の『ジゼル』全幕、もうじき!
パリとバレエとオペラ座と。
3年ぶりにパリ・オペラ座バレエ団が来日する。東京文化会館で2月27日に幕を開けるのは、ロマンティックバレエの最高傑作『ジゼル』。パリでは1月31日から2月15日までその公演があり、ダンサーたちはステージで得た高揚した気持ちを抱えて来日するに違いない。パリ・オペラ座バレエ団によって『ジゼル』全幕が東京で踊られるのは、10年ぶりである。1幕、2幕と追って作品を鑑賞するのでガラで踊られるパ・ド・ドゥとは感動のレベルが異なるし、パリ・オペラ座が世界に誇る素晴らしいコール・ド・バレエの仕事を見るいい機会となる。

暗めの照明の舞台で、幾層ものチュールからなる白く幻想的なロマンティック・チュチュ。26名のウィリスたちのアラベスクはひたすら美しい。photo:Michel Lidvac
まずは、バレエにあまり詳しくないという人のため、公演を主催するNBSによる『ジゼル』のあらすじを以下に。
第1幕:ぶどう栽培を営む村。母親とともに暮らす娘ジゼルは、ある若者──じつはシレジア公爵アルブレヒトと恋に落ちている。ジゼルは踊ることが何より好きだが、母親は心臓の弱いジゼルの身体を心配し、「そんなに踊っていると、ウィリになってしまうよ」と言ってやめさせる。そんなとき、貴族の一行が狩の休息にやってくる。その中に婚約者バティルドの姿を見たアルブレヒトは身を隠すが、ジゼルを慕う森番ヒラリオンがアルブレヒトの正体をあばく。真実を知ったジゼルは正気を失って息絶える。
第2幕:夜。妖気漂う森の中で、ウィリとなったジゼルが墓から現れる。深い悔恨の思いで墓を訪れたアルブレヒトは、いまやジゼルの仲間である、魔性のウィリたちに捕まるが……。
東京公演ではエトワール6名による3つの異なる配役で踊られる。ガルニエ宮での公演で この作品に初役で取り組んだのはジェルマン・ルーヴェ、レオノール・ボラック、そしてユーゴ・マルシャン。オレリー・デュポン芸術監督の任命による3名のエトワールである。

第2幕、ウィリに囲まれたアルブレヒトを救うべく、ミルタに命乞いをするジゼル。photo:Michel Lidvac
---fadeinpager---
レオノール・ボラックのジゼルと、ジェルマン・ルーヴェのアルブレヒト。
「小さい時、アルブレヒトを理想の王子様のように見ていて、彼に恋していたくらいなの。本当はひどい奴だというのにね(笑)。モラルのなさは子どもなのでわかってなかった。それに第2幕の死の暗い面も見ていず、まるで宙に飛び立ってしまいそうなウィリたちの非現実で魔法のような面だけに目がいっていました」
と語るのは、ジゼル役を踊ることを小さい時から夢見ていたというレオノール。コール・ド・バレエ時代には端役で第1幕の貴族たちのひとり、代役でウィリスとペザントのパ・ド・ドゥという程度だったそうだ。パリ公演のためのリハーサルがかなり進んだところで、彼女に役作りについて語ってもらうことにした。
「この作品を踊りたいと思ったのは、ジゼルに自分を重ねることが若い時代には簡単なことだったからでしょうね。初恋が生まれ、それによって失望することもありえ……こうした経験は人生の早い時期、思春期に訪れることですね。その後すぐに立ち直って普通の生活に戻るにしても、当人にしてみれば大きな出来事。地球上いたるところで誰にでも起きることです。ジゼルのように命を失わないにしても、裏切られて味わうつらさ、痛ましさ……とても普遍的な物語です」
ふたりともが初役というレオノールとジェルマンの組み合わせ。リハーサルは昨年12月に始まり、オレリー・デュポンがふたりの稽古を見にきてくれることもあって……。
「パリとニューヨークの公演で私が狩猟の貴族の端役で出た時、オレリーがジゼルでした。いろいろなダンサーが踊ったジゼルの中でも、彼女の役の解釈には心触れられました。70年代だと思うのだけどビデオで見たカルラ・フラッチのジゼルも素晴らしかった。ふたりとも第1幕がとても自然なの。バレリーナすぎず、とっても人間的で。私、第1幕では自分の感情に素直な人間的な面を見せることが大切だと思っています。お人形のように演じるジゼル役を時々見ることがあるけれど、あまりキッチュになってはいけない。農村の娘なので少し地に足のついた感じを見せて、それによって第2幕とのコントラストもより大きく出せると思うのです。若くフレッシュな娘を想像してジゼル役に取り組んだのですが、思っていたより難しいことがわかりました。 若いといっても彼女はお茶目でもなく、控えめで少し慎み深く……若い娘役っておきゃんな感じが多いのだけど、そうした面を取り去るというのは若い娘を演じる簡単さも同時に取り去ることがわかって……。それに彼女は恥ずかしがり屋だけどナイーブなだけであって、愚かではない。このあたり、気をつけないと……こういった微妙なニュアンスの表現が難しい。それだけに興味深い仕事だと感じます」

純朴な娘ジゼル。アルブレヒトとの時間が楽しく過ぎることで、その後に待つドラマの悲劇性が増す。photo:Yonathan Kellerman/ Opéra national de Paris
この村娘ジゼルが恋に落ちる相手がロイス。村の若者といったいでたちだが、彼の正体は公爵アルブレヒトである。クルランド大公の娘バティストと婚約しているのだが、もちろんジゼルにはそれを隠し彼女の気を引くのである。彼女のパートナー役、ジェルマン・ルーヴェはどのようなアルブレヒトを演じるのだろうか。
「アルブレヒトって多かれ少なかれ卑怯者でしょ。ダンサーによってはジゼルへの愛はなくて、単なる遊びというように演じる人もいます。でもジェルマンはジゼルへの愛が基本にあって、とことん憎むべき男にはしない!と決めたんですよ。自分の嘘から抜け出せなくなる、というのが彼が演じるアルブレヒト。最初は無邪気な嘘、それが段々と単なる嘘では済まなくなって自分がついた嘘の罠にはまってしまうという……。アルブレヒトは、ジゼルの友達が一緒に踊ろうと声をかけた時に断るでしょ。これはふたりの関係を公にすることにまだ心の準備ができていず、困惑してるのです。彼女に真意を話せるタイミングが見つけられずにいるうちに、悲劇へと至ってしまうんですね」
アルブレヒトの裏切りにジゼルは正気を失うほど強い衝撃を受け、弱い心臓が耐えられず死に至る悲劇。第1幕の途中で心臓の弱いジゼルを母親が気遣うシーンが何度かあるが、最後、母の心配が現実となってしまうのだ。第1幕最後の狂気のシーンはジゼル役を踊るダンサーにとって、表現力が問われ大きな見せ場となっている。
「リハーサルコーチもオレリーからも、この場面は私の演じたいように、と言われました。信憑性を出すためには、確かにパーソナルである必要がありますね。ジゼルの狂気は徐々に来るものだと私は思うので、あまり最初からはこれみよがしにはしたくない。自分の頭の中で起きていることに驚いている感じ……。症状からこれは統合失調症のように私には思え、その患者は自分の手が感じられないということがあるらしいので、私は自分の手が認識できないという感じを試してみようかと……。これは私が想像したちょっとしたことですけど、説得力があるかどうか見てみましょう。このシーンでは自分の幸せな時間を思い出す瞬間があり、メランコリーもミックスされていますね。幸せだった時間の中に避難するように閉じこもって……」

第2幕、精霊のジゼルとアルブレヒト。photo:Yonathan Kellerman/ Opéra national de Paris
緻密な彼女の役作りはオペラ・ガルニエの舞台で大成功。ジゼルの心の中が観客に透けて見えるような説得力があり、ともにこの悲痛な数分を体験させ、涙させる素晴らしさだった。彼女にとって第1幕で興味深いのが女優演技の仕事なら、第2幕はテクニックの面での仕事だという。
「腕の使い方、姿勢、身振りなどがロマンティックバレエ独特のものでほかのクラシック作品とは異なるので、これを学ぶのはおもしろいですね。丈の長いロマンティック・チュチュと相まって、地に足がふれていず宙に体が浮遊してるような魔法。観客にとってどれだけそれが大切なことか自分の経験から知っているので、その期待に応えられるようにと仕事をしています。私の視点ですが第1幕はジゼルのドラマ、第2幕はアルブレヒトのドラマ、だと。第2幕のジゼルはほかのウィリ同様命のない精霊なので苦しむ存在ではありません。この場の演技の基本は顔に表情を表さないことなのだけど、音楽がドラマティックだとつい顔に反応が出てしまいそうになって……それと戦う必要があります。演技をしない演技というか、普通とは反対の仕事ですね。たとえばアルブレヒトを彼女は助けたいのにミルタは反対する。ふたりの間に挟まれたジゼルは、顔ではなく身体で表現することが要求されます」
---fadeinpager---
ドロテ・ジルベール、運命の『ジゼル』
芸術監督オレリー・デュポンも「彼女のジゼルは素晴らしい。この役がとても似合っています」と太鼓判を押すドロテ・ジルベール。『ジゼル』はドロテにとって運命と言える作品なのである。10歳の時、地元トゥールーズの劇場で踊られた『ジゼル』を見て、美しい白いチュチュもさることながら、彼女の心はノエラ・ポントワが踊った役に揺さぶられた。その時に、「ママ、ダンスって職業にできるの?」と母に尋ね、仕事としてダンスが存在することを理解。この時アルブレヒト役を踊ったのはマニュエル・ルグリで、そのルグリと『くるみ割り人形』を踊って自分が2017年にエトワールに任命されることになるとは……。
「ジゼルの物語は型通りとはいえ、無条件の愛、許し……語ることがとてもたくさんあるピュアで美しい作品よ。私がとりわけ好きなのは第2幕。音楽も素晴らしいし、美しいシーンがたくさんあるわ。たとえば、お墓の前に座るアルブレヒトの膝もとに、はらはらとひとつずつ花を落としていく時。私は信心深い人間ではないけれど、この時、聖母マリアの絵画が私の目に浮かぶの。彼の手からするっと逃れるシーンも好きだわ。第2幕ではずっとアルブレヒトにジゼルは言い続けてるの、ずっと愛しているわ、気にしないで、あなたを許すわ……って。最後の別れは悲しいわね」

白い花をアルブレヒトに降らせる精霊ジゼル。彼にジゼルは見えず、気配を感じるだけ。photo:Michel Lidvac
「私は演じることが好きなので、常に役をうまく演じたい、よい出来にしたいという意欲があるの。だからビデオを見たり、本を読んだり、映画を見たり、時にはメモもとってと、事前の仕事にたっぷりと時間をかけるようにしています。踊る人物像を豊かにするために、多くのインスピレーションを得るよう努めます」
ドロテによると、ジゼルの狂気は頭の中で何かがプチンと切れたように突然やってくる。心臓は弱くても、それまで頭は正常だったのだが、自分の人生で経験したことのない裏切りという行為にひどくショックを受けるのだ。
「理解を超えたことなのね。なぜ?何が起きたの?と。母親に大切に守られて生きてきて、父親はいなくても彼女のそれまでの人生はとても純粋なものだったの……それゆえに電気ショックを受けたようになってしまう。そして頭の中で彼女は思い出を生き直す。あ、マーガレットの花、彼はウイと言ったのに、なぜノンなの、本当にノンなの?……というように彼女の頭の中の声を観客に見せるようにします」

花占いをするジゼル。この楽しい思い出が狂気の中に蘇る。photo:Yonathan Kellerman/ Opéra national de Paris
今回のパリ・オペラ座の公演では狂気のシーンで髪のほどけ方を過去の舞台と違え、ビジュアル的により狂人感を増していた。毎回取り組むたびに物語に厚みを与える仕事に取り組むドロテ。文句のつけようのないテクニック、そして名女優ぶり。彼女のパートナーは、過去に何度もこの作品を一緒に踊っているマチュー・ガニオである。ふたりが一緒に踊る時、すべてが見事にシンクロし舞台の上にエレガンスが漂う。彼もまた芸術面で優れた仕事を見せるダンサーとして知られ、パリ・オペラ座を代表するダンスール・ノーブルゆえにプリンス役は板についている。技術も芸術面も優れた経験豊かなエトワールふたりによる哀しくも美しい舞台は、パリでも高く評価された。なおマチュー・ガニオがアルブレヒトを初めて踊ったのは、2006年。意外にも全幕を東京で踊るのは、これが初めてだそうだ。

キャリアの頂点にあるふたりによる美しい最後。photo:Svetlana Loboff/ Opéra national de Paris
---fadeinpager---
堂々たるミルタを踊るオニール八菜。
ウィリは結婚前に亡くなった若い娘たちの精霊。心に傷を負った娘たちである。男に裏切られ、心に傷を負った娘たちである。ローズマリーの枝をかざし、夜の森に迷い込んだ男たちを死ぬまで踊らせるのがウィリの女王ミルタ。ジゼルの墓参りに来たアルブレヒトも彼女が非情に踊らせて……。パリ・オペラ座の公演ではオニール八菜、ヴァランティーヌ・コラサント、セ・ウン・パクの3名がこの役を踊った。ヴァランティーヌとセ・ウンはオペラ・バスチーユの公演『バランシン』があり、東京の5公演のミルタ役はプルミエール・ダンスーズのオニール八菜に任されている。

ウィリたちを従えた女王ミルタ。photo:Yonathan Kellerman/ Opéra national de Paris
「ミルタの役はジャンプがほとんど。私はけっこう飛べるので振り付け面での問題はありません。でも、ミルタのキャラクターは私には無理!って、最初この役に配役された時に思いました」
初役で踊った時のことを振り返って、オニール八菜が語る。過去のオペラ座で誰もの記憶に残るミルタといったら、マリ=アニエス・ジロ。彼女とは正反対のタイプのダンサーといっていい。
「自分ならどうできるだろうか、とほかのミルタのビデオを見たりして研究したんです。ミルタもジゼルやほかのウィリ同様に受けた傷の痛みが心に残っていて、私は彼女を意地悪な女性だとは思いません。最初の登場のシーンでは哀しみを抱えるミルタを見せるようにしています。でもミルタ役が感じさせなければいけない責任感や重量感を出さないと、ウィリの女王ではなくジゼルになってしまう……(笑)。そのためには自分が思い描くミルタより強く見せる必要があるんですね。私は腕が華奢なので、上半身の姿勢や視線の仕事が大切でした」
みぞおちのあたりで手のひらを上に腕を組み、無表情なミルタ。パリの公演ではユーゴ・マルシャンとアマンディーヌ・アルビッソンというほかのカップルに比べて大柄なふたりに対しても、毅然と立ち向かうミルタ役を演じて仕事の成果を見せた。空間を浮遊するような彼女の踊りの美しさにも注目を!

アマンディーヌ・アルビッソンとユーゴ・マルシャン。photo:Yonathan Kelllerman/ Opéra national de Paris

ミルタの命令で、死ぬまで踊り続けなければならなくなるヒラリオン(写真はオードリック・ベザール)。photo:Yonathan Kellerman/ Opéra national de Paris
---fadeinpager---
芸術監督オレリー・デュポンも、コール・ド・バレエから主役まで。
『ジゼル』は1841年に初演されたバレエである。それから約180年近く踊られ続け、愛され続けている。オレリー・デュポンも現役時代、舞台に立っている。
「クラシック作品の中でいちばん数多く踊ったのが『ジゼル』です。コール・ド・バレエから始め、ジゼルの友達のひとり、ふたりのウィリスのひとり、ペザントのパ・ド・ドゥ……このパ・ド・ドゥは何度も踊ってもういい!というほど。そしてジゼル。ほぼすべてを踊ってきたのでジゼル役には問題なく入れました。
『ジゼル』ではニコラ・ル・リッシュと踊ったとても良い思い出がありますす。第2幕で、彼に素晴らしくホールドされて、自分が美しいと感じられました。ふたりが一体になったよう。まるで自分の身体が本当に宙に飛び立ってしまいそうに思われて……音楽も美しいでしょ、第2幕は。でもコール・ド・バレエ時代にウィリを踊った時には滑稽な思い出もあるのよ。ジゼルがお墓の前に膝まづくアルブレヒトに花をはらはらと落とすシーンがありますね。その後にウィリたちが登場するとき、私のポジションはちょうど花の落ちているお墓のところ。これ生の花なので滑るんです。足を取られて転ぶことがよくあって、馬鹿笑いが止まらなかったという思い出も……」
「ジゼルは『白鳥の湖』と同様、ダンサーにとって必ず踊るべき役といえます。クラシックバレエはすべてがきっちりと書かれていますけど、ほかの作品と違って『ジゼル』には芸術面でダンサーの自由に任されている部分が残されています。たとえば狂気のシーン。いろいろなことを試せる自由があります。それはとてもモダンなことですね。だからダンサーの皆がこの作品を踊りたいと願うことになるのです。そして第1幕と第2幕ではスタイルがまったく異なります。バレエによっては肉体的にとてもハードで、しかも芸術面の自由のない作品もありますけど、ジゼルは人物、 演技、技術、疲労……バランス良くすべてがこめられている役です。ジゼル役でよいダンサーなら、あらゆる作品においてよいダンサーといえますね。これはアルブレヒト役にも共通しています。今回の日本のジゼルの配役、素晴らしいでしょう。ぜひ、6名のエトワールを見に来てほしいです。すべての配役で見てほしいです」

第1幕、ジゼルの友達8名。右から3番目のビアンカ・スクダモア(スジェ)と5番目のナイス・デゥボスク(スジェ)はこれに加えてパリ公演でふたりのウィリスも踊り、オレリー・デュポンのコール・ド・バレエ時代と同じコースを歩んでいる。 photo:Yonathan Kellerman/ Opéra national de Paris
---fadeinpager---
『ジゼル』トリビア
19世紀のクラシックバレエらしく、パントマイムがいろいろ登場する。その中でも、覚えておくと話の進行がわかりやすい2つのマイムがある。ひとつは、顎の下を手の甲で撫でまわすようなマイム。第1幕の初っ端からヒラリオンがジゼルの住む家を指差し、このマイムをする。これは“美しい”という表現で、男性がすることが多い。もうひとつは、額の前あたりで両腕を回転させるマイム。これは“ダンス”という意味だ。第1幕では、どちらかというと「踊ってみせて」的に愛らしく使われるが、第2幕ではアルブレヒトに向かってミルタがこのマイムで、「踊れ!」と非情に命令をする。このほかのマイムは、たとえば左手の人差し指を右手で指し示すのは“婚約”というように、ストーリーの流れから、想像しやすいだろう。
パリ・オペラ座バレエ団では完璧なテクニックに加え、芸術面の仕事もダンサーたちは疎かにはしていない。それは主役だけに限らず。たとえば狩りの途中の休息のために村にやってきたクルランド大公に注目してみよう。配役されたダンサーにもよるが、パリ・オペラ座での公演でヤン・シャイユ演ずる大公は家から姿を現したジゼルの母ベルトに強い視線を送り、その後、何かを思い出そうとする様子を見せる。そして、去り際、跪くジゼルの前を通り過ぎた後、振り返り、彼女の顔を手で持ち上げてじっと見るというシーンも。パリ・オペラ座でジゼル役を何度も踊ったエトワールのアニエス・ルテスチュが現役時代に語っていたことだが、ジゼルはベルトと大公の間にできた子ども。ほんの一瞬でそれが物語られるのだが、これは見逃しても本筋には影響がないプラスアルファである。
【関連記事】
ジェルマン・ルーヴェの舞台に、誰もがフォーリンラブ!!
舞台裏ツアー付き! パリ・オペラ座来日公演チケット限定販売。
madameFIGARO.jpコントリビューティング・エディター
東京の出版社で女性誌の編集に携わった後、1990年に渡仏。フリーエディターとして活動した後、「フィガロジャポン」パリ支局長を務める。主な著書は『とっておきパリ左岸ガイド』(玉村豊男氏と共著/中央公論社刊)、『パリ・オペラ座バレエ物語』(CCCメディアハウス刊)。