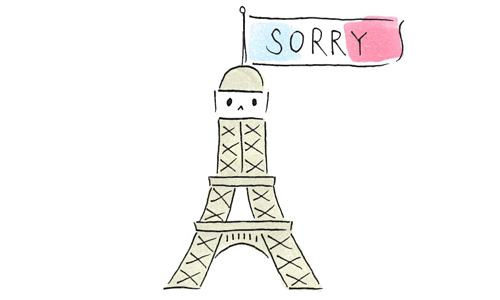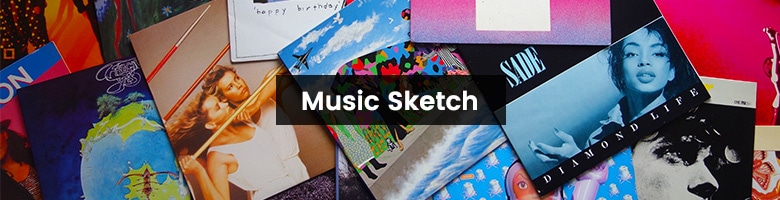
映画『AMY エイミー』を観て
Music Sketch
映画『AMY エイミー』が評判良い。第88回アカデミー賞長編ドキュメンタリー賞を受賞した、享年27歳で亡くなったエイミー・ワインハウスを取り上げた作品である。

キャッツアイをはじめ、レトロなファッションからも注目を浴びた。©Getty Images
自分が実際に取材したことのあるミュージシャンのドキュメンタリー映画を見ることは少なくはないが、これは本当に生々しい。感情のジェットコースターに乗っているかの如く、最初から最後まで心休まるシーンが少なく、揺さぶられる。ホーンセクションなどバンドを従えたステージでは大きく見えるエイミーだが、実際に会うと華奢で小柄。とても繊細な性格であることは一目見てわかったが、タトゥーを入れるほど大好きだった祖母の話など人懐っこい笑顔で話し、曲について詳しく聞くと、はにかんだ表情で答えてくれた。取材した2007年5月当時も恋人のブレイク・フィールダーと復縁するなど話題に事欠かなかったが、ただ、そこからの4年間が壮絶すぎて、あの細い身体でこれだけの人生を背負っていたのかと思うと、涙無くして見られない。
「Stronger Than Me」
この映画を見て何に一番驚いたかというと、そもそも彼女の人生自体がドラマチックとはいえ、プライヴェートな写真や映像、また当時の彼女が出演したラジオなどの音声が驚くほど多数盛り込まれ、リアリティが詰め込んであること。実際、5年前の死去以降、英国ではTV番組等で彼女の特集が複数組まれたため、それよりもより深く掘り下げる必要があったのだろうが、夫であったブレイクがお金目当てで写真素材など提供したのでは?と思いたくなるほどショッキングなものもある。

友人同士で音楽を楽しんでいた頃。友人のジュリエット・アシュビーが撮影。©Juliette Ashby
アシフ・カパディア監督の話によると、エイミーの最初のマネージャーで古くからの友人でもあったニック・シマンスキーと、幼なじみのジュリエット・アシュビーとローレン・ギルバートがこの企画に協力してくれたことが何より大きかったそうだ。当初は非協力だったため苦労したが、ニックを説得後、女友達の2人にはそこから9ヶ月かけて了解を得ることができ、エイミー・ワインハウスの真実を伝えるために、3年かけて制作したという。

ジョーン・バエズやキャロル・キングを愛聴していたデビュー前のエイミー。©Nick Shymansky
エイミー・ワインハウスといえば、スモーキーな歌声で魅了する歌唱力はもとより、自身の恋愛体験など私生活を赤裸々に歌にしていたことで知られる。複雑な家庭環境やドラッグ好きの恋人との関係に悩まされ、アルコール依存症や摂食障害になる一方で、2008年の第50回グラミー賞で最優秀新人賞や最優秀楽曲賞など5部門を受賞。子供の頃から幸せや安堵感に包まれる場所を求めつつ、挫折と栄光の狭間で常にギリギリな思いで生きてきた。
「Rehab」
レディー・ガガがイギリスへ行った時に、エイミー・ワインハウスに間違えられたからと、元の黒髪を金髪に変えたのは有名な話で、その頃からガガは彼女のことを気にしていたし(のちにエイミーはトニー・ベネットとデュエット曲を収録して話題になったが、その後、ガガも彼との共演アルバムを発表している)、アデルやサム・スミスなどに取材すると、「尊敬するエイミー・ワインハウスのように、自分の身に起こった真実だけを歌にしていきたい」と答えているほど、その影響力は大きい。"自分の人生から搾り出した楽曲、歌声だからこそ、より多くの人の心に訴えかけることができた"と、身を以て実証したシンガー・ソングライターであるからだ。

家族が撮影したエイミー。元々はお茶目な面も多かったそう。©Winehouse family
アシフ・カパディア監督は映画『アイルトン・セナ〜音速の彼方へ』で英国アカデミー賞最優秀ドキュメンタリー賞を受賞している。監督に「今回、女性のドキュメンタリー映画を手がけたことで、女性の人生は男性の生き様とは違うな、と思う点はありましたか?」と聞いてみたところ、次のような返事があった。
「やはり男性と女性では違うし、しかもその違いというのは今まであまり取り上げられていない。アイルトン・セナも、エイミー・ワインハウスも若くて才能のある人物だったけれど、男性か女性かであるというだけで全然違う。"アディクト(中毒)"になる過程も音楽業界だと特に顕著で、男性がやったら"イカすヤツ、クールなヤツ!"で終わるけど、女性は断罪される。エイミーの人生を約1000時間程のフッテージを通して見ているけれど、非常に不思議に思ったのが、ドラッグに溺れるようになったきっかけを作ったのは恋人だし、彼女が有名になってから、周りに支える女性がいなかったこと。女性の存在がいなくて、男性ばかりだった。だから少しでも周りに彼女を支える女性がいたら、状況は変わっていっただろうな、と、僕は思ったね。残念ながら母親はあまり彼女の人生の中で重要な役割を持てなかった。そこには彼女の幼少時期の父親との関係がいろいろと絡んでいると思うけれど、母親の存在も非常に希薄だったということで、女性がいなかった」

同じような家庭環境で育ち、惹かれ合ったというブレイクとエイミー。©Nick Shymansky
メディアに関しても言及してくれた。
「パパラッチやタブロイド紙の話でいえば、女性の扱いに関してはやはり辛辣。お酒やドラッグに関しても、エイミーは溺れていったわけだけど、身体も男性と違うから、男と同じように飲めないのに、飲むわけで。それに加えて摂食障害があったから、そこにもまた影響があったんじゃないかな。イギリスでは、マスコミに出始めた頃は少しふくよかだったから、いろいろからかわれていた。しかも過食嘔吐症も患っていたわけで。なのに、"ちゃんとセラピストに行け"とか、ステージに上がる前に"精神的にちゃんと安定しているのかな"と、チェックをする人はいなかった。やはり音楽業界で権力を持っているのは男性だということが、非常に大きく影響しているんじゃないかな」

2011年7月23日に心臓発作により死去。享年27歳だった。©Rex Features
カパディア監督は映画を取り出す前から人の心理というものに興味があり、「今回、エイミーはアーティストとしては非常にポジティヴだけれども、人としてはある種の"負け犬"だったわけで、負け犬の部分に興味を掻き立てられた」と話してくれた。また、エイミーはユダヤ人、監督はムスリム人のインド系という違いはあるものの、住んでいる場所が近く、同じエリアだけに「60年代、70年代ならまだしも、何で今この時代において麻薬に溺れる子がいて、それを責任もって対処する人間がいなかったんだろう、何でこんな事が起きてしまったんだろうという疑問が頭をよぎった」と言う。私は"エイミー=負け犬"というのがわからないが(家庭環境云々よりも、ドラッグに溺れたという意味だと思われるが)、"シンガー・ソングライターの多くは、幸せな時よりも悲しみに浸っている時の方が曲を生みやすい"という説があるように、スリリングな恋愛や人生を歩んでいたからこそ名曲を書けたのだと思う。ただその振り幅が振り切れて、大好きな音楽活動を蝕むほど精神に異常をきたしてしまったのが残念だ。
「Love is a losing game」
エイミー・ワインハウスの魂の歌は、今も多くの人の心を捉えて魅了する。辛いと感じながらも、つい聴き続けてしまうのは、歌の素晴らしさと併せてシンパシーに似た安堵感のような、居場所をそこに感じさせてくれるからだろうか。
ファンはもとより、1人の女性の恋愛模様や生き様を知るうえでも濃密なドキュメンタリー映画だと思う。
映画『AMY エイミー』予告
*To be continued