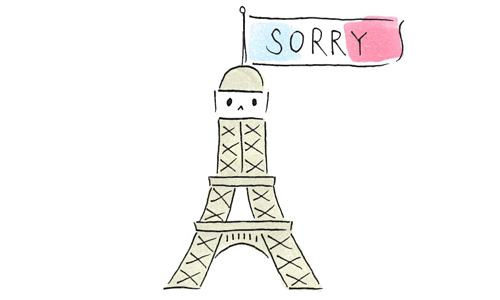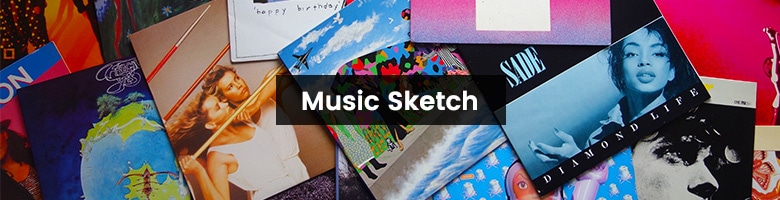
グラミー賞を受賞した、セイント・ヴィンセントにインタビュー
Music Sketch
St.Vincent(セイント・ヴィンセント)ことアニー・エリン・クラークの取材は前回に続く2回目。前回は理知的な印象が強かったため、今年2月に発表された第57回グラミー賞「最優秀オルタナティブ・ミュージック・アルバム」を受賞後に来日し、再会した時に、ここまでブッ飛んだ面白さがある人とは思わなかった。もちろん私は彼女のことを常に追いかけているわけではいないし、そんな短時間の取材でその人の何がわかるわけでもないのだけど。ただ、彼女が生み出す音楽のユニークさから言えば、捉えどころのない面白さは当然のことなのかもしれない。インタビューできたのは渋谷クラブクアトロ公演が始まる前の15分に満たない時間だったが、3年ぶりのインタビューなのに、私のことを覚えていてくれたのには驚いた。頭脳も記憶力も相当明晰なようだ。

以前に比べ、計算されたような動きで魅了していくセイント・ヴィンセント。2月20日、渋谷クラブクアトロで。
*****
■ ギターらしい音を出すことにこだわっていない
―最新アルバム『St.Vincent』(2014年)でのグラミー賞受賞、おめでとうございます。自分ではどこが評価されたと思いますか?
「ありがとう(笑顔)。理由は幾つかあると思うけど、このアルバムに収録された、みんなの記憶に残る楽曲が評価されたんじゃないかしら。今の時代は機材のおかげで、誰でも音楽を作ろうと思ったら結構簡単に作れる。でも、時代を超える楽曲を作ること自体は決してラクにはなっていないために、私の楽曲が評価されたのではないかと思うわ。あとは私が7年間で4枚のアルバムを出し、数多くのツアーを行なうなど、いろいろやってきた積み重ねの結果の評価ではないかしら」
―特筆すべきなのは、あなたが弾くギターの音色、そしてベース奏者がいなくて、ギターやキーボードを重視したバンド編成。自分のサウンドというものが確立できたと思ったのはいつ頃からですか?
「あっ、あなた、ギター弾くわよね? 覚えてるわ」
―えっ? ありがとうございます。今日は(ギターを)持って来なかったですけど(笑)。(前の取材の時に、次回は持って来るように言われていた)
「今も弾いているの?」
―はい、時々(赤面)。
「ほとんどのギタリストは右手のことを結構侮っているわよね。私は叔父(タック&パティのタック・アンドレス)の影響もあって、指で弾くことで可能な多様な表現を探求しているわ。さらにギターから出した音をいろいろ加工していくうちに、音がモンスターのようなキャラクターを持って出来上がっていく。アプローチとして、私は単なるノイズメイカーでしかなくて、ギターらしい音を出すことに全くこだわっていないの(笑)」
「Digital Witness」
■ 普通の曲にならないように、自分の耳や脳、指を騙してみる
―例えば「Regret」という曲では、ギターはもちろん、ドラムのスネアの音も加工している気がしていて。あなたが書いている歌詞も現実からインスピレーションを得てはいるものの、どこかフィクション的で、それはサウンドを加工している雰囲気と似ていると思います。自分でも加工すること、音をデジタライズすることで曲そのものをモンスター化しているとか?
「そうね。今回アルバムを作る上で一つ大きな自分のソースがあるといえば、テーマとして有機的なもの、つまり人間が弾いている音楽というものを如何に無機質な音にするか、それは鏡の向こうを通して音楽を人間的ではないものにするような......。それがこのアルバムのテーマだったの」
―「Birth in Reverse」のミュージックヴィデオにはその意図が感じられますよね。
「これは、元々ギターで書いた曲なんだけど、普通にやったら普通の曲になるから、自分自身の耳や脳、指を騙すために、敢えて変なチューニングにすることで、自分の慣れや弾き癖でギターを演奏しても違う結果が出てくるようにしたの。いろいろ試しながら作った曲よ」
「Birth In Reverse」
―1つ1つの曲のどれもが個性的な楽曲になっていますが、あなたにとって曲作りはどういう意味があるものだと思いますか?
「私にとって曲作りとは、自分の知識と直感的に出てくるものすべてを歌という楽曲の形の中に共存させること。それらは必ずしもとても融合しているわけではないけれど、自分にとっては大きな発想を一番完璧にする表現形態であり、その発想を伝える上での小さな媒介なの」
―前の3作目にあたるアルバム『Strange Mercy』(2011年)でインタビューした時は、「音楽は自分の苦悩やストレスを、自分を癒してくれるものへと変換してくれるもの」と話していましたが、今回のアルバムは前作に比べて特にまずメロディが美しく優雅で、ハーモニーもきれい、その分、サウンドの加工具合がより強調されていたので、音楽へ向かう気持ちが変わってきたのかなと。
「笑。そうね、前のアルバムを出したときよりハッピーになっているから。前作は悲しみの中で作った作品。今回はそれに比べると全然ハッピーだったからね」

ステージではセンターにお立ち台が用意され、そこで寝そべって歌うことも。右側に立つシンセサイザー、ギター、バックコーラスを担当する日本人Toko Yasuda(PLVS VLTRA / ex Enon、ex Blonde Redhead)も重要な役割を担っている。
■ バリシニコフと同じ振り付け師にステージを依頼
―デヴィッド・バーンとアルバム『Love This Giant』(2012年)を制作し、このツアーも回り、その時のバーンならではのシアトリカルなパフォーマンスもとても評判が良かったですよね。その後のあなたのソロ・ツアーをネットでチェックしていたら、そこから影響されたものを感じましたが、バーンと回ることで学んだことはありましたか?
「私のツアーでも、『Love The Giant』の時と同じ、アニー・B・パーソンというコレオグラファーを付けているの。ミハイル・バリシニコフのような著名なバレエ・ダンサーから、私のように全く舞踏経験の全くない人とも仕事をする人なのよ」
David Byrne & St. Vincent 「Who」
―自分のパフォーマンスにも取り入れるようにしたのは何故ですか?
「デヴィッド・バーンのツアーの時に、ホーン奏者などは凄く振り付けが決まっていて、私とデヴィッドもそれなりに振り付けはあるんだけど、でも私は歌わなきゃいけないので、どうしてもわりと同じ場所にずっと立って弾かなきゃならない。でも周りを見るとみんな楽しそうで、羨ましい気持ちになったの(笑)」
―(笑)。それで自分のショウも?
「自分の身体がここでこう動くとわかっていると、そこを意識しなくてもより感情に入り込めるのね。自意識が考えすぎなくて、歌に集中できる。あと動きがあることでドラマも生むし、潜在意識的にステージの演出にちょっとした物語性が生まれるから」
「Rattlesnake」TV番組『Late Show with DavidLetterman』出演時のもの
―そういえば、立ち姿もバレリーナのようだし、顔付きも変わってきましたね。
「そういってもらえて嬉しい。すぐにでも踊りたいわ(笑)。ありがとう。会えて良かったわ。次回はギターを弾いてね」
―(笑)あなたの曲をコピーしておきます。
「必ずね(笑)」

ギターを弾きまくる他に、お馴染みの観客へのダイヴも行なわれ、そこからステージに戻って華麗に演じていくパフォーマンスには魅了されるばかり。
*****
取材後にサインをもらった時にも、メッセージの最後に"Can't wait to hear YOU play."と書いていて、この人は本当にギターの話をするのが好きなんだなぁと実感。パフォーマンスすることへの美意識と音楽への情熱に満ちあふれたライヴを観た後は、楽曲をコピーすることさえ恐れ多いと感じてしまったけれど。
ここ最近は人気モデルのカーラ・デルヴィーニュと付き合っているという噂もあるが、天才肌の彼女のこと、何があっても不思議ではないと思ってしまう。全てを超越した独自の世界に棲んでいるような、そんな凄さがSt.Vincentの才能から感じられる。
4月1日発売の『St.Vincent

『St.Vincent
*Live Photo : MASANORI NARUSE
*To Be Continued