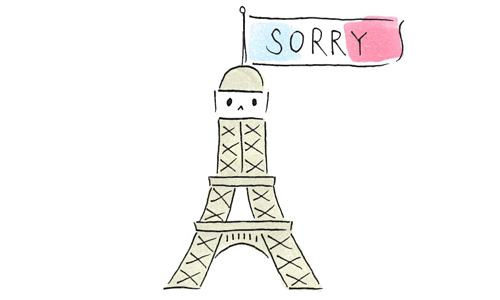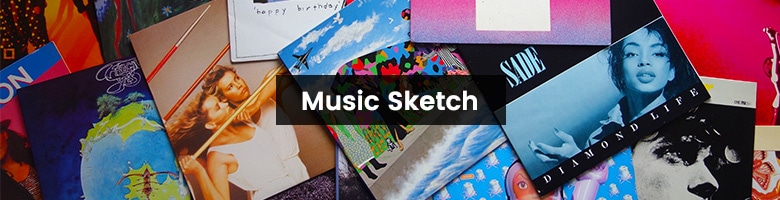
勝井祐二インタビュー ROVOの最新作『RAVO』について《後編》
Music Sketch
前回に続き、ROVOのメンバーである勝井祐二さん(Violin)に、最新アルバム『RAVO』について語っていただきます。
 今年5月に行われた日比谷野外音楽堂でのライヴシーン。ライヴ毎に新曲を演奏し、細部を微調整しながら楽曲をシェイプしていったそう。手前右がエレクトリック・バイオリンを演奏する勝井さん。
今年5月に行われた日比谷野外音楽堂でのライヴシーン。ライヴ毎に新曲を演奏し、細部を微調整しながら楽曲をシェイプしていったそう。手前右がエレクトリック・バイオリンを演奏する勝井さん。
――最新作『RAVO』はどの曲もオイシイ部分がギュッと濃縮されていますよね。
「去年の秋以降に主な新曲ができて、今までと違う曲調とかにまとめ上げていく過程でバンドメンバーに共通の着地点がだんだん見えてきて、バンドの方向性が共有出来て一緒になっていく感じがあって。曲を作って最初手探りで演奏していくと、やっぱり曲が長くなりがちなんですね。それをシェイプできたというのは、今年5月頭からツアーのリハーサルに入って、日比谷野外音楽堂でライヴをやって、そこからすぐに合宿してレコーディングという流れが効いてるというか。"ここに入っている曲をダンス・ミュージックとして届けたい"ということを制作中にみんなが共通に思っていて、そのすべてが収束したのが、5月のツアーからだったんですよ」
――曲をまとめる際に特に意識したことは?
「この作品はROVOの原点回帰なんですよね。これまで大作主義的な方向性もあったし、複雑なことを複雑に聴かせるみたいな表現もあったし。でも一番最初に僕と山本(精一)さんでバンドを作ろうと言った時は、"とにかくシンプルでミニマルなことをやろう"というのが動機だったので、1996年の結成から1周してそれに戻ったというか。ある種のフィジカルな表現だと思うんですけど、ダンス・ミュージックとして機能するわかりやすさというか。それにメロディの要素もあるし。ツアーから日比谷野音までの勢いでベーシック部分を録音しているんですけど、その後のポスト・プロダクションに結構手をかけていて、それが前作と一番違う点ですね」
丁寧かつ熱心にインタビューに答えてくれた勝井祐二さん。
――音が本当に緻密ですよね。
「1999年の初のフル・アルバム『imago』は、ほとんどポスト・プロダクションだけで出来ていて、曲が出来ていないセッションやリズムのアイディアを録って、スタジオの後でダビング、エディット、リミックスのようなコラージュのような作業で曲にしていった。曲によっては全員分の演奏が入っていないものもあるしね。それが僕らの出発点だから、そういうところも今回やりたいと思って。今はライヴバンドなので、ライヴで曲を育てていくけど、録音芸術にもちゃんと正面から取り組んでアルバムらしいアルバムを作りたかったから、ポスト・プロダクションも重視した。これは、今やれることを全部やったアルバムなんですよ」
――だから聴いていくと、細かくさまざまな音が入っていますよね。音の足し引きは最終的にはどうしているのですか?
「ダビングは自己申告制なんです。でも最終的には僕と益子さんと山本さんで、結構カットしたりもします」
――そういったレコーディング・スタイルだからこそ楽しめる実験性もあり、構成の面白さもあるという。
「それは本当にそう思う。でもバンドのアンサンブルは人前で何回も演奏しないとまとまらない、というのも確実にある。だから、その両方をやりたかったんですよ」
 ROVOの最新アルバム『RAVO』。
ROVOの最新アルバム『RAVO』。
――贅沢なアルバムですね。
「木の中に彫刻が埋まっている感じ。そこにあるものを継ぎ足すというより、その中から探り出すという。それを削って中から出していくというか」
――今回の曲順もベストだと思います。
「僕もそう思います。僕が考えましたから(笑)。『Shino+』で明るく終わるのがいい」
 ROVOはライヴ・バンドとしての人気が高く、日本でのツアーやフェスはもちろん、海外でのツアーやフェスも評判。ライヴDVDも発売されている。
ROVOはライヴ・バンドとしての人気が高く、日本でのツアーやフェスはもちろん、海外でのツアーやフェスも評判。ライヴDVDも発売されている。
最新作『RAVO』は、まさにコズミックな空間でダンスを楽しむような、さまざまな音の粒子やグルーヴと戯れながら別世界へ誘引される快感に溢れています。今週末の11月21日(日)には、東京・恵比寿リキッドルームにてライヴがあるので、興味が湧いてきたら、ぜひ体感してみてください。絶対に楽しめますよ。
次回では、ソロ・アーティストとしても長年活躍してきた勝井祐二さんのお話を紹介します。
* LIVE PHOTO: Wataru Umeda
*To Be Continued