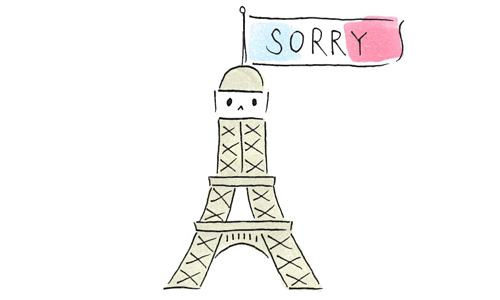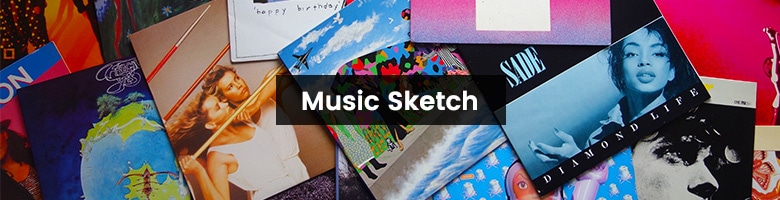
トミー・ゲレロ 気鋭の最新作を語る
Music Sketch
ファッション/サブカルチャーをリンクさせたことからも、アメリカ西海岸のストリート・カルチャーシーンでカリスマ的人気を誇るトミー・ゲレロ。ジャック・ジョンソンとともに名前が挙がることが多いですが、彼のルーツはスケートボードであり、マインド的にはオン・ザ・エッジなスピリットを持っていると感じます。心地よいギター・アンサンブルと繊細なビーツから生まれるグルーヴ、心に沁みるメランコリックな音楽世界を基盤にしつつ、毎回異なったアプローチでアルバム制作に励んでいるトミー。最新作『リヴィング・ダート』はひとりですべての楽器を演奏し、しかも無の境地である白紙の状態からたった5日間という短期間で音楽をクリエイトした作品になりました。
雨の日の渋谷で取材。トミー本人がベストショット!と気に入ってくれた1枚。
――作業の中でいちばん大変だったのは何ですか?
「全部ハードだった。曲を何も書いていなくて、何のアイデアもなく、何のアプローチもなく、スタジオでインプロヴァイゼイションを繰り返しながら、その場で決めていった。いちばん重視したのはダイナミクス。べース、ギター、パーカッション、キーボード・・・・・・と、1人で全楽器を演奏したから、他のミュージシャンとの間から生まれる空気がない。だから、そのエネルギーを1人で作り出さなくてはならないのが難しかった」
――今回は、ループペダル含め、できるだけアナログに近い機材を使ってレコーディングしたそうですね。それだけに、1人での作業にはより手間がかかったと思いますが、そこまでアナログにこだわった理由は何ですか?
「僕も現代の生活の中ではコンピュータの前に長く座っていることが多い。だから、その生活からちょっとでも脱出できればいいと思う。多くの人がシーケンサーやプログラミングを使っているけど、僕は敢えて2度と同じことを作り出せないよう、違うやり方をしている。全くメモリーのない機材を使っているから、作る曲が毎回少しずつ違う。でも、それがいいと思うんだ。僕らは人間だから、どこかに愛情とかニュアンスが必要なんじゃないかな、人間だって、何かする時に全く同じやり方をしない。たとえばあるポップ・バンドが同じ曲を何週間もリハをして、それからライヴで演奏していたら、その時にはその曲に対するスピリットが沈んでしまう。僕はそういうのには興味がない。音楽はそういうものだとは思わないから。いろんな複雑なことができる機械よりは、onかoffぐらいのレベルがちょうどいいと思う」
ライヴ・パフォーマンスでも楽器に囲まれて1人で演奏。
――すべてライヴレコーディングしたのですか?
「編集もオーバーダビングもしていなくて、全部演奏を通して録音していて、その中でいちばんいいと思うものをミックスしたんだ」
――即興演奏から曲が生まれ、しかも歌詞もないので、曲のタイトルを付けるインスピレーションはどこから得ているのですか? それとも演奏する前に、ある程度世界観をイメージしてから始めるのですか?
「最初にイメージすることはないね。すべて人生からヒントを得ているよ。自分の取り巻く状況だったり、世の中で起こっている出来事、そういったものからインスピレーションを受けている。世界中がネガティヴなもので溢れているけど、僕はいつもそういうことについて考えていて、あとは・・・・・・自分が感じていることが表に出てきているんだと思う。たとえば『BURN BRIGHT IN DARK DAYS』だと、非常に精神的に落ち込んでいる時に、どうやって自分の気持ちを持ち上げていくかを考えながら付けたんだ」
――ラテン語のタイトル「AUT VIAM INVENIAM AUT FACIAM(道は自分で見つけるか、自分で切り開く)」は、どのように考えて付けたのですか?
「このフレーズは、KROOKEDというスケートボードのブランドのデザインをしていた時に、ラテン語のフレーズについて調べていて発見したんだ。そして、自分の信念にとても共感できる言葉だと思ったんだよね。自分が信じているDIY(Do It Yourself)という精神に非常に共鳴するような内容だったんだ」
――この曲は、アルバムの中で最もビートが強調されたノイジーなサウンドですよね? 曲を完成し終えた時に、このタイトルがピッタリだったという?
「そうだね。すべての曲から考えると、あの曲がピッタリだったんだ。ノリがいいから。僕の場合、作っている音楽に歌詞がないから、ある意味タイトルが自分の内面を反映しているんだ」
繊細で乾いた音を響かせながら、どこか幻想的な雰囲気を放つギターサウンドには、一度耳にしたら忘れられない美しさがあります。
――以前インタビューした時に、「自分に誠実になればなるほどメランコリーな音楽になる」と話していましたが、今回も全般的にそうなっていますよね?
「(笑)。作業が終わってからアルバムを通して聴いた時に、結構ダークなムードになっていると初めて気づいたんだ。全く意図的ではなかったんだけど。ただ、僕はクリエイティヴでいるためには、感情を表現しなくてはならないし、正直で自分に忠実でないといいものはできないと思う。そして大事なのは、リスナーがその感情を見たり、知ったり、感じ取れないといけないと思うんだ。僕は自然とそれを表現できていると思うんだけど」
――メランコリーな仕上がりにはなっていますが、音楽はセラピーであり、最終的に自分をポジティヴに持っていく手段になっていますよね?
「そうだね、そう思うね。音楽を聴くといろんな感情を味わうことができるし、曲を作ったり、演奏したりすることも瞬間的にセラピー効果がある。特に他のミュージシャンと演奏していると、夜通し何時間でも演奏できてしまうからね。何も考えずに心から楽しんで、いろんな感情を味わえる瞬間が、僕にとってセラピーになるんだと思う。これは僕にとってスケートボードと共通するところがあって、何も考えずに瞬間を楽しんでいるものなんだ」
とても接しやすい人柄。特に息子が生まれてから、さらにフレンドリーになったような。
――以前、音楽とスケートボードの共通点について「流れているもの」と話していましたが。
「音楽をやっている時は、意識をほとんどしていない。確かに内向的で自分を見つめることもあるけど、何かを強く意識するとか、客観視しているつもりはない。もちろん作品ができてから気づくことはあるけど。スケートボードも同じで、何も考えていない状態で、ただ身体が動く。そういう意味で双方は似ていると思うよ」
――あなたの人生を生きやすくするために音楽を作り出している感じですか?
「違うね、場合によるね。今、自分の思い通りに音楽を演奏していない、作り出していないという思いが強い。もっと演奏したいし、他の人とライヴをしたいしね。僕にとって音楽はスケートボードと同じで、"いつかこうありたいという目標を与えてくれるもの"だけど、人生というのはとても細分化されていて、仕事に行っている自分、家族と過ごしている自分、音楽をやっている自分といった、いろんな自分がいて、思い通りに音楽ができないことがフラストレーションになっている。演奏するのはすごく好きだけど、うまくなりたい欲求もあって、いつか座ってジャズギターをトゥルルルル~っていうふうに弾けるようになりたいんだ(笑)。ただ時間がなくて、あまりできていないんだけどね。今はそこへ向かって進んでいる感じさ」
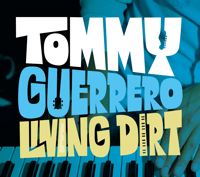 最新アルバム『Living Dirt』。全部即興演奏といっても、どこかデザインされたような美意識を感じさせる作品。
最新アルバム『Living Dirt』。全部即興演奏といっても、どこかデザインされたような美意識を感じさせる作品。
Live Photo:レコード会社提供
*To be continued