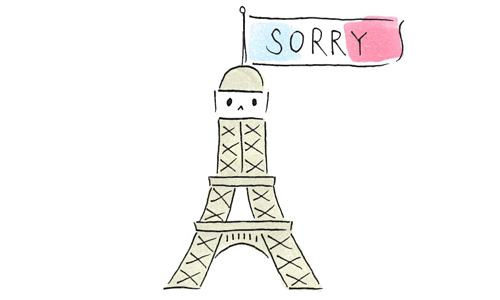齊藤 工―移動映画館 シネマバード、海外へ。
インタビュー
1999年、19歳だった齊藤工はパリを拠点にヨーロッパのエージェントに所属し、モデルとしてのポテンシャルを探っていた。つてのない中、メゾンのオーディションを片っ端から受けた。自分に何ができるか、未来に向けての武者修行の時期と言えるだろう。
2017年1月、前回の滞在ではオーディションの最終オーディションまでしかたどり着けなかったルイ・ヴィトンにより、2017秋冬メンズコレクションにゲストとしてパリへ招聘された。
この数日間のパリ滞在の後、彼は南インド洋に浮かぶマダガスカル島へ飛んだ。
映画館のない地域に住む人たちに向け、彼は定期的に「移動映画館cinema bird」という活動を続けている。その精神に賛同したJICA(国際協力機構)とテレビ局からマダガスカルの子どもたちへの移動映画館を依頼されたのだ。そこで彼が目にした光景とは?
そして、2017年は「齊藤工」名義で4Kオリジナル映画『blank13』も発表する。キャストは高橋一生とリリー・フランキー等。映画の楽しさを多くの人と共有したい。彼の枠にとらわれない活動と発想の源を聞いた。
マイナスから発信すると飛距離が出る。
2016年の12月31日に『絶対に笑ってはいけない科学博士24時!』(日本テレビ系)にサンシャイン斎藤として出演して、大きな反響をいただいたんですけど、あの時はテレビの向こうをまったく意識せず、とにかく目の前にいるダウンタウンのふたりを命がけで笑わせる、その一瞬に集中した仕事でした。それが世間に広まった、ということを体験し、やっぱり表現というのは「マジョリティに向けた大きな表現」よりも、「マイノリティからマイノリティへと狭めていく」ほうが届く人には届くんだな、と実感しました。僕は最近、心が動いた瞬間のことをメモするようにしているんですけど、バラエティに出たり、1月のルイ・ヴィトンのパリコレクションでグザヴィエ・ドランと会って話をして通じた瞬間を記録することは、自分の心の形成だと思う。それこそが「作る」ということかと。

いちばん左がグザヴィエ・ドラン監督。

ルイ・ヴィトンのメンズコレクション アーティスティック・ディレクターの、キム・ジョーンズと。
3月5日にゆうばり国際映画祭に行ってきたのですが、その時も「ジャスティス!」と声をかけられました。自分としては、そういう固定されたイメージを持たれることは、決して悪いことじゃないと思っています。そもそも、「本当は俺、こういう人間じゃない」というパブリックイメージさえなかった時代が長かったので。それにある固定のイメージがあると、この次、振り子のように、対極に大きく飛ぶことができる。「ゼロ地点から発信する」よりも、「マイナスから発信」したほうが飛距離が出るんですよね。その対象が映画でもドラマでもファッションでもなく、バラエティだったのが僕らしいのかもしれません。
マイノリティの目線を持つこと。
先ほども言ったように、僕は不特定多数の大勢の人に向かって広い表現を目指すよりも、特定の人に狭い範囲でいいから深い表現をすることが大切だと思っています。
先日のパリ滞在中、ルネ・マグリット展を目指して美術館に行ったのですが、そこで抽象画家のサイ・トゥオンブリーの回顧展をしていたので、そちらも見たんです。最初のコーナーでは僕の甥っ子が1歳の時に描いたもののほうが、まだうまいよっていうくらい、単なる落書きにしか見えないものだったんですけど、どんどん作風が深化していく過程をみせる構成でした。後で知ったのですが、彼は自ら死を選んだのです。彼の絵を見ながら感じたのは、俳優という僕の職業とまったく違うな、と。それは何かというと、「これでよし」という感覚をもって作品を終わらせるファイナルワークの在り方。毎回、これで作品を終わらせるための、句読点の「。」を打っていく作業を、どう見ても未完成なのに絵として完成させている、という……。その作業の連続を見ているうちに、気づいたら涙があふれていて、マグリット目当てでここに来たのに、おまけに、これからアフリカに行くというのに、こんな重い資料を買うなんて、と自分で呆れながらも図録を購入しました。心が震えました。僕は日本でも美術館になるべく行くようにしているんですけど、パリの美術館って、周囲の街に溶け込んでいるというか、共存していて、まるでチェーン店のうどん屋に行くような気軽さで美術館が存在している。そこに憧れます。
とはいえ、日本の美術も遡れば遡るほど、自然や農業と共存していて、芸術に寄り添った暮らしをしている民族なんだなとパリで気づかされた。そういう意味で、自分の生活している半径だけでは理解しづらいものがある。そこに国外へ出る意味があるし、マイノリティの目線を持つ意味があると思います。日本の美術館に平日に行って、あれだけの広い場所にポツンとひとり立つと、空間の方が主導権を持っていて、自分の小ささを思い知らされる。そういう体験はとても大切だと感じています。
マダガスカルでの移動映画館。

1月、パリコレクションを見た後、マダガスカルに飛びました。
JICAからの依頼だったのですが、僕が行って何ができるか、他の人ができることをやっても意味がないなと考え、数年前から日本国内で続けている「映画館のない地域に移動映画館を持って行って上映の場を作る」という試みを、マダガスカルの子どもに向けて開催することにしました。僕が行った小学校は、舗装された道に辿り着くまで40分もかかるサバンナの中にあって、子どもたちの半分は裸足で学校に通っている。給食がないので、子どもは昼に家に戻って食事をとり、また学校に戻るという場所だった。
そんな中で、ただ映画作品を持って行って観てもらうだけじゃなく、映像をみんなに作ってもらうことから始めることにしました。まずは未来の自分の絵を心の中で描いてもらって、どうなっていきたいか考えてもらい、それを演じる人、撮る人、監督がいて、録音担当がいて、ヘアメイクもいる。これらはすべて、この子たちが生まれて初めて見る職業で、それを体験してもらうことが狙いです。


知り合いに、カンボジアで移動映画館の活動をしている人がいます。カンボジアの僻地に行って、子どもたちに将来の夢を聞くと、「先生かお医者さん」って言うんだけど、それはその職業しか知らないから。ここがまさに僕が続けている移動映画館を、日本国内で映上映をすることと、発展途上国に持っていく場合は「やるべきこと」が異なる、という点なのです。
映画を上映することで、世界にはたくさんの職業があることを知ってもらえる。上映後にワークショップを行い、ヘアメイクなど体験してもらって、子どもたちの夢の選択肢を増やすきっかけづくりをしたいんです。その意味で、移動映画館というものは、場所によって厚みが変わってくる、と、応援したい気持ちで臨みました。
やってみて感じたのは、マダガスカルの子どもたちの反応。「興奮!」の一言に尽きます。



生まれて初めて映画を見る子どもたち、なおかつ、自分たちの姿がそこに投影されている。もう大変な興奮で観てくれました。この番組は3月26日、BSフジでオンエアされるので、ぜひ、多くの人に観ていただきたいです。
映画娯楽を人と共有すること。
マダガスカルの体験を通して、僕は俳優という表で演じる仕事をし、ディレクションもしていますが、実は映画娯楽を人と共有することがいちばん性に合っているんじゃないか、と再認識しました。国内で移動映画館を続けているのもそういうことです。
いまミニシアターがどんどん減っていて、まさか渋谷にあったアート系映画館の代表格だったシネマライズがなくなる時代がくるなんて、10年前には夢にも思っていなかったんですけど、このことは僕にとってはSMAP解散と同じくらいショックだった。
2016年は移動映画館を福島県南相馬と大分で開催しましたが、大分はお寺での上映会で、この体験を通し、「あ、お寺って映画館になりうる」と気付いたんです。ひとつに、和紙って音を逃がさない。お経を読んだり、太鼓の音を響かせることを計算された空間として作られていて、とても音響効果がよかったんです。僕らはこれまで、自治体と交渉して学校などの場所を借りて移動映画館をしてきたんですけど、お寺の場合は、住職の方の意思と地域の人の上映をしたいという思いさえあれば、かなりスピーディに開催までこぎつけられる。いま、全国の映画館はどんどんなくなっているけれど、お寺はどこにもある。離島にもある。そこに映画の上映の場としての活路を見出したんです。


シネコンの劇場で、封切間もないのに、閑古鳥が鳴いている状況に時々出合います。映画の宣伝は初日と2日目の動員に対する宣伝がメインで、その数字とランキングの順位ばかりが話題になるけど、それは既存の映画館のための不健全なシステムだと僕自身は思っていて。観たい時に、観たいエンタメと触れられる場所を創ることのほうが重要だと思う。ニーズはあるのに、それがうまく機能していない、偏っているのが日本の映画配給システムだなと。映画館側の事情で作られた映画は、観たい人の日常のニーズと合ってないんじゃないか。才能はあるけど、若くて無名な映画作家の、劇場公開されない邦画作品が蠢いている中、お寺という即席のミニシアターが日本全国根付いていけたらいいな、と思います。僕が死んだ後までも根付いたら、きっと面白いアミューズメントになるんじゃないか。
昨年、河瀨直美監督の短編に出演し、奈良の東大寺での上映体験をする貴重な機会を得たのですが、その時、東大寺の方に、「お寺というのは昔から何かを発表したり、人が集まるべきところ」と伺って、さらにお寺映画館への普及に力を注ぎたいと思いましたね。
高橋一生主演の初長編映画を監督。
2016年の秋、70分の作品を監督しました。
『blank13』は、脚本家のはしもとこうじさんの実体験を元にした物語で、彼が小学校の時、お父さんが煙草を買いに行ったきり戻って来なくて、13年後、突然戻ってきたというエピソードに基づいています。事実に基づくという強さがあるのは計算していたことですが、高橋一生さん、リリー・フランキーさんをはじめ、役者さんがリアルを超える表現をしてくれて、撮影中は「圧巻!」と感じることが多かったです。高橋さんをはじめ、台詞にない言葉がどんどん出てきて、監督として「カット」とやり取りを途切れさせるのがはばかられるくらい。後半はほぼアドリブの応酬です。お葬式の場面で、息子が知らなかった父親の知り合いがやってきて、いろいろと語っていくのですが、佐藤次郎さんは面白いし、村上淳さんは僕が告げてもなかったことを明かしたりとか、もう、獣たちが跋扈して、奇天烈な演技を披露してくれている。自分が想像していたよりも生っぽい映画になりそうです。
監督として心がけていたのは、日本ぐらい、方程式で作る国はないなと思っているので、それを壊すところから始めたいなということでした。音楽はRIZEの金子ノブアキさんに依頼したのですが、彼はRIZE以外にもノスタルジックな音楽を作っています。たとえば、ひとりで7つの楽器を駆使して曲を創ったりするんです。その彼が物語の構造上、後半ものすごくパンクなところで、「敢えて音を抜こう」と提案してくれたことにも刺激されました。
「前半は音の演出を巧みに入れて、後半は音をなくし、強気で攻めた方がいい」と……。
ここにきて、足し算じゃなく、引き算を選んでいて、でもこういうチャレンジができることはうれしかった。イメージにとらわれず、毎日探求心の赴くまま、意識的にゼロから自由に飛んでいる気がします。
なお、齊藤工がルイ・ヴィトンを纏い、パリのカフェで撮影されたファッションポートレート&独占インタビュー「パリの街とセッションする、ということ。」は、現在書店に並ぶフィガロジャポン最新号2017年5月号(3月20日発売)P322~327に掲載。
texte:YUKA KIMBARA