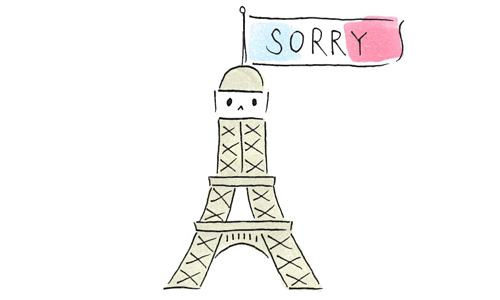『リトル・ジョー』が描く幸福と母性、クリエイション。
インタビュー
バイオ企業で“人々を幸福にする”新種の花の開発に成功した研究者アリス。まもなく彼女は、その花の花粉を吸った息子や仲間たちが奇妙な行動をとりはじめたことに気付く――。2019年のカンヌ国際映画祭で最優秀女優賞を受賞した心理スリラー『リトル・ジョー』。この作品で注目される、オーストリアの気鋭ジェシカ・ハウスナー監督にインタビュー。

人を幸福にする新種の花“リトル・ジョー”とは?
幸福とは、自分たちの頭の中にあるもの。
――『リトル・ジョー』はSFともいえますが、いっぽうで個人的で感覚的な「幸福」という概念に疑問を投げかけていますね。日本でも公開された『ルルドの泉で』(09年)でも奇跡を通して幸せを掴もうとする人々が描かれました。
人は、概念によって突き動かされているんじゃないかと私は思うんです。幸福は、現代的な概念。我々現代人は“みんな幸せになるべきだ”と思っているところがあって、昔に比べると、幸福を求める気持ちに突き動かされて行動しているように感じます。私は映画を作る時に、自分たちが生きている世界や、その世界はどのようにかたちづくられているのかを表現したいと思っているんです。

本作が長編5作目となるジェシカ・ハウスナー監督。
――そうした“幸福”を安易に求める現代社会の風刺でもありますか?
なぜ、人間がそんな行動をしているのか、といった概念を暴こうしているのは、間違いないですね。実は、幸福は自分たちの頭の中にだけにあるものだということを人間は忘れがち。つまり、求めているもの、信じているものを真実だと決めてしまう。本当の真実と、人々が望む真実の関係に私は興味があるんです。
たとえば、カンヌ国際映画祭で私にインタビューしたあるジャーナリストが、“幸せを見せます”と海辺の美しい別荘を見せてくれました。おもしろいと思いました。つまり、海辺の家が幸せなのではなく、スマートフォンの中にある海辺の別荘の写真が彼にとっての幸せなんです。海辺の別荘に行った時に、どんな美しい体験ができるのか、その期待感が幸せなんです。実際には、雨が降っていたり、石につまづいたり、いい体験にならないこともあるかもしれない。

主演のエミリー・ビーチャムは、本作で第72回カンヌ国際映画祭女優賞を受賞。
――美しい真紅の花の花粉が、静かに人々を変容させていく様子が不気味ですね。花というある意味、静的ともいえる植物を核に用いた理由はなんですか?
膨大なリサーチをした末に、花に決めました。当初はいろいろな案があって、リンゴもそのひとつでした。自分自身に種がなくても実を作れるというところが、最高だと思ったのですが、リンゴは人間が能動的にかじるという行為が必要となるのでやめました。それよりも花であれば、香りなどを気が付かないうちに吸い込んでしまうこともある。それがよりストーリーに機能すると思った。気付かないうちにいかに影響を受けているのかということを、掘り下げたかったんです。

エミリー・ビーチャム扮する研究者アリス(左)と、ベン・ウィショー演じる助手のクリス(右)。
---fadeinpager---
“何かを生み出す”ことは本来、女性的なこと。
――SFスリラーやホラーは、古典的な題材でもありますね。たとえば、永遠の命を求める『フランケンシュタイン』とか。このジャンルに興味を持った理由は?
『フランケンシュタイン』は、創造主と創造物との関係が興味を惹かれる点でした。実は『リトル・ジョー』とは、テーマというより、女性の視点で描くことを選ぶうえで関係しているんです。
子どもの頃、クリスマスに親が世界の偉大なる発明者たちという本を贈ってくれたのですが、目次を見ると、キュリー夫人以外全員男性でした。“名前が出る価値がある女性は、ひとりだけ”――そういう男性社会で私も育ってきた。いまは変わりつつあるとはいえ、女性が自分で何かを創造する物語は必要だと思っていました。メアリー・シェリー(『フランケンシュタイン』の著者)も実は、女性を主人公にしたかったんじゃないかと思う。でも当時、本を売ろうとしたら、女性の科学者がフランケンシュタインをつくるという物語にはできなかったのではないでしょうか。でも、女性が子どもを産むということを考えれば、“何かを生み出す”のは女性的概念なんです。

アリスは、愛息ジョー(左/キット・コナー)にちなんで、花を“リトル・ジョー”と名付ける。

“リトル・ジョー”が成長するにつれ、ジョーは奇妙な行動をとりはじめる……。
――母親と子どもとの関係も『リトル・ジョー』の興味深いテーマですね。仕事をしているからかまってやれない、ごはんも作ってあげられない。主人公のアリスは常にシングルマザーとして負い目を感じていますが、花の影響によって“いい母親になる”という概念を捨て去ります。これは、女性が“いい母親でなければならない”というオブセッションを社会から押し付けられているということに対する批判的なメッセージを込めたのでしょうか。
ええ、そのとおり。しかもあなたが“概念を捨て去る”という表現をしてくれたのは、うれしいですね。彼女は、いい母親としての概念を捨て去っただけで、子どもを捨て去ったわけではないんです。アリスが、燦々と光り輝く母親像を捨て去ったことへの理解はとても重要。なぜならば、女性に押し付けられた概念を捨て去るという行為は、私たち女性が自分でしなければならないことだからです。
仕事を持つ母親が罪悪感を感じなくなるような社会がくるまで待っているのは、すごく長い時間がかかる。私たちは、母親が子どもを慰めるためにだけ存在しているだという概念を、捨てなければいけない。だいたいいまの時代にそれは不可能だし、女性が目指すゴールとしても魅力的じゃない。私は、10歳になる子どもがいますが、いつも自分を父親だと思うようにする、というシンプルなトリックを使っています。そうすると罪悪感は消え、私は子どもも愛しているし、仕事も献身的にやっている、と肯定的に捉えられるんです。

“リトル・ジョー”の鮮やかな赤をはじめとする独特の配色が、お伽話のようなムードを演出する。

『リトル・ジョー』はシングルマザーとして悩みを抱えて働く女性の物語でもある。
1972年、オーストリア・ウィーン生まれ。The Film Academiy of Viennaで監督業を学び、在学中に映画賞受賞作の短編『FLORA』(1996年)『INTER-VIEW』(99年)を制作。2001年、長編初監督作『Lovely Rita ラブリー・リタ』がカンヌ国際映画祭ある視点部門に出品。2作目『Hotel ホテル』(04年)もカンヌ国際映画祭ある視点部門で上映された。09年、『ルルドの泉で』がヴェネツィア国際映画祭コンペティション部門に出品され、国際映画批評家連盟賞を受賞。14年には『AMOUR FOU』(原題)が再びカンヌ国際映画祭ある視点部門でプレミア上映された。
●監督/ジェシカ・ハウスナー
●出演/エミリー・ビーチャム、ベン・ウィショー、ケリー・フォックスほか
●2019年、オーストリア・イギリス・ドイツ映画
●105分
●配給/ツイン
●7月17日(金)より、アップリンク渋谷、アップリンク吉祥寺ほか全国にて公開
http://littlejoe.jp
© COOP99 FILMPRODUKTION GMBH / LITTLE JOE PRODUCTIONS LTD / ESSENTIAL
FILMPRODUKTION GMBH / BRITISH BROADCASTING CORPORATION / THE BRITISH
FILM INSTITUTE 2019
【関連記事】
花に支配される!? 耽美なスリラー『リトル・ジョー』
interview et texte : ATSUKO TATSUTA