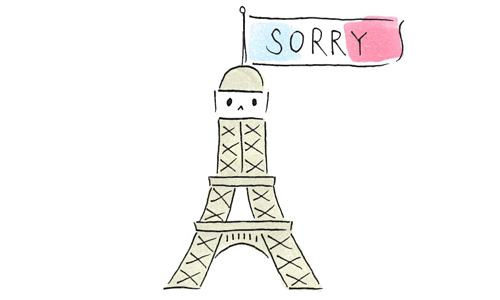カテゴライズ不要の水原希子が、役者として大切にしていることって?
インタビュー
世界最大級のストリーミング配信Netflixが、今年初めて打ち出す日本発のオリジナル映画、廣木隆一監督作『彼女』。高校時代に恋い焦がれた同級生から、夫殺しを持ちかけられる永澤レイ役に水原希子。レイの恋心を自覚して、人としての一線を超えさせる篠田七恵役に佐藤ほなみ。美容整形外科医としての地位も、愛情深いパートナー(真木よう子)との生活も一瞬で手放してしまうレイ。長年DVを受け続け、レイと逃亡という道を選ぶ七恵。2007年から5年にわたって連載された中村珍の漫画『羣青』を原作に、あまりにも濃厚で、危険で、激しい道行きに、観客は否応なく巻き込まれてしまう。レイ役、水原希子に話を聞いた。

ピアス ¥110,000/シャルロット シェネ(エドスロトーム オフィス)、他スタイリスト私物
果たして私はこの作品に賭けられるのか、自分自身を試したかった
――水原さんとNetflixといえば、依頼人の人生を再生させる『クィア・アイin Japan!』でのガイド役で見せたハッピーガールのイメージが全世界の視聴者にすでに伝わっていると思います。今回の『彼女』ではそのイメージを一変させる、想っていた女性の夫殺しに手を染めるレイという女性を演じています。演じるには躊躇する設定だったのではないかと思うのですが、このタイミングでチャレンジした動機を教えてください。
『ノルウェイの森』(2010年)『ヘルタースケルター』(12年)から数えて10年近く演じて来たのに、「役者の仕事をやっている」という気が全くなかったんです。モデルの仕事もしているし、ファッションに興味もあったし、アートにも関心があって、旅行もしたかった。自分の人生でやりたいことを同時進行でやっていたんですけど、日本でいう役者さんって、コンスタントにずっと映画に出て、舞台にも出て、と。そういう方たちと比べると、「自分を役者と言っていいんだろうか」という気持ちがあったんです。
『彼女』の話をいただいた時、果たして自分はこの作品に賭けられるのか、自分自身をテストするという意味も含めて、自問自答しました。もちろん物語の内容を見せていただいて、「こんな物語はいままで見たことなかったな」と感じたし、苦しい話ではあるんだけど、最後に見えてくる景色がレイと七恵のふたりにしかわからないんだけど、彼女たちだけの愛の形を表現したら、すごくおもしろいものになるだろうなと。そういう意味で、役者として、そして個人の水原希子として、自分はこれをやれるのかと、チャレンジが多かったと思います。
---fadeinpager---

七恵の夫を殺害し、逃避行を続けるレイと七恵。七恵が寝入った間に、レイはある決意をする。
――『クィア・アイin Japan!』の中で水原さんが、出演した50代の女性に代わって、日本の女性が置かれている年齢の格差や、不平等さを語っていたことがいまも頭に残っています。『彼女』も対等ではない関係性でねじれる愛情のアンバランスさを描いていますね。
それは七恵が感じていることで、レイ自身は気付いていません。だから七恵の中に「あんたのそんなところが嫌なんだ」という感情が起きる。門脇麦さんと出演した『あのこは貴族』もそうだけど、いろんな人生があって、互いの間に横たわる不平等さをすべて分かり合うなんて無理なんだけど、それでもちょっとだけ、他者に対して一方的なレッテルを決めつけないで、理解しようと歩みることはできると思うんです。そこは七恵が乗り越えていくところなのかな。レイ自身は家族だったり、恋人だったり、全てを捨てて、七恵のことを理解できると証明しようとする。“捨てる”というやり方で、レイ自身も見えてきたものがあったと思う。
――レイという女性をどう感じましたか?
不器用な人で、愛するということがうまくできなかった人だと思います。母親に同性愛者であることを否定され、そこで苦しんだ。七恵に対しては、当初、彼女を所有しようとしますよね。七恵にお金を貸すのは、彼女をその間、所有したい、自分のものにしたいという思いがあったはず。でも、最終的には手放すことで、もっと違う愛の形に気づくというか。それは演じている間、ふたりの寂しさの中で自然と導かれた感情でした。旅を重ねる中で、やっとふたりが信頼しあえるところまでいって、世界に私たちふたりしかいない状態で、母性という言葉を使うのが適切かはわからないけど、大きな愛に気付く。『彼女』はそういう物語だと思います。
――『彼女』は七恵役のさとうほなみさんがいないと成立しない作品だったと思いますが、ミュージシャンでもある彼女から受けた印象は?
ミュージシャンっていう顔は、全く見えてこなかったですね。「そういえば、この人、ミュージシャンだった」っていうのは頭の片隅にしかなくて、撮影中は本当に七恵そのもの。ほなみちゃん自身の話をすると、すごくパワフルな人でした。七恵って、ずっと虐げられてきて、ボロボロなんだけど、そこで紙一重で生きようとする意志もあって……。そのパワフルさは、ほなみちゃんにしか出せないものだったと思う。とてもエモーショナルな感情のまま、ふたを閉めず、全力でこっちに来るんですよ。それって私にしか見せていない表情ですから、受けて苦しくもあったけど、同時に「これが生きている人間なんだ」と、私しか知らない彼女を見ている感情にもなった。一言で表すと、いろんな意味で圧倒されました。
---fadeinpager---

七恵の生家に立ち寄ったふたり。穏やかなシーンにも、ふたりが背負った罪の気配が見え隠れする。
――廣木隆一監督は、どういう演出家でしたか?
監督は、物語の時系列に沿って作品を撮影していったんです。そのことに助けられました。台本を読んでいても、これどうなんだろうとわからないことが多くて。実際に現場に入って、本当に体験する、という感じだった。全部が大事なシーンで、一場面も欠かせなかった。本当に体験して、演じられたということは、本当にその瞬間を生きるということだった。だからもう、あんまり思い出したくない。だって、ずっと苦しかったから。
――このドラマに共感できるところは、レイの持っている七恵への愛情が、精神的な部分もあるけど、性愛の対象でもあるということをきちんと描いているところです。その分、水原さんも、佐藤さんも肉体の表現を繊細にされていて、そこに感情移入しました。肉体的な表現は大変でしたか?
そうですね。でも、悩むというより、やるというか。特に最後のふたりのラブシーンは、本当に最後の撮影日で、いちばん大切な瞬間だから、そんなことは気にしてられないくらい、無我夢中でやっていました。すごく繊細なシーンでもあるので、スタッフのみなさんにすごく気を配っていただきました。
――『アンモナイトの目覚め』でのケイト・ウィンスレットとシアーシャ・ローナンのラブシーンでは、ケイトがフランシス・リー監督に「私たちに任せて」と提案して、ふたりで作ったとインタビューで話をしていますよね。
やっぱり、そっちのほうがいいというか。もちろん、監督の演出は大前提としてあるけれど、演じているのは私たちだから。どういう環境で演じられるのかは配慮されるべきだと思います。違和感のない状態で演じることが、結果、作品の良さに反映されると思う。何かしら嫌だなと思っている状況での撮影が続くと、どうしてもバリアが出来ますし、やらなくてはならないという演技はすごく苦しいこと。それが原因でいいシーンじゃなくなったりしたら、それほど悲しいことはない。廣木監督も含め、Netflixチームともフランクに話せる環境でした。
加えて、初めての試みでしたけど、インティマシー・コーディネーターを現場に入れていただいたんです。(※編集部注/「インティマシー・コーディネーター」とは、ヌードやラブシーンなど、身体の接触や露出などセンシティブな場面で、演じる側と演出する側の意向を確認して、調整・ケアする役目の人)。その人がいることで、スタッフとキャストの間で暗黙の了解で済まされていたことが、きちんとどうするか、どうしたいかコミットしていって、同じ方向を向くきっかけになりました、そういうのがよかったなと思います。
---fadeinpager---

罪を犯したふたりの逃避行が、行きつく先とは。
――『彼女』は女同士の恋愛というより、女性同士の連帯、共感を描いたシスターフッド映画だと感じたのですが、水原さんが影響を受けたシスターフッドを扱った映画はありますか?
そんなことを言ったら、全部(笑)。映画だけでなく、日常で、いろんな女性に支えられてきています。会社は意図せず、全員女性スタッフなんですけど、同じ意識を持った強い女性たちがまとまってくれている。私の中華圏のエージェント会社の社長は女性なんですけど、それはそれは強い女性で、女性であろうと意見を言っていいんだと気付かせてくれた存在。この環境は、すごく恵まれていると思います。
――水原さんが臆することなく意見を言えるようになったきっかけは?
強くないとやってられなかった。若い頃から仕事を始めたし、「私、大丈夫だから」と強く言わないと怖くて進めない時も。いま振り返ると、そこまで強くしなくてもよかったな、と思うこともあった。周りにいる女性たちと、コミュニケーションをとったり、いろんな関係もあって解放されたり、癒されたり。仕事をし、表現する上で、何もリミットをかける必要はないと感じているから、実行しています。そういう認識がもっと社会で当たり前になるべきだし。いま、いい意味で社会が変動してる時なので、「GO!GO!」って感じですね(笑)、平等ってことを目指したいです。
――ここ数年、LGBTへの理解が進み、演じる側も、見る側でも当事者たちの声が社会の中で大きく聞こえるようになっています。その中で議論になるのが、当事者が演じたものを見たいという意見です。一方、『キッズ・オールライト』のアネット・ベニングのように、ストレートであっても、レズビアンの役を素晴らしい演技で表現できることを否定はしたくないという気持ちもあります。水原さんはどういう考えをお持ちですか?
私自身は、性自認は女性。自分のことをヘテロやレズビアンとは思っていませんが、自分の素敵だなと思う人や、好きになった人は、どんなジェンダーであろうと、その時は惹かれるんですよ。登場人物と同じ当事者性の俳優が実際に演じられる、そのムーブメントはすごくいいと思う。LGBTの人にチャンスが少ないなら、巡ってくるべきだと思う。でも、だからといって「このジェンダーだからこの役は演じちゃダメ」というのは違うと思う。役者としては、大切なのはその人物のことを深く理解して、演じることだから。そこにカテゴライズはいらない。私はそう、思います。

1990 年生まれ、テキサス州ダラス出身。『ノルウェイの森』(2010年)にて女優デビュー。映画、TV、CM、モデルと幅広く活躍。代表作に『ヘルタースケルター』(12年) 、『進撃の巨人 ATTACK ON TITAN 』(15年)、『奥田民生になりたいボーイと出会う男すべて狂わせるガール』(17年)、『あのこは貴族』(20年)など。語学力とインスタグラムで570万人超えのフォロワーを持つ影響力が認められ、ディオール ビューティやコーチなどハイブランドのアンバサダーも務める。
●監督/廣木隆一
●出演/水原希子 さとうほなみ 真木よう子 鈴木 杏 田中哲司 ほか
●原作/中村珍『羣青』(小学館IKKIコミックス)
●2021年、日本映画
●142分
●Netflixにて全世界独占配信中 www.netflix.com/彼女
エドスロトーム オフィス
tel:03-6427-5901
photo:YASUYUKI EMORI, interview et texte: YUKA KIMBARA, stylisme:MASAKO OGURA, coiffure et maquillage: RIE SHIRAISHI