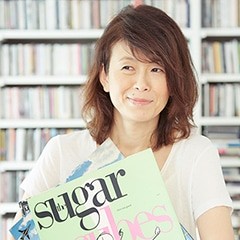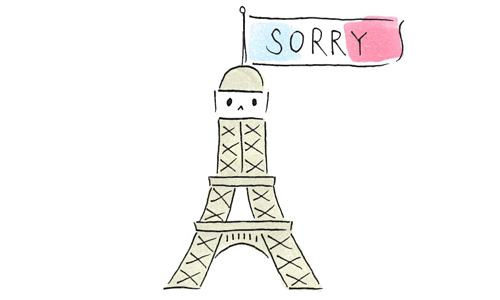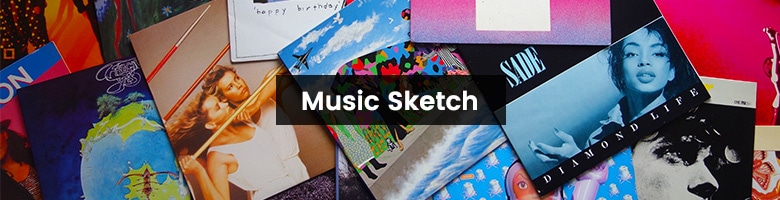
オペラ『ルサルカ』@新国立劇場 ②
Music Sketch
現在公演中の、オペラ『ルサルカ』の話を続けていきます。
多感な少女が寝室で人形と遊びながら空想の世界に浸っていると、不思議な夢の中に入り込んでしまう・・・・・・。ファンタジーの世界を象徴するように、ステージには自由に行き来できる大小の扉が設置され、任意に形を変えていく"水"は"生命の象徴"として映像と合わせて描かれます。また、大地を意味する木々や、魔女が棲む月など、まさに別世界に誘引するようなセットも次々と登場。音楽での表現をサポートするように使われている照明や美術も、最新技術とともに丁寧に駆使されていて、それらが構築する神秘的空間に魅了されるばかりです。
 魔法使いの力を借りて、人魚から人間へと変身していくルサルカ。スモーク液のロスコと舞台装置を使ったトリックも見応えがあります。
魔法使いの力を借りて、人魚から人間へと変身していくルサルカ。スモーク液のロスコと舞台装置を使ったトリックも見応えがあります。
人間に恋をした水の精の悲恋のストーリーは、アンデルセンの『人魚姫』や、フーケの『ウンディーネ』を原作にしたジャン・ジロドゥの戯曲『オンディーヌ』が有名です。ポール・カランは、アントーニン・ドヴォルザークが作曲した妖精オペラ『ルサルカ』が、フロイトが『夢判断』を出版した1900年の作品であることに着目し、また当時、イプセンやチェーホフが女性の社会進出をテーマに小説を書いていたからと、このオペラで少女が大人へと成長する心理的かつ肉体的な旅を描きたかったそう。「これはおとぎ話であり、現代的な作品でもあり、現代社会に関する話でもあります。愛、何かに取り憑かれるということ、セックス、コミュニケーションが題材になっています」と、11月22日に行なわれたトークショウでも話していました。
 ルサルカ役のオルガ・グリャコヴァ。すばらしい歌唱力、そして演技力にも心打たれました。
ルサルカ役のオルガ・グリャコヴァ。すばらしい歌唱力、そして演技力にも心打たれました。
「とにかく現代的な設定にしたかった」という、ポール・カラン。ルサルカが人魚から人間になる場面では、魔女が"人間になる引き換えとして、口がきけなくなることと、(思春期の少女が大人の女性になる証として)血が欲しい"と、ルサルカに話し、「人魚の尾を切るのではなく寝間着であるガウンを切るといった設定で、大人になることへの恐怖や魔法のような瞬間を表現したかった」と、説明します。
 ルサルカが王子との婚礼に臨む場面。しかし移り気な王子に裏切られ、急展開に。スケールの大きな舞台にふさわしいオーケストラ演奏が劇場に鳴り響きます。
ルサルカが王子との婚礼に臨む場面。しかし移り気な王子に裏切られ、急展開に。スケールの大きな舞台にふさわしいオーケストラ演奏が劇場に鳴り響きます。
また、「現代の若者の姿に被るよう、彼女は早くから大人になりたがっていて、自分の意思から旅に出るという展開にした」と、いいます。オペラというと、歌手が次々と声を張り上げて熱唱するというイメージがあると思いますが、ルサルカが大人になるまでの前半は歌うことなく演技に徹している、というのも、ストーリー性を重視したポール・カランの考えだったようです。
もう少し続けます。
オペラ『ルサルカ』の情報はこちら→http://www.atre.jp/11rusalka/
Photo:新国立劇場オペラ『ルサルカ』(2011年) 撮影:三枝近志
*To be continued