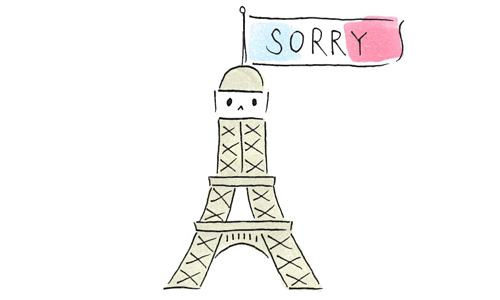『燃ゆる女の肖像』主演、アデル・エネルの素顔に迫る。
インタビュー
第72回カンヌ国際映画祭で、脚本賞受賞をはじめ映画賞を席巻したフランスの気鋭セリーヌ・シアマが脚本・監督を務める『燃ゆる女の肖像』。18世紀のブルターニュを舞台に、画家と貴族の令嬢の出会いと情熱を描いた美しく熱いドラマだ。望まぬ結婚を前に葛藤する貴族の令嬢エロイーズを演じた、フランス映画界を代表する女優となったアデル・エネルにオンラインインタビュー。

貴族の令嬢エロイーズを演じたアデル・エネル。
これは18世紀を舞台にした、今日的な物語。
――カンヌで脚本賞を受賞していますが、実際にとても素晴らしい脚本ですね。この脚本を最初に読んだ時、どのような感想を持ちましたか?
セリーヌがこの作品の構想を練っているという話は、かなり前から聞いていたの。でも、いろいろな事情でなかなか着手できなかったり、取りかかってもまた棚上げになったり。なので、出来上がった脚本を受け取った時、内容についてはすでにかなり知っていました。2日くらいかけて読み、フィクションならではの描き方がされていて、政治的な問題提起も的確にされていると思ったわ。セリフなど役者としてもいろんな幅をもって演じられる、とても素晴らしい脚本よ。
――セリーヌ・シアマ監督とは、あなたが女優として脚光を浴びたシアマ監督のデビュー作『水の中のつぼみ』(2007年)以来、15年近くの付き合いだと思います。本作でさらにその評価が高まりましたが、あなたから見て、どのような点がほかの監督と違うのでしょうか?
彼女の強みは、“衝突”というモチーフを使うことなく、人間関係の複雑さを描くことができる点。線の使い方、色の使い方に明確なアイデアを持っているし、何よりも彼女はフィクションを愛している。語らなければならないテーマを持ちつつ、ステレオタイプな語り口を崩し、問題提起をしつつもそれを乗り越えるツールのようなものを与えてくれる。そういうことができるという意味で素晴らしい監督だと思うわ。

撮影中のオフショット。左から、画家マリアンヌを演じたノエミ・メルラン、アデル・エネル、セリーヌ・シアマ監督。photo : CLAIRE MATHON
――18世紀が舞台ですが、今日的テーマが内包されていると思います。この映画がいま作られた意味をどう感じていますか。
そう、この映画は18世紀が舞台でありながら、とても現代的な映画だと思うわ。ふたりの女性の立場は平等で、ともに手探りで独自の言語をつくりあげていく。フィクションならではのやり方で、とても現代的なテーマを語っているの。また、多くの映画は男性の視点で描かれることが当たり前になっているけれど、そういった慣例に関しても問題提起している。「あなたは私を見ているけれど、私もあなたを見ているのよ」というセリフがあるのだけれど、これは男性に対して、女性も男性を見ているのだ、という点を突いていて、まさに現代の世界にも通じると思う。

画家のマリアンヌ(右)はブルターニュの貴婦人から、娘エロイーズ(左)の見合いのための肖像画を依頼され、身分を隠してエロイーズに近づく。
---fadeinpager---
冒険心がありながら、制約を受けて生きてきた女性。
――マリアンヌとエロイーズは、対照的な女性として描かれますね。マリアンヌは、冒頭でキャンバスが船から落ちるとそれを引き上げるために海に飛び込む。あなたが演じたエロイーズは、島に住みながら海に入ったことがない。この自由な生き方と保守的な生き方の対比をどう解釈したのでしょうか。
マリアンヌとエロイーズは確かに対照的に描かれているわ。エロイーズは、結婚だけに限らず、さまざまな制約の中で生きてきた人。でも、物語が進むにつれて、実は好奇心が旺盛で、冒険心もある人物というのがわかってくる。彼女は生命力が乏しい女性と思われがちだけれど、実はこれまではしがらみからそういう行動をとっていたのだということがわかってくる。そうしたキャラクターの変化を演じるのはとても興味深かったわ。

ブルターニュの孤島で一緒に過ごすうちに、対照的なふたりは次第に惹かれ合っていく。
――この物語は、マリアンヌとエロイーズのラブストーリーであるいっぽう、使用人のソフィを含めた3人の女性を通じて、女性の生きづらさについて描いています。特にマリアンヌは、父親の名前でしか作品を発表できないし、芸術のために結婚しないといいます。ジェンダーギャップについての運動が進んでいるフランスでも、こうした“壁”は、いまも存在すると思いますか?
女性アーティストの生きづらさは、今日でも大いにあると思うわ。男女の不平等は製作現場でもいまだにあるし、男女の役割分担も明確に残っている。たとえば、女性の作り手が存在感を示すためには、男性が作ったものより、はるかに優れたクオリティのものを作らなければならない、とか。そういった意味で、いまでも不平等は存在する。なぜなら、問題を解決しないことで既得権益を守りたいと思っている人がいるからよ。残念ながら、フランスでもそれが現実。

使用人のソフィ(左)とエロイーズ(中央)、マリアンヌ(右)。映画そのものも油彩画のように美しく、国内外の映画人の心を捉えた。
――観る者の心を揺さぶる圧倒的なラストシーンでしたが、どのような思いで演じましたか?
最後のシーンはシアマ監督が脚本で最初に書いた、思い入れの強いシーンなの。準備を整えて臨んではいるけれど、その時に湧き上がってきた生の感情も捉えたかった。狭い場所でのクレーンを使っての撮影で、テクニカルな面でも本当に難しく、私もものすごく集中力を要したわ。

結ばれるはずのないふたりの恋の行方は……? ぜひスクリーンで見届けたい。
1989年フランス・パリ出身。2002年『クロエの棲む夢』のヒロイン役でデビュー。07年、セリーヌ・シアマ監督の長編デビュー作『水の中のつぼみ』でセザール賞有望若手女優賞にノミネートされる。さらに『メゾン ある娼館の記憶』(11年)でも同賞ノミネート、『スザンヌ』(13年)でセザール賞助演女優賞を受賞。続く『ミリタリーな彼女』(14年)でもセザール賞主演女優賞を受賞し、名実ともにフランス映画界を代表する女優のひとりとなる。ほかの主な出演作に『午後8時の訪問者』(16年)、『ブルーム・オブ・イエスタディ』(16年)などがある。
●監督・脚本/セリーヌ・シアマ
●出演/アデル・エネル、ノエミ・メルランほか
●2019年、フランス映画
●配給/ギャガ
●12月4日より、TOHOシネマズシャンテ、Bunkamuraル・シネマほか全国にて公開
©Lilies Films
https://gaga.ne.jp/portrait
【関連記事】
『燃ゆる女の肖像』が脚本賞に! 立田敦子のカンヌ映画祭レポート2019
セリーヌ・シアマも脚本に参加したアニメーション映画『ぼくの名前はズッキーニ』
interview et texte : ATSUKO TATSUTA