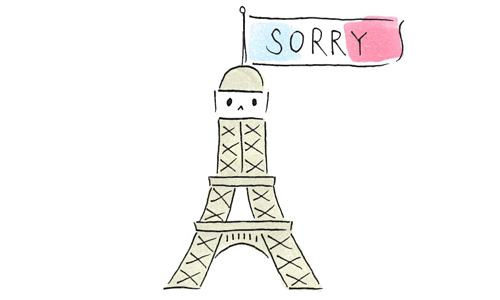パリ・オペラ座バレエ団の『オネーギン』、観に行く前に。
パリとバレエとオペラ座と。
『ジゼル』の全幕公演で幕を開けたパリ・オペラ座バレエ団来日ツアー。3月5日からの二つ目の演目は、『オネーギン』全3幕である。プーシキンによる原作は映画化、オペラ化もされている。バレエ作品としては『ジゼル』に比べるとなじみが薄いのではないだろうか。子どもも楽しめる『ジゼル』と異なり、『オネーギン』はドラマティックバレエの傑作と謳われるだけあり、なかなか複雑な心理劇でもある。バレエ作品の多くが死別の悲劇であるが、これは主人公の意思により結ばれないふたりの物語なのだ。それゆえにダンサーたちの踊りだけでなく、演技者としての仕事も見どころとなる作品である。
これはジョン・クランコがシュツットガルト・バレエ団のために1965年に創作した作品で、2018年秋に彼らが来日ツアーを行った際に踊られている。このご本家以外のバレエ団が日本で『オネーギン』を踊るのは、今回のパリ・オペラ座バレエ団が初めてなのだそうだ。そしてパリ・オペラ座バレエ団が日本で『オネーギン』を踊るのも初めて。この貴重な機会に、見逃してしまうのは惜しいだろう。

作品に美しさをプラスするチャイコフスキーの音楽、『椿姫』と同様にユルゲン・ローゼによる舞台装置とコスチューム。photo:Julien Benhamou/ Opéra national de Paris
まずは公演主催者NBSによる物語紹介から。舞台は1820年代のロシアである。
第1幕、第2幕「田舎の地主の娘タチヤーナは、帝都育ちの洗練された青年オネーギンに憧れ、恋文をしたためる。いっぽう若くして人生に飽い たオネーギンは一途なタチヤーナの愛を疎んじ、友人レンスキーをつまらぬ諍いから決闘で殺して失意のうちに去る」
第3幕「数年後、将軍の妻となったタチヤーナとオネーギンが再会。オネーギンはタチヤーナの気高い美しさに心を打たれ、熱烈に求愛。 しかし胸に恋心を残しながらも人妻としての矜持を失わないタチヤーナは、これを拒絶する 」
主人公のタチヤーナとオネーギンに加えて、タチヤーナの妹オリガとその許婚レンスキーが物語の進行に重要な役割を果たす。バレエを超えた演劇的作品の『オネーギン』。この4役を踊るダンサーたちは、テクニック面のみならず役者としての仕事を要求される。配役されたダンサーたちはほかの作品以上に芸術面の仕事を見せられるよい機会なので、各人が自分なりの役づくりに励むのだ。芸術監督オレリー・デュポンも現役時代にニコラ・ル・リッシュと踊っていて、第3幕、最後のパ・ド・ドゥは彼女のお気に入りだという。
「これはまるで男優と女優が踊っているようで……ダンス以上のものでした。タチヤーナ役もオネーギン役もキャリアの早い時期ではなく、ある程度成熟してから得るのがふさわしい役ですね。テクニックの理解力があり、芸術面の仕事もでき、そしてパートナーとの関係づくりも大切で。ダンサー自身の成熟が要求される役です」
こう語る彼女が選んだ2組による『オネーギン』が東京で踊られる。同じ作品でも、ダンサーたちの役の解釈によって異なる舞台となるので、2配役とも見てみるとおもしろいだろう。

第3幕のパ・ド・ドゥ。2018年、パリ・オペラ座での公演より。photo:Michel Lidvac
---fadeinpager---
オネーギンとタチヤーナ。
来日公演でユーゴ・マルシャンを相手にタチヤーナ役を踊るドロテ・ジルベール。初役はいまから10年前で、パリ・オペラ座で公演があるごとに新しいパートナーと組んでいる。「最初の時は若かったから、タチヤーナ役を準備するのはなかなか大変な仕事だったわ。特に第1幕。恋に臆病なタチヤーナなので自分の気持ちとだけ向き合っていて、たったひとりなの。彼女はもちろん、そこにいる人々みんなをオネーギンは無視していて、ブロックされた彼女の思いは行き場がないのよ。第3幕ではオネーギンとの間にピンポンのようにやりとりがあるので演じるのが楽になるのだけれど……」
このドロテの言葉を裏付けるように、ユーゴが第1幕のオネーギンについてこう語る。
「オネーギンはタチヤーナには感じるものがなく、まったく興味を示しません。とても陰気な人物です。ノスタルジックでロマンティック……手の届かない何かを追求していて、それによって盲目になってしまっています。悪意のある人ではありませんが、自分の周囲で起きていることを理解したり、ほかの人に注意を払うといった能力を失ってしまっていて……。自分自身にあまりにも興味を持ちすぎているんですね。これが僕の思う第1幕のオネーギンです」
そんなオネーギンになぜタチヤーナは恋をしてしまうのだろう。
「彼女はブルジョワ家庭に生まれ育ったとはいえ、田舎のことです。そのいっぽうオネーギンは都会人で、彼の存在感や少し距離を感じさせる面に惹かれたんでしょうね。もっとも恋に落ちる時って、なぜ、とは考えないものでしょ。彼女はまだ愛するということを知らずにいて、オネーギンが庭に来た時に、自分の中に生まれたよくわからない感情に埋もれてしまうのね。これが初めての恋。彼に手紙をしたためる、というのはいかにも若い娘の行為で子どもっぽい。祝宴の場でも彼女は素朴で自分の気持に素直で、ピュア。小説好きの彼女は自分の人生も、小説のように進むのだと信じているのでしょうね」
とドロテが説明する。その幼さの残る夢見る少女が、第2幕の最後にオネーギンとの決闘でレンスキーが命を失ったところで、大きな変貌を遂げるのだ。その場を去ろうとするオネーギンに、後悔の念は見えない。決闘は彼にとって初めてのことではなく、今回もいつもどおり彼は命を落とすことなく……。その彼にぶつけるタチヤーナの視線はとても強い。ドロテが続ける。

決闘の場に姿を現すオネーギン。photo:Julien Benhamou/ Opéra national de Paris
「決闘によるレンスキーの死で、愛情、愛する人を弄んではいけないのだと知り、彼女は精神的に成長します。そしてオネーギンと視線を交わす勇気を持つのね。家族思いの彼女はレンスキーの命を奪い、そして妹をこんな状況に陥れたオネーギンに過ちをわからせたい、罪悪感を感じさせたいの。彼に対する思いはあっても、彼女はここで彼のダークな一面を知るのよ」
第2幕最後の一瞬。その視線を受けるオネーギン役のマチュー・ガニオは、ここで若い娘ではなくひとりの女性をタチヤーナに見いだすという。
「それまで彼女のことを小娘として上から目線で見ていたのが、ここで突然彼女が自分と対等になります。ひとりの女性である彼女の視線は彼にこう言っています。“あなたの悪意、あなたの過ち。ご覧なさい、あなたのしでかした愚かなことを”と。彼はその場から逃げ出し、そして長い旅に出るのです。でもどんな地の果てに行こうと彼は彼女を思い出し、決闘を思い出し、後悔の念が付いて回る……」

ユーゴ・マルシャン。第3幕、回想のシーンより。photo:Julien Benhamou/ Opéra national de Paris
そんな日々を過ごし、決闘から10年後に彼は帝都に戻るのである。そこから第3幕がスタートする。ユーゴ・マルシャンはそのオネーギンについて
「第2幕と第3幕の間で彼は年をとります。人生に傷つき、それゆえに一種の謙虚さのようなものを知る人間となっています。若き日々の自分を悔やみ、その後悔の中には本当の愛情物語を経験していないことも含まれます。長くひとりでいたこともあり、タチヤーナが彼に捧げたであろう愛が彼には惜しまれる……でも、彼女を得ることはできないのです」と。
再会し、求愛するオネーギンを受け入れたくも、拒むタチヤーナ。激しく揺れ、引き裂かれるような心が描かれているのが、第3幕の悲痛なパ・ド・ドゥである。ドロテも作品中、このパ・ド・ドゥがいちばんのお気に入りだという。
「タチヤーナは大人の成熟した女性となっていて、情熱的な愛というのではないにしても、グレミンは良い夫だし、彼女は不幸ではないの。自分の人生があり、自分の場所が確立できている。オネーギンが視界から消えているときは彼を忘れることができていたのだけど、彼を目の前にするや思い出が蘇り……恐ろしいことね。彼女の頭の中はすっかり混乱し、求愛する彼の情熱に負けたくなってしまうのよ。でも彼女が受けた教育、倫理観が引き止めるのね。彼への情熱と自分が取るべき態度の間で、彼女は引き裂かれる。“なぜいまになって。10年前に言ってくれていたら結婚していなかったのに”って、彼女は思うの。振り付けにも明らかでしょ、心が引き裂かれているのが。怒りがあり、愛があり、それに理性を保とうとする心。第3幕のパ・ド・ドゥにはそうした思いが込められているのよ」

第3幕より。ジゼルに続き女優ぶりを発揮するドロテ・ジルベール。photo:Julien Benhamou/ Opéra national de Paris
ユーゴはオネーギンをひねくれ者だと形容する。いまはレンスキー役だけど、次はオネーギンに挑戦したいと意欲的なジェルマン・ルーヴェが“彼はほとんどスキゾフレニアだ”と冗談めかして言いたくなるほど、とにかく複雑な人物である。マチュー・ガニオは2011年に初役でオネーギン役に取り組んだ時、この人物を理解するのに苦労をしたそうだ。
「決して感じのよいというタイプではない人間ですね。複雑な人です。他人を苦しめることができる人物を受け入れ、演じることが僕にはとても難しかった」
作品の再演は、役柄を掘り下げることができるよいチャンスという彼。オペラ・ガルニエでオリガ役をレオノール・ボラックが初めて踊った2018年に、リュドミラ・パリエロとマチュー・ガニオが主役の『オネーギン』を見る機会があったそうだ。
「私、彼のオネーギン役の解釈がとっても気に入りました。とりわけ悪意の塩梅が素晴らしい。もし完全に不愉快で憎むべき人間にしてしまったら、タチヤーナが心惹かれることはないでしょ。 彼のもともとの美貌に、私が思うパーフェクトな分量の冷たさが加えられていました。彼は私生活ではとても優しい人。それがあの演技と衣装で、とっても冷たく見え、しかも、それが似合って見えたことに驚きました。完全なる変身。冷たい美しさで、魅力があって……。東京では彼と一緒の舞台なので、とても楽しみです」
マチュー・ガニオは2018年に、シュツットガルト・バレエ団が日本で公演を行った際に、ゲストとして招かれているという本家のお墨付きである。彼のパートナーはタチヤーナを踊ってエトワールに任命されたアマンディーヌ・アルビッソン。このふたりが初めて日本で組み、熟成の味わいを残す舞台を見せることだろう。もうひと組のドロテとユーゴは、お互いに息が合うことを認める関係。こちらもまた強烈な印象を残す公演を期待できそうだ。

マチュー・ガニオ。第1幕より。photo Michel Lidvac
---fadeinpager---
オリガとレンスキー。
第一キャストのオリガとレンスキーは、前出のレオノールとジェルマン・ルーヴェ。第二キャストはナイス・デュボスク(コリフェ)とポール・マルク(プルミエ・ダンスール)だ。2018年のオペラ座での『オネーギン』にて、初役で踊った若いカップル2組である。ポールとともに今回が初来日というナイスは、オレリー・デュポン芸術監督に抜擢され、バレエ団に正式入団した数カ月後の2018年2月に妹オリガ役でパリ・オペラ座の舞台に立つことになった期待の新星である。もともと踊る人物像に入り込む仕事が好き、という彼女であるが、この早々の大役にはいささか面食らってしまったと言う。

レンスキーを踊るジェルマン・ルーヴェ。photo:Julien Benhamou/ Opéra national de Paris
「すぐに原作を読みました。そしていろいろな配役のビデオを見て視覚面の仕事をし、相手役のポール・マルクとふたりとも初役だったので、とにかく稽古につぐ稽古で役を準備。彼とは友達ということもあるけれど、おかげで本番はいつになくストレスを感じることなく舞台を務められました。オリガは物語の展開を担う役です。彼女って世間知らず。あまり物事を深く考えるタイプではなく、人からちやほやされるのが好きで、男性の目を引きたいと思っています。その気持ちは、姉タチヤーナが恋するオネーギンに対してもあって、それが悲劇の引き金となってしまうのですね。オリガはタチヤーナに姉妹愛を強く感じていても、文学少女の姉は自分の想いにふけっていて、ロマンティックであまり楽しい女性ではないと思っています。生真面目すぎ。だからオリガはオネーギンとカードやダンスを楽しんで、彼女に見せびらかすようにします。それに初恋の相手のレンスキーをちょっと嫉妬させてみよう、という気持ちもある。オネーギンに対して、特に興味を持っていたわけじゃない、って私は思っています。それに妹って、どこの家庭でもそうだと思うのだけど、自分は透明な存在じゃないということをアピールする必要を感じている。自信のなさもあるのかもしれないけれど……。大事な存在のレンスキーなのだけど、初恋相手で理想化していることもあって彼女は彼の気持ちが読めていません。嫉妬心を掻き立てる試みは初めてのことなので、それが引き起こすことの大きさがわかっていない。まさか決闘を引き起こす結果となるなんて、想像すらしていません。火を弄び、燃やしてしまった……ということですね。レンスキーを失い、彼女の人生はここで暗転します」

2018年、入団間もなくオリガ役に大抜擢されたナイス・デュボスク。photo:Julien Benhamou/ Opéra national de Paris
彼女のパートナーでレンスキー役を踊るポール・マルクは、『オネーギン』がオペラ座にレパートリー入りした時の公演をビデオで見る機会があり、第1幕で踊られるオリガとレンスキーのパ・ド・ドゥにすっかり魅了されてしまったそうだ。
「振り付けも、衣装も、音楽も何もかもが素晴らしいパ・ド・ドゥです。レンスキー役に配役され、すごくうれしかった。このパ・ド・ドゥを稽古する喜び、舞台で踊る喜び……。この素晴らしい体験をまた日本で味わえるのは幸運ですね。この人物を準備するにあたっては、原作を読んでどんな若者なのか研究しました。彼はオリガを一途に愛しています。だから第2幕の祝宴の場でオネーギンと彼女の間で起きていることが理解できない。彼には怒りがあり、絶望があり、悲しみがあり恐れもあって、と感情の動きがいろいろあるんです。こうした役を踊るのはおもしろいですね。テクニックをマスターしておけば、振り付けがよくできているので、これに音楽を利用すると表現するのがとても楽なんです」

誰の目にも理想のカップルであるオリガ(ナイス・デュボスク)とレンスキー(ポール・マルク)。photo:Julien Benhamou/ Opéra national de Paris
タチヤーナの誕生パーティで、オネーギンはレンスキーの愛するオリガをトランプゲームに誘い、ダンスに誘って彼女の歓心を買うような態度をとる。そんなオネーギンにレンスキーは手袋を投げ、決闘を挑むのである。ナイスも上で語っているように、彼の心の動きについてオリガは気付かない。オリガとレンスキーの関係について、レオノールの説明を聞いてみよう。
「幼馴染みで、とっても気が合うふたりなんです。だからふたりが結婚するのはオリガにはごく当然のことに思えています。誰の目にもパーフェクトな、愛らしいカップル。レンスキーと違って、オネーギンというのはオリガから見てとてもミステリアスで手の届きそうもない存在です。彼は彼女を笑わせてくれ、それまでに味わったことのない興奮を彼に掻き立てられます。レンスキーが決闘をオネーギンに申し込むほどの怒りに至る心の中は彼女には見えていなかった。彼が少し気分を損ねている、というのはわかっていたにしても“ちょっと大げさね”というように思った程度。小さい時から彼がこうしてイラつくのを何度も見ているので、いつものことのように感じていたから、決闘には驚かされてしまうのです」

第2幕、タチヤーナの誕生祝いのパーティ。喜びも束の間……。photo:Julien Benhamou/ Opéra national de Paris
観客も驚くのである。レンスキー役を踊るポール・マルクの話を聞いてみよう。
「第2幕の宴の場に集まっていた人々は、決闘とはいささか度を越している、とレンスキーの行動に驚かされますね。原作を読んだとき、彼がオネーギンに決闘を申し込んだことは正当なことに読めました。それは彼が若く、衝動的でカッとしやすい人間ということをプーシキンがそこに至るまでにわからせてくれたから。だから、僕は舞台で彼のこうした面を見せ、彼の心の中で起きていることの流れから決闘を申し込むのは当然のことと観客にわからせるように務めます」
決闘の前、命を落とすかもしれないレンスキーの美しいスローなソロがある。その静けさを破って決闘を思い止まらせようとタチヤーナとオリガが駆けつけ、物語はテンポを上げて悲劇へと向かってゆく。レンスキー役のダンサーはもちろん、オリガ役のダンサーにとっても実にドラマティックなシーンである。

第2幕、レンスキーのソロを踊るポール・マルク。photo:Julien Benhamou/ Opéra national de Paris
「レンスキーを決闘へと駆り立てた軽率な行動を悔やみ、悲しみ、怒りなどさまざまな思いを抱えてオリガは彼にすがりつきます。強い感動があり、演じていて涙があふれそうになった思い出があります」
とナイスが2018年のオペラ座での舞台を振り返る。オネーギンとタチヤーナだけでなく、第1幕、第2幕の展開に大切な役割を果たすレンスキーとオリガのカップル。これを踊るダンサーたちも、人物像づくりに力を入れずにはいられない演劇バレエなのである。
---fadeinpager---
『オネーギン』トリビア。
第1幕で庭のテーブルに腰をかけ、自分の前の鏡をのぞきこむオリガ。後方から忍び足でやってきたレンスキーを鏡の中に見つけると、彼女は喜びに顔を輝かせる。そのいっぽう、姉のタチヤーナは鏡の中にオネーギンが映るや、驚くような表情を見せる。それぞれの女性の反応の違いは、“若い女性が鏡をのぞきこんだ時に自分の背後に見えた男性と結婚することになる”というロシアの言い伝えを知っていると、わ分かりやすいだろう。タチヤーナが背後に見たオネーギンは、彼女にとって未知の男性。ふたりの視線が初めて交差するのが、この鏡の中において。これは何かの前兆では?と、小説好きで、言い伝えを知る彼女は思ってしまうのだ。

鏡のシーンより、オリガ(レオノール・ボラック)とレンスキー(ジェルマン・ルーヴェ)。photo:Julien Benhamou/ Opéra national de Paris
第2幕、宴の会場でレンスキーが白い手袋をオネーギンに投げ、決闘を挑む。オネーギンはこれをなぜ受けてしまうのだろう、と思うだろうが、どんな原因からであろうと、決闘を挑まれた人間は、受けざるを得ないのである。さもなければ臆病者とみなされてしまう。オネーギンにとって、この世で最も大切なのは名誉。それはステージにかかる紗幕に紋章のように謳われていることだ。たとえレンスキーが友達でも、自分の名誉を保つためには断れなかったのである。
パリ・オペラ座バレエ団に『オネーギン』がレパートリー入りしたのは、2009年のマニュエル・ルグリのアデュー公演の際だった。5月15日の彼のアデュー公演前、4月16日にレンスキー役のマチアス・エイマンとタチヤーナ役のイザベル・シアラヴォラがエトワールに任命された。そのイザベルは2014年2月28日に『オネーギン』の舞台で引退するのだが、その数日後の3月5日に初役でタチヤーナを踊ったアマンディーヌ・アルビッソンがエトワールに任命されるのだ。それから6年後の3月5日、アマンディーヌはタチヤーナとして、東京でマチュー・ガニオと踊る。

アマンディーヌ・アルビッソン。photo:Julien Benhamou/ Opéra national de Paris
30周年を迎える「フィガロジャポン」読者のために、バックステージツアー付きスペシャルチケットを限定で用意しました。
このチケットを購入いただいた方は、3月7日(土)夜公演の『オネーギン』鑑賞に加え、通常は公開されることのない舞台裏をご案内&エトワールのジェルマン・ルーヴェを囲んでの写真撮影も予定しています!
【関連記事】
そして、ジェルマン・ルーヴェがエトワールに!
madameFIGARO.jpコントリビューティング・エディター
東京の出版社で女性誌の編集に携わった後、1990年に渡仏。フリーエディターとして活動した後、「フィガロジャポン」パリ支局長を務める。主な著書は『とっておきパリ左岸ガイド』(玉村豊男氏と共著/中央公論社刊)、『パリ・オペラ座バレエ物語』(CCCメディアハウス刊)。