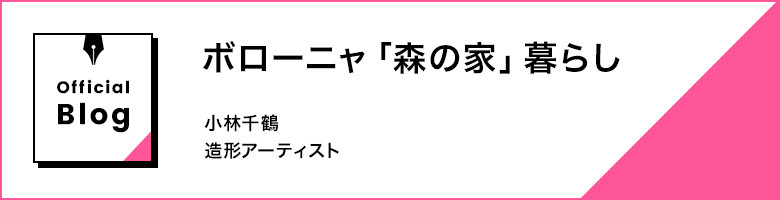
そして1月、新しい一年のはじまりはじまり。
年が明けてはや1週間と少し、子どもたちは17日間の冬休みを終えて学校に戻り、やっと日常が戻った。

長かった冬休み中、イタリアらしい行事尽くしだったので、ここでご紹介。
カトリックの国イタリアでは、ジェズ・バンビーノ(子どものイエス・キリスト)が生まれた日を祝うナターレ(誕生の、の意味)は一年の中でも最も大切な行事のひとつ。12月8日から始まったクリスマスシーズンは年を越えて1月6日まで続く。

ヴィジリア(イヴ)の24日は日本の大晦日のような雰囲気。午前中、町の中はナターレを迎えるための最後の買い物をする人たちで大賑わい。魚屋は大行列。ヴィジリアには宗教的な理由から肉は食べず魚料理を食べるのだ。午後には多くの店が閉まってしまうので、プレゼントを準備するのもラストチャンス。プレゼントは子どもだけでなく家族や親戚、大切な友達にも贈られる。
夕食を私は今年も24日の午前中まで作品のデリバリーがあり、最後の作品を届けたらそのまま森の家へ。地元の町のバールへ常連やオーナー一家にナターレのご挨拶を兼ねアペリティーボをしに行ってから、魚介のリゾットとタラのソテーで簡単に済ませた。キリストの誕生を厳かな気持ちで迎えるヴィジリアの夜は、家族で食事をし、教会のミサに行ったり映画を観たりして、まったり過ごすのだ。うちでは今年もプロジェクターでクラシックな映画鑑賞(確か『101匹わんちゃん』)。

ナターレの朝、子どもたちは起きたら真っ先にツリーの下に。ナターレの前から置かれてあった親戚や友達からの贈り物が並ぶ中、いちばんのお目当てはバッボ・ナターレ(クリスマスパパことサンタクロース)からのプレゼント。9歳のゆまはそろそろプレゼントの本当の送り主を問い始めたものの、いまだに純粋に楽しみにしている。

ナターレのお昼はこの日のために遠くからも集まった家族や親戚とお祝いするもの。でもうちは親戚より親しい友達や、家族と離れている友達と過ごしている。

ボロネーゼなのが誇りである、夫に嫁入りしたものの、残念ながら伝統の家族の味を残してくれる家族がいないので、子どもたちに残せる味の記憶は私が作ることになる。キッチンでもクリエイティブな私、伝統レシピを参考にはしても、どうしてもマイウェイにアレンジしたくなる。特に野菜をたくさん食べたい、食べさせたいので、前菜や付け合わせがメインに負けない充実の内容に。

でも、ボローニャでナターレのテーブルに欠かせないトルテッリーニ・イン・ブロードは、伝統どおり。ブロードは、信頼の肉屋セレクトの去勢鶏、牛リブ、牛骨、牛タン、それにセロリ、ニンジン、 玉ネギ、ローリエ、クローブ、粒胡椒を水からぐつぐつ煮て、丁寧にアクと脂をとって作る。そのブロードでゆで上げるのは、仲良しの大人気生パスタ屋、スフォリア・リーナのトルテッリーニ。

パルミジャーノをかけて熱いブロードといただくトルテッリーニ・イン・ブロードは、間違いなく子どもたちがいちばん好きなボローニャ伝統料理。たえも一皿ペロリと食べてしまう。
ちなみにボローニャのナターレのテーブルに並ぶもうひとつのプリモピアットといえば、ラザニア。 ベシャメル、幅広パスタ、ラグー(ミートソース)、パルミジャーノを順に2、3度重ねてオーブンでこんがり焼いた料理は伝統どおりに作ると1ポーション1000キロカロリーにもなる超ハイカロリー料理。今回はベジタリアンで作ろうかと思ったものの子どもたちはあまり好きでないのでパス。
---fadeinpager---

ゆでた肉、ボッリートは、温め直してセコンドピアットに。 畑のパセリとアンチョビ、ケッパー、ゆで卵の黄身、酢につけたパンなどで作った自家製サル サ・ヴェルデといただく。この鮮やかな緑のソースが大好評。肉料理にはもちろん、ブルスケッタにのせてアンチョビやゆで卵を載せたらアンティパストにもなる優れもの。作りたては色も香りも絶品なのでぜひ作ってみてほしい。
ボローニャのナターレ菓子といえばパノーネやチェルトジーノ。どちらもフルーツの砂糖漬け、 ナッツ、はちみつ、モスタルダ(西洋カリンやオレンジにマスタードが隠し味のジャム)、チョコレートなどで作って寝かせたお菓子。

でも子どもたちはモスタルダが苦手で定番パネットーネの方が好き。

ミラノ発祥のパネットーネ。これはとなり町発祥の人気ベーカリー、カルツォラーリのもの。卵黄とバターをたっぷり使ってパネットーネ酵母で長時間熟成・発酵させたナターレのお菓子は、一年中食べたい季節菓子のひとつ。

食後は暖炉の前に移動。食後酒やお茶にナッツや果物をむきむき、大切な人たちと暖炉を囲んで過ごす。そして誰もが必ず「暖炉って最高だよねぇ。」とそれぞれのナターレの思い出を語り出す。これほどシンプルで素敵なナターレの過ごし方はないと思う。
翌日26日はサント・ステファノで祝日。 パオロに由来を聞いたら、あっさり「知らないなぁ」。。。 調べると、サント・ステファノが祝日なのはオーストリア、デンマーク、アイルランドなど数カ国だけで、イタリアで祝日になったのは1947年から。理由は宗教的なことではなく、要するに3 連休にするためだとか。
ともかく、この日はナターレの残り物を食べ、2日間食べて飲んでなまった身体を動かすべく出かける日とも言える。私たちはアドリア海近くの中世の町、サンタルカンジェロ・ディ・ロマーニャまでドライブ。

リミニからほど近いこの小さな町では、年間を通してアートや劇などカルチャーイベントがたくさん行われ、イタリア内外からの観光客も数多く訪れる。毎月第一日曜日にある蚤の市もボローニャよりお値打ちな物が出回るので毎月通いたいくらい。コストパフォーマンスの良い食べどころもとても多く、なおかつこの町出身で食周りのコミュニケーションの仕事をしているヴェロニカがいつもおすすめに連れて行ってくれるので、もう行くだけで至れり尽くせり。

周りにはいくつも小高い丘があり、その上には小さな中世の村や修道院が。世界で面積の小さい国第5位のサンマリノ共和国もそんな丘の上にあり、サンタルカンジェロから車でたった30分。何度訪れても発見がある大好きなエリアだ。
それから数日たった大晦日。イタリアではカポダンノ(年の初め)と言って、この日の夜新しい年を迎えるお祝いをする。食事の定番はコテキーノやザンポーネとレンズ豆。レンズ豆は金運アップの意味があって正月料理に欠かせない。

コテキーノもザンポーネも中身は同じ。豚の皮、頭や首などのコラーゲンの多い部分に豚ひき肉、それにナツメグやシナモン、胡椒などのスパイスを混ぜた太いソーセージで、コテキーノは内臓に、ザンポーネは豚の後ろ足に詰めたもの。これを3、4時間グツグツ煮ると、ゼラチン質なソーセージのようになる。

ボローニャの隣、モデナが発祥のこの料理はいまやイタリア全土で定番の正月料理になっている。 カウントダウンは食事の後友達と集まって、という人も多い。ボローニャの友達からも村の友達からも誘われたものの、風邪っぽい家族がいたので、近くを散歩して夕焼けを見に行って、オセロで遊んで、年が明ける前に寝てしまった。

---fadeinpager---
ふと目が覚めると日付が変わっていて、山間のあちこちから花火の音が聞こえた。
ちなみにボローニャのカポダンノの名物といえばヴェッキオーネ。過ぎ行く年を象徴する彫刻ヴェッキオーネ(大きな年寄り、お古、の意味)をカウントダウンとともに燃やして新しい年を迎えるのだ。

ボローニャのおへそ、マッジョーレ広場に登場した2019年ヴェッキオーネは高さ8メートルの引き出しおじさん。引き出しの中には、ボローニャ市民が書いた来年に向けたポジティブな言葉が刻印されたメタルの板と、過去に葬りたいことを書いた紙が数千枚。広場には1万人もの人がカウントダウンに集まった。深夜0時に着火され、数時間後ヴェッキオーネが灰になった後に残ったポジティブメッセージ入りメタルの板は、集まった市民に一枚ずつ渡された。それはちょっとしたお守りかおみくじのよう。1922年から続くヴェッキオーネのプロジェクトで最も多くの人が製作に携わり、かつ記憶に残るものになったのではないか。
1ヵ月ほど続いたナターレ期間、締めくくりは1月6日、エピファニア。 伝説によると12月25日、ジェズ(イエス・キリスト)の生誕を知った東方三博士は、神の子を拝むためにベツレヘムへ向かう。道中迷いそうになり、道を尋ねた人物が老婆べファーナだった。ベファーナは東方三博士に同行するよう誘われるものの、拒否。しかし後悔して東方三博士を追いかけるも、時すでに遅し。それで家々を回り、出会った子どもたちみんなにお菓子を渡すようになったとか。その中にジェズ・バンビーノがいることを願って。

ナターレの贈り物といえばバッボ・ナターレ、になったのはイタリアでは近年になってからで、伝統では1月5日の夜中にべファーナが贈り物を持ってくることになっている。子どもたちは靴下を暖炉前、玄関の外にかけて寝て、翌朝ドキドキしながら中を確認。良い子にはお菓子を、悪い子には炭を入れていくのだ。この辺りがユーモアのある魔女っぽくて好き。

サン・ニコラ(サンタクロースの元)、バッボ・ナターレ、ベファーナにイースターのウサギ(チョコレートの卵)に歯の妖精に(歯が抜けると抜けた歯と交換にお金がもらえる)、と贈り物をもらえる機会を指折り待っている次女のみう(三姉妹でいちばん手強い)。エピファニアの朝、靴下には、チョコレートのたまご2つとクルミやピーナッツ。どういう意味??と言うので「もうちょっと良い子を目指してね、じゃない?」と言ったけど、納得したかなぁ。
---fadeinpager---

ところで、毎年元旦にはおせち料理を用意することにしている。あるもので作るので気分だけ、だけれど、祖母から受けついた御重や塗りのお椀を出すと、背筋が伸びる。手がかかるのに子どもたちは品数を食べてくれない。でも「日本の料理ってきれいだね。」と楽しみにしていてくれるのだから、きっと日本の伝統の大事なインプットにはなっていると思う。

一番人気は炭火で焼いた餅…。あと田作り。私も大好き。
それにお正月飾り。

日の丸の扇子を持ったあっぱれ陽気なねずみくんに、 昔から惹かれて作り続けている円をお正月飾りにも入れた。
○は今年のラッキーモチーフだそうで、ぜひ縁起にあやかりたい。

2020年、みんなにとってまんまる笑顔がいっぱいな良い年になりますように。
ARCHIVE
MONTHLY










