ワイキキ小学校を成績優秀校に変えた16の習慣。
Culture 2021.08.10
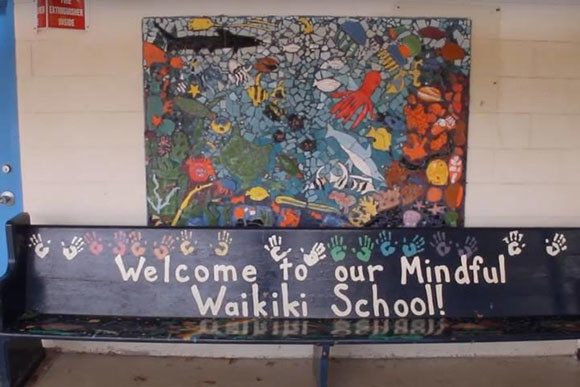
YouTube/OurPublicSchool
文/船津徹(TLC for Kids代表)
「あるプログラム」を学校の基本方針に取り入れた公立小学校の軌跡は、生来の才能に関わりなく学力を鍛えられることを証明しましたが、これはあくまで稀なケース。優秀な子どもを育てる親には共通点があります。
日本人に馴染み深い南国リゾート地ハワイ。あまり知られていませんが、ワイキキビーチのほど近くにあるワイキキ小学校は、全米の公立学校にとって最大の栄誉である「ブルーリボン賞」を、2007年、2013年、2020年の合計3回受賞している成績優秀な小学校です。
成績優秀校と言っても学区内に住む子どもであれば誰でも通うことができるごく普通の公立小学校です。生徒構成は低所得者家庭が22%、マイノリティが84%、英語を第二言語で学ぶELL(English Language Learner)が22%と、決して恵まれた環境とは言えません。事実、2003年の学力調査では、習熟目標に到達している生徒の割合が英語41%、算数28%と、学力的にも厳しい学校でした。
ところが「あるプログラム」を取り入れたことをきっかけにワイキキ小学校は成績優秀校として全米で知られるようになったのです。いったいどうやって成績不振校から優秀校へと変貌することができたのでしょうか?
---fadeinpager---
習慣教育を取り入れたことで学校が変わった!
ワイキキ小学校が変わるきっかけとなったのが、カリフォルニア州立大学名誉教授アーサー・コスタ博士が提唱する「Habits of Mind」と呼ばれる「習慣教育」を取り入れたことです。
アーサー・コスタ博士はカリフォルニア州の学校指導カリキュラム制作担当者として長らく教育行政に関わってきました。どうしたら学業や社会で成功する人材を育てることができるのか? 全米の教育者や研究者と議論を重ねる中で、優秀な子どもには「共通する習慣」があることが分かったのです。それらをまとめたものが「Habits of Mind」です。
コスタ博士の「Habits of Mind」を学校の基本方針として取り入れてからワイキキ小学校の学力は飛躍的に向上し、2008年の学力調査では英語の習熟率が83%、算数が66%を記録。2014年には英語94%、算数93%というレベルまで高まったのです。
---fadeinpager---
コスタ博士が提唱する「16のよい習慣」とは、次のとおりです。
【16のよい習慣】
1.やり抜く習慣・・・あきらめない、やり続ける
2.衝動を抑える習慣・・・行動する前に考える、落ち着く
3.共感して聞く習慣・・・注意深く聞く、気使う
4.柔軟に考える習慣・・・違う見方をする、別の可能性を考える
5.思考を思考する習慣・・・自分の思考の偏りに気づく
6.正確を追求する習慣・・・見直す、念には念を入れる
7.疑問を持つ習慣・・・鵜呑みにしない、なぜ?どうして?と問う
8.知識や経験を活かす習慣・・・過去の経験を思い出す
9.明晰に伝える習慣・・・はっきり話す、言葉を選ぶ
10.五感を使う習慣・・・感じてみる、触れてみる
11.想像、創造、革新する習慣・・・ユニークであれ、独創的であれ
12.不思議と発見を楽しむ習慣・・・よく観察する、夢中になる
13.チャレンジする習慣・・・勇敢であれ、リスクを冒せ
14.ユーモアを持つ習慣・・・楽観的であれ、肩の力を抜く
15.共に考える習慣・・・協学せよ、共に学ぶ
16.学び続ける習慣・・・興味を持ち続けよ、変わり続けよ
出典「Habits of Mind」Arthur Costa
---fadeinpager---
家庭と学校が連携して良い習慣を育てる。
「Habits of Mind」は16の習慣を育てることを目標としています。もちろんこれらすべてを一度に教えることは不可能ですから、まずはひとつの習慣からスタートし、時間をかけて他の習慣を指導していきます。
ワイキキ小学校で行っていることは、とてもシンプルです。16の習慣のうち、毎月最低ひとつの習慣をテーマに掲げ、学校と家庭が連携して子どもに意識づける、といった地道な活動です。
たとえば「やり抜く習慣」がテーマであれば、授業中にわからない問題に出会ったときに「あきらめないで!」と生徒同士が声をかけ合います。先生も「やり続けよう!」と励まします。家庭でも親が「あきらめないで!」「やり続けよう」と共通の声がけをするのです。
子どもを取り巻く人たちが同じ習慣を意識し、同じ言葉をかけ続けることで、必然的にその習慣に対する意識が高まります。いわば「あいさつのしつけ」のようなものです。親、兄弟、近所の人が「おはようございます」と声を毎日かけることで、ごく自然に子どもも「おはようございます」と照れずにあいさつできるようになります。
親や先生が根気強く声を掛け、励まし続けることで、生徒たちは、ひとりひとりが自分たちのできる範囲であきらめずに思考し、課題に粘り強く取り組んでいく習慣を身につけることができるのです。
近年、教育の分野において「やる気」や「粘り強さ」などの「非認知能力」が注目されていますが、コスタ博士の習慣教育は「非認知能力の具体的な育成法」であり、ワイキキ小学校の例は、非認知能力を鍛えることが学力に良い影響をもたらすことを証明したケースと言えます。
---fadeinpager---
親の習慣が、子どもの習慣を作っていく。
ワイキキ小学校の実践によって、習慣の力は、家庭の経済環境や家柄、国籍や持って生まれた才能に関わりなく、誰でも訓練によって高めることができることが明らかになりました。ただし、誤解してほしくないのは、習慣力は本質的には学校や先生に教えてもうものではない、ということです。家庭と学校が一致団結して習慣教育に取り組んだワイキキ小学校は極めて稀なケースです。
子どもによい習慣を育てるには、あくまでも「親」が中心となること。家庭内の努力が必須になります。親が子どもと協力をしながら、親自身も習慣を変えていくことで育つものであり、優秀な子どもを育てている家では、周囲から言われなくても、よい習慣を鍛えるための実践を行なっているのです。
ワイキキ小学校の例でも分かりますが、習慣を作るということはそこまで難しいことではありません。まずは何かひとつに集中して、親がよい習慣が身につく仕組みを作ってあげることで、加速度的に大きな効果を発揮していきます。家庭での過ごし方、遊び方、声のかけ方、サポートの仕方、与える環境など、親の行う小さな行動が子どもの習慣を大きく変えるきっかけとなるのです。
---fadeinpager---
では、優秀な子どもを育てている家庭では、具体的にどんな習慣を意識しているのでしょうか? そこには、驚くほどの共通点があります。たとえば以下のようなことです。
・勉強しなさいと言わない
・勉強は学校や塾任せにするのではなく、家庭で親が教えている
・本を好きにさせ、興味を引き出している
・習い事を全力でさせている
・習い事は、親が技能の底上げをサポートし、トップクラスにしている
・どんな小さなことも、子どもに選択をさせている
・食事中の楽しい雑談を大切にしている
・子どもに考えさせる質問を多くしている
・ボードゲームやカードゲームで遊んでいる
親が上記のような習慣作りを意識し、子どもとの接し方を少し変えるだけで、子どもの思考と行動習慣が変わっていきます。家庭での習慣教育が、自ら学び、自ら考える力を育み、確かな学力と豊かな人間性を兼ね備えた人材育成へとつながっていきます。
YouTube/OurPublicSchool
TLC for Kids代表。明治大学経営学部卒業後、金融会社勤務を経て幼児教育の権威、七田眞氏に師事。2001年ハワイにてグローバル人材育成を行なう学習塾TLC for Kidsを開設。2015年カリフォルニア校、2017年上海校開設。これまでに4500名以上のバイリンガル育成に携わる。著書に『世界標準の子育て』(ダイヤモンド社)『世界で活躍する子の英語力の育て方』(大和書房)がある。
text: Toru Funatsu









