我が愛しの、ジェーン・バーキン 11歳から綴られたジェーンの日記を読み解く。
Culture 2024.06.12
2018年、ジェーン・バーキンの日記が発売された。11歳からの寄宿舎生活、3人の男性との出会いと子どもたち、仕事......喜びも悲しみも、自身が綴る約60年に及ぶ人生のストーリー。
11歳から書き始めた日記は、寄宿舎生活の孤独を癒やすためだった。『Munkey Diaries(マンキー・ダイヤリーズ)』(Fayard刊)は可愛がっていた猿のぬいぐるみに語りかける形で進行する。セルジュ・ゲンズブールとの暮らしを捨て、ジャック・ドワイヨンのもとへ向かうところで終わり、続く『Post-scriptum(追伸)』は、2013年に長女ケイト・バリーが亡くなって日記が書けなくなるまでが収められており、19年10月に出版された。

『Munkey Diaries』(上)『Post-scriptum』(下)
表紙の乗馬服を着た猿のぬいぐるみは伯父からのプレゼント。1冊目は寄宿舎にいた時の鬱屈した気持ちや3人のパートナーとの出会いや別れのシーンが綴られ、2冊目では別れたセルジュに続いて最愛の父親が亡くなるシーンや東日本大震災への対応が残っている。ジェーン・バーキン著 ともにFayard刊 9.40ユーロ(上左)、9.90ユーロ(上右)
──日記を刊行した動機は?
日記は人生そのもの。喜びも悲しみもそこにはあり、これまで語ったことのない話がたくさんあると思ったから。私に取材したりしなかったりで、多くの本が書かれている。それならば自分の解釈も伝えようと思った。日記ならその時の感情が蘇る。ごまかしなしに......。記憶と思い出は別なもの。
──「人は変わらない」と書いていますね。確かに子どもらしさを失わず、創造力豊かな言葉遣いです。
読み返してみて、まさに人は変わらないことにびっくりした。自分の欠点もそのまま。子どもっぽくて面倒臭い人。白血病を発症して治療している間に、友人のガブリエルが私の日記をテキストに打ち込んでくれた。彼女なしにはやり遂げられなかった。ずっと公表したくないと思っていたのは怖かったから。自分で自分が好きじゃなかった。すべて英語で書いていたので3回仏訳した。軽快な英語に比べ、フランス語にすると間延びする。セルジュの歌のように弾む感じが出なくて残念。なかなか満足できなくて出版に2年もかかってしまった。
──順調だった仕事のことはほとんど書かれていないのはなぜ?
自分にとって感情面のほうが大事だったから。だいぶ偏っていたから、適宜コメントを補い、映画や歌のことを付け加えました。
---fadeinpager---
──日記はぬいぐるみの猿に語りかける形で書かれています。ずっと一緒だったのですか?
セルジュが亡くなるまではね。いまは彼と一緒に棺桶の中で眠っている。ファラオの埋葬品みたいに。セルジュはこの猿のために「オランウータン」(1969年)という曲を書き、彼のアルバム『メロディ・ネルソンの物語』のジャケットに私と一緒に写っている。
──代わりのぬいぐるみを見つけました?
かけがえのない存在だったのよ! 猿の服は祖母が縫ってくれたり、自分で手作りしたもの。旅行に行く時も一緒で、連れて行かないなんて考えられなかった。父が難しい手術を受ける時は貸してあげたし、セルジュがアメリカン・ホスピタルに入院した時は彼の側にいた。ある時、アンリ・シャピエ司会のテレビ番組「ル・ディヴァン」に出演する直前に、飼っていたブルドッグの一匹、ベティが噛みついてバラバラにしてしまったのだけど、番組の開始を遅らせてもらって、ぬいぐるみを縫い直したわ。失くしたらどうしようといつもビクビクしていた。猿の服はケイトとシャルロットにあげた。猿のことをあまり知らないルーにはズボンをあげたわ。もう思い残すことはない。猿はずっと猿のまま!
──父親とセルジュには共通点があったとか。
父は気まぐれな人だった。ふたりとも睡眠薬を飲んだ後が愉快だったわ。ユーモアのセンスも似通っていた。セルジュは兄のアンドリューと話が合い、ふたりは友情で結ばれていた。父も兄もセルジュに魅了され、いえ夢中だった。広い心と愛情で結ばれたみんなが一緒にいるのを見るのはこのうえない喜びだった。前夫ジョン・バリーに対して、両親は自分たちが歓迎されず、邪魔者扱いされていると感じていたけれど、セルジュは両親を大歓迎した。雪の降るロンドンで私の小さな家にみんなで集まって幾度クリスマスを祝っただろう......。あるクリスマスでは、セルジュが浮浪者を招き入れたことがあった。列車やフェリーで旅したこととか、イギリスでの思い出はたくさんあって素晴らしい時代だった。私がイギリス人であること、イギリスの家族に彼がこれほど受け入れられたこと、イギリスの家族が彼のロシアの家族を大好きになったこと......そうしたことをセルジュはとても喜んでいた。
──恋に生きる恋多き女性ですが、男性の気を引くためや許してもらうために突飛な行動をしたことはありますか?
ある晩、セーヌ川に飛びこんだことがある。セルジュの顔にクリームパイをぶちまけた後だった。そこからどう仲直りするかがとても難しくて! ドラマティックな展開が必要だったの。

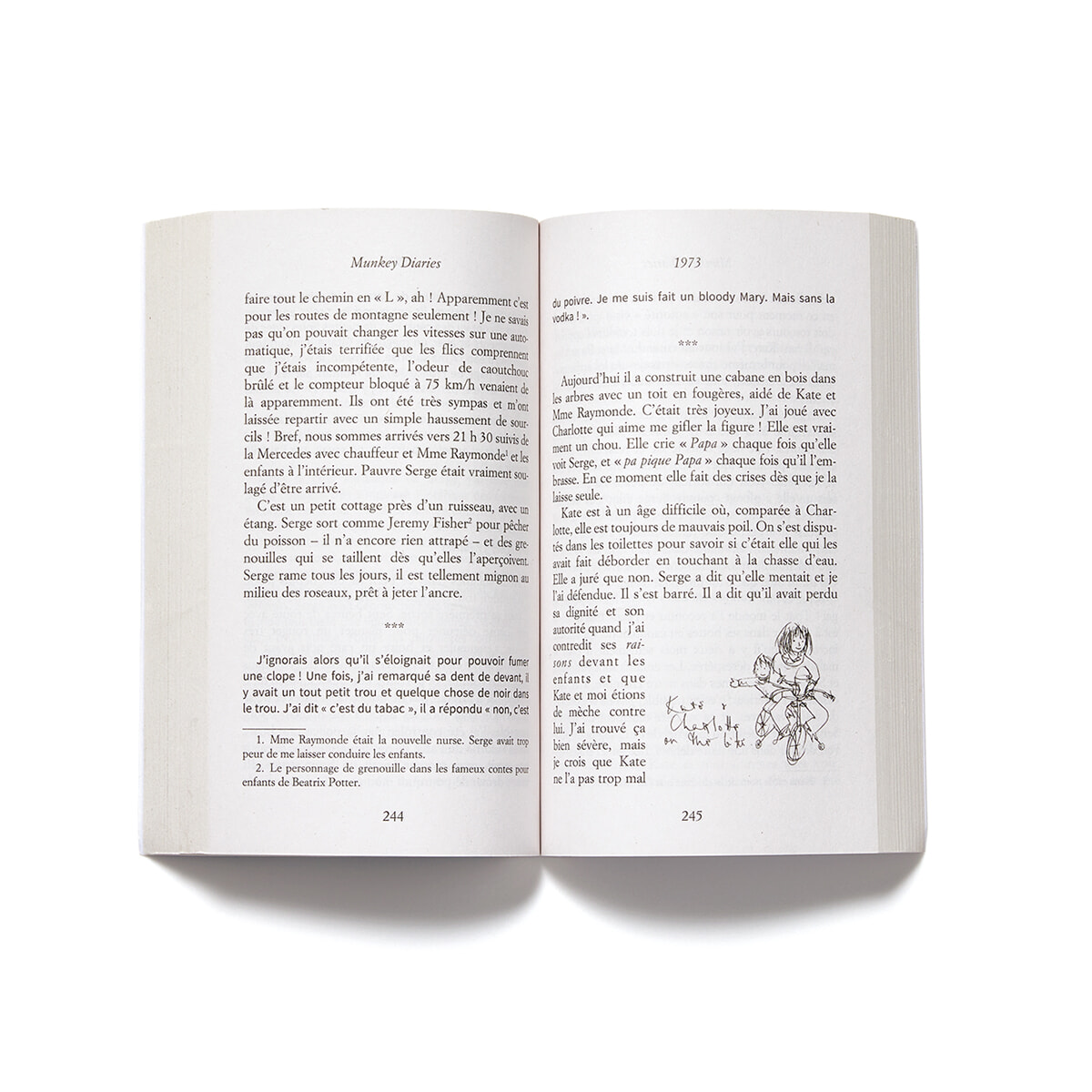
英語をフランス語に自ら訳し、注釈もつけた。添えられているデッサンにも注目。ケイト妊娠中で不安な頃(上奥)と、シャルロットが生まれたゲンズブールとの幸せな暮らし(上)で、タッチがかなり異なっている。
---fadeinpager---
──この日記はひとりの女性が解放されていく記録ともいえます。
確かに。私は他人の視線をあまりにも気にしながら生きてきた。恋愛の裏には恐れる気持ちがある。日記を読み直して思ったのは「こんなにびびっているなんてぞっとするわ!」ということ。人は悲しい時、気持ちを吐き出したい時、励ましてほしい時に日記に飛びつく。人生が楽しくてしょうがない、うまくいってハッピーな時は書く暇がない。そういう意味で日記は公平ね。セルジュなら「banal bleu(平凡な悲しみ)」と言うかしら。娘たちには日記をつけて保存することを常々勧めてきた。
──長女と次女に愛のこもった手紙を書いていますね。まだルーが生まれていない頃でした。ケイトのことをヴェラスケスの絵になぞらえています。
ケイトが生まれた頃を思い出すのは辛かった。日記ではケイトの目の話を書いていて、ケイトの父親と「この娘はとてもチャーミングになるね」と話していた。ケイトは公平な性格で、海辺でいつもシャルロットを守っていた。思わず泣いてしまったくだりは、アンドリューと娘ふたりが交通事故に遭った時のこと。病院で姉妹はくっついて離れず、シャルロットは「アンドリューのせいじゃない」と繰り返していた。
──日記を通じて感じるのは、あなたの自信のなさや罪悪感です。
それは自分の人生に重くのしかかっている。自分は融通の利かない人間、つまり型にはまった人間だったと思う。もっと大胆になれればよかった......。両親に気に入られたい、学校で嫌われたくない。がっかりされたくない、という不安を常に抱えていました。
──運命を変えようと、若くしてフランスへ旅立ちましたね。
いまとなっては必然だったと思う。どこかに行く必要があった。あまりにも完璧な両親だったから。フランスに来てある種の解放感を感じたわ。誰も私が何者かなんて知らないし、喋るのが下手でも咎められない......なんて素敵なの! フランスで私は愛され、受け入れられた。イギリスに戻ろうと思ったことは一度もない。セルジュやジャックと別れた後でも。シャルロットはニューヨークで自由を味わっているかもしれない。日常のしがらみや亡くなったケイトのことから解放されて。その時はわからなくても、後から理解できることがある。
──ケイトが亡くなった後、「ここを去るわ。どこか別な場所が必要」と言っていませんでしたか?
いいえ、機能停止状態だったからどこにいようがあまり関係なかった。ひとりだけ別な人生を歩んでいる感じ。子どもを亡くした人の多くはそんなふうになると思う。とにかく生きて、何かをしようと試みる。でも私は大した努力をしなかった。病気になったのも、そのほうが都合がよかったからでしょう......。
──あるインタビューでケイトのことを「彼女のことを46年間知ることができてラッキーだった」と語っていましたが、悲しみの中で言う、最も素敵な言葉だと思います。
あらゆる点で素晴らしい娘だった......。おどける時も悲しむ時も、とてつもなく大きな心の持ち主。娘が恋しい......でも本当に、46年間一緒にいられる機会に恵まれた。日記はケイトの死で終わっている。もう書けなくなったから。別な形で執筆を続けることはあるかもしれないけれど......。
▶︎ジェーン・バーキン、永遠のファッションアイコンの魅力を紐解く。
*「フィガロジャポン」2024年3月号より抜粋
●1ユーロ=約169円(2024年6月現在)
photography: John Chan text: Lætitia Cénac (Madame Figaro)










