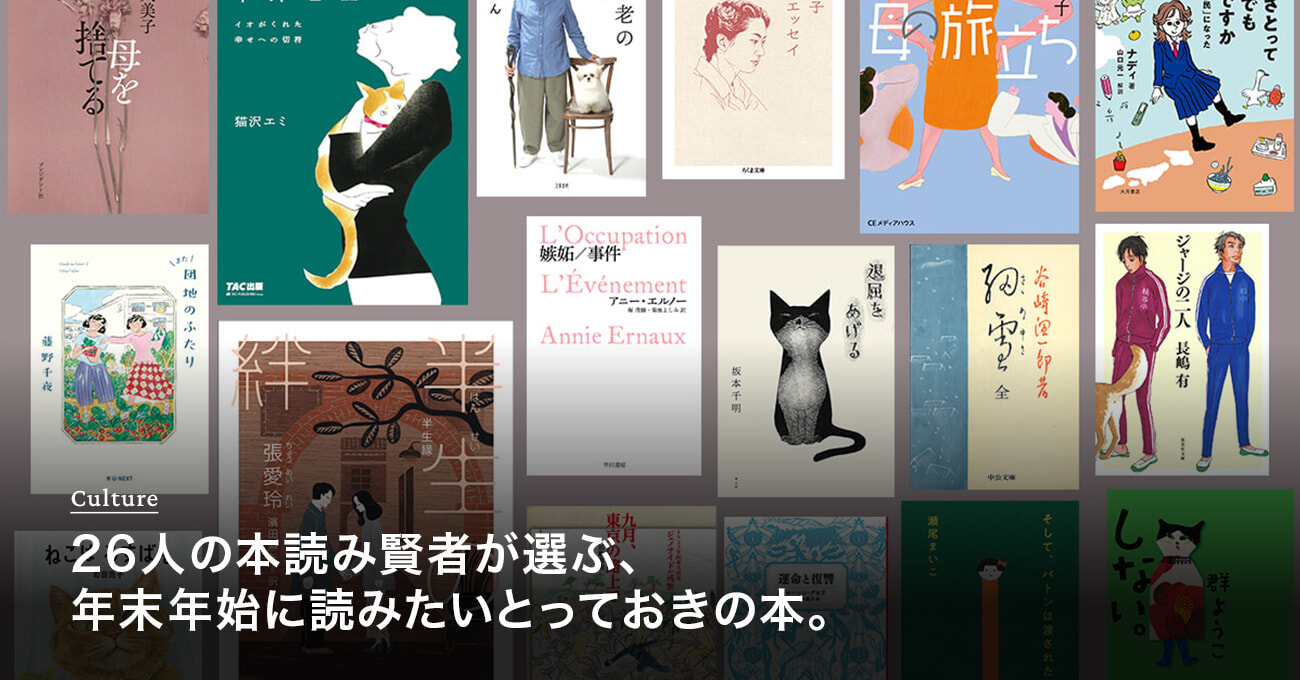うつわディクショナリー#42 お正月間近のいま、木漆工とけしのお椀と重箱を
うつわディクショナリー 2018.12.23
私たちの暮らしに馴染む漆椀とお重
「木漆工とけし」は、木地師の渡慶次弘幸さんと塗師の渡慶次愛さんご夫婦が沖縄で営む漆器工房。沖縄産の樹木を漆器づくりに取り入れることで、お正月などハレの席にも、カジュアルなふだんの食卓にも合う独特の素朴さをもった暮らしのうつわを作っている。お正月直前のいまだからこそ、自分にぴったりの漆器を探しに出かけてみては?

—渡慶次さんご夫妻が、漆器をはじめたきっかけは?
渡慶次弘幸:ふたりとも沖縄出身で、工芸指導所で出会いました。僕が木工課で、妻は漆課。卒業後にそれぞれ輪島で漆器の木地屋、漆工房に弟子入りしました。輪島の徒弟制度は4年間が弟子、その期間が過ぎると一人前として認められ「年期明け」をし、その後の1年間をお礼奉公の期間として働きます。お礼奉公を終えた後もさらに2年間仕事をする中で、結婚して子供ができ、子育てを沖縄でしたかったこともあり戻って仕事をすることを考えました。
—沖縄には琉球漆器がありますから、人々は漆器に親しみがあるのでしょうか?
渡慶次:沖縄の温度や湿度は漆器づくりに最適で、伝統工芸品として琉球漆器が残っていますが、琉球漆器は琉球王朝の中で王様たちが使っていたハレのうつわとして、沈金(ちんきん)や螺鈿、箔絵、堆錦(ついきん)といった絢爛豪華な装飾があるものが主流。日常に漆器を使う文化はないので、僕らが作ろうと思っていた漆器が受け入れられるかどうか、正直心配でした。
—木漆工とけしの漆器は、沖縄の樹木を使っているんですよね。
渡慶次:沖縄ならではの木というとデイゴですね。センダンやイタジイ、クスノキなども使いますが、これらは本州でも生育します。沖縄の木は、ふしが多かったり、曲がっていたり、硬すぎたり柔らかすぎたりして加工しずらいので漆器に使う気はなかったんですが、ある時、たまたま譲り受けたセンダンの木を削ってみたところ、面白くて。
—どんなところが面白かったんですか?
渡慶次:沖縄独特の成長の過程もあり、轆轤で削ると木肌がぼそぼそしていて荒いんです。でもそれをいかして削るのも面白いのではないかと思うようになって、妻に「一度、塗ってみてよ」と。彼女は、塗師として、木地に合わせて塗り方を変えることでその特徴をいかしていくことを大事にしています。その時も、センダン独特の荒さを残しつつ仕上げてみてはどうだろうかと、木目や削り跡をつぶさずに、独特な質感が生まれる塗り方を考えてくれました。
—それが多くの人に親しまれている「サビ」仕上げのはじまりだったんですね。
渡慶次:沖縄の木に向き合って始めた仕事が、地元の人にも受け入れられて嬉しかったですね。地元の素材を使い、樹種によって異なる木の特徴を読み取ってちょうどよい削りと塗りを探す仕事は、僕たちだからできることなのかなと。二人でお互いの仕事を観察しながら木地と塗りのちょうどいいバランスを探していくんです。
—琉球張子で人気の豊永盛人さんとのコラボレーションした作品もおおらかでいいですね。
渡慶次:サビの仕上げや、漆にスズ(錫)を混ぜた仕上げなど扱いやすい作品に取り組んで、たくさんの人に作品を手にとってもらうようになった頃、D&DEPARTMENT PROJECTの方から琉球漆器の老舗工房との二組展の企画をいただいて。この機会に以前から取り組みたかった琉球漆器と呼べるものを作ってみようと思いました。豊永盛人さんの感覚、絵付けや筆使いには、古い琉球漆器に描かれた文様のおおらかさに近いものを感じていたので、僕たちが琉球漆器をやるなら加飾を豊永さんにお願いしたいと思いました。文献や昔の漆器などをたよりに、それをそのままやるのではなく、当時の職人の仕事ぶりを想像しながら自分なりの絵柄にしていくその技術と自由さは、今まで漆器に興味を持っていなかった人にも目を向けてもらえるきっかけになっています。
—漆器の中で渡慶次さんご一家が一番よく使うものを教えてください。
渡慶次:お椀がいちばんですが、その他ではおかずを盛りつけたり、果物を入れたりできる大きめの平皿や鉢物ですね。木の素材感が分かる仕上げのものは、特に盛り付けやすくカジュアルに使えますよ。一般的には、お椀を使うことが多いでしょうけど、それ以外のかたちもぜひ生活に取り入れてもらいたいです。使うことが手入れになるので毎日気軽に扱ってほしいと思います。
※2019年1月7日まで「雨晴」にて、木漆工とけし×雨晴「時を重ねたもの」を開催中です。

今日のうつわ用語【琉球漆器】
14〜15世紀の中頃に中国から沖縄地方に伝わり琉球王国の中で制作されてきた漆器。沈金、堆錦、箔絵、螺鈿など絢爛豪華な装飾が施されている。沖縄の伝統工芸品。
【PROFILE】
木漆工とけし 渡慶次弘幸、渡慶次愛/HIROYUKI TOKESHI,AI TOKESHI
工房:沖縄県
素材:漆器
経歴:渡慶次弘幸さんは、沖縄県工芸指導所木工課卒業後、輪島の桐本木工所に弟子入り。愛さんは、沖縄県工芸指導所漆課卒業後、福田敏雄氏に師事。年季明け後に福田敏雄氏、赤木明登氏の両工房にて勤める。2010年ふたりで沖縄に戻り独立、工房を構える。http://www.tokeshi.jp/
雨晴
東京都港区白金5-5-2
Tel. 03-3280-0766
営業時間:11時〜19時30分
定休日:水曜
https://www.amahare.jp/
✳商品の在庫状況は事前に問い合わせを
「木漆工とけし×雨晴 『時を重ねたもの』」開催中
会期:2018年12/14(金)〜2019年1月7日(月)
※定休日:毎週水曜日
年末年始の休業日:2018年12月31日(月)〜1月4日(金)
木漆工とけし 渡慶次弘幸、渡慶次愛/HIROYUKI TOKESHI,AI TOKESHI
工房:沖縄県
素材:漆器
経歴:渡慶次弘幸さんは、沖縄県工芸指導所木工課卒業後、輪島の桐本木工所に弟子入り。愛さんは、沖縄県工芸指導所漆課卒業後、福田敏雄氏に師事。年季明け後に福田敏雄氏、赤木明登氏の両工房にて勤める。2010年ふたりで沖縄に戻り独立、工房を構える。http://www.tokeshi.jp/
雨晴
東京都港区白金5-5-2
Tel. 03-3280-0766
営業時間:11時〜19時30分
定休日:水曜
https://www.amahare.jp/
✳商品の在庫状況は事前に問い合わせを
「木漆工とけし×雨晴 『時を重ねたもの』」開催中
会期:2018年12/14(金)〜2019年1月7日(月)
※定休日:毎週水曜日
年末年始の休業日:2018年12月31日(月)〜1月4日(金)
photos:HAL realisation:SAIKO ENA
ライター/ 編集者
子育てをきっかけにふつうのごはんを美味しく見せてくれる手仕事のうつわにのめり込んだら、テーブルの上でうつわ作家たちがおしゃべりしているようで賑やかで。献立の悩みもワンオペ家事の苦労もどこへやら、毎日が明るくなった。「おしゃべりなうつわ」は、私を支えるうちのうつわの記録です。著書『うつわディクショナリー』(CCCメディアハウス)
Instagram:@enasaiko ウェブマガジン https://contain.jp/
BRAND SPECIAL
Ranking