音楽を感じる! 懐かしの少女マンガのすすめ。
Music Sketch 2021.10.23
『立ちどまらない少女たち/〈少女マンガ〉的想像力のゆくえ』は興趣が尽きない一冊だ。『キャンディ・キャンディ』(1975~79年)をきっかけに、日本の少女マンガの発展におけるアメリカ文化やその文学との関連性、さらに音楽の扱われ方から吉本ばななといった文学作品への影響、昨今のアメリカンコミックから映画化された『ワンダーウーマン』にまで考察が及ぶ。著者の大串尚代さんは、アメリカ女性文学やフェミニズム、日本少女文化の研究者として知られる。そこで前半では音楽が感じられる少女マンガについて、後半ではミュージシャンを描くことでさらに自由になった少女マンガの世界、ジェンダー表現などの話を伺った。女性の生き方やジェンダー問題についての言及が盛んないまの時代だからこそ、少女マンガが活況を呈し始めた頃のマンガの在り方を見直したい。

『立ちどまらない少女たち/〈少女マンガ〉的想像力のゆくえ』大串尚代著 松柏社刊 ¥2750 著者は、慶應義塾大学文学部教授。少女文化と外国文化の交差点に立ち、少女マンガや家庭小説、ジェンダー論など多角的に取り上げ、一気に読ませるおもしろさ。
---fadeinpager---
音楽を題材に、同時に社会問題も描いていた水野英子。
――ロックを扱った少女マンガの先駆者といえば、『ファイヤー!』(1969~71年)を描いた水野英子さんでしょうか?
大串:ロックを含む音楽を扱ったマンガとして、水野さんの『ファイヤー!』は早かったですよね。反体制としてのロックを描いていらっしゃるのがすごいと思います。

写真左から、『ブロードウェイの星』(全2巻、双葉社刊)、『ファイヤー!』(全4巻、集英社社刊)ともに水野英子著。筆者私物。
――ミュージカルの世界を軸とした『ブロードウェイの星』(1967年)も『ファイヤー!』も、当時は相当センセーショナルだったと思います。前者では主人公スウは黒人と白人の混血児で、その親友ルースはロマの娘で黒人と結婚しますし、後者では男性が主人公でヒッピー・ムーブメントを扱ったり、インディアンが登場したりするなど、人種の描き方も意識が高い。ここにはアメリカの女性文学の影響もあると思いますか?
大串:そこは私もすごく知りたいと思っているところです。アメリカを舞台にした水野さんの作品は人種問題が描かれています。肌を黒く染めて黒人として振る舞ったり、黒人とカテゴライズされるはずの人が肌の色が白いために白人としてまかり通ったりするという、パッシング(人種異装)のモチーフが出てくるので、アメリカの小説を何か読まれていたんだろうか、と思ったほどです。ただ、当時は翻訳作品も限られていたかもしれません。ウィリアム・フォークナーや、ラルフ・エリスンなどは翻訳があったかもしれないんですけど。
――そうですよね。
大串:『すてきなコーラ』(1963年)は映画『麗しのサブリナ』(1954年)をベースにされているので、映画をご覧になっていたんでしょうね。『悲しみは空の彼方に』(1959年)や『アラバマ物語』(1962年、原作小説の翻訳は64年に刊行)など、人種を扱った映画作品もご覧になっていたかもしれません。このあたりはご本人にお伺いしたいところです。アメリカのカウンターカルチャーの状況というのをかなり調べられていたのではと思いました。いまであればネットでビジュアルも見られたりしますが、当時のことを考えると、新聞をはじめ、外国の雑誌や音楽雑誌だとか、時事的なところもすごくリサーチをされた方なんじゃないかという気がします。
---fadeinpager---
少女マンガから音楽が感じられる時。
――水野さんの作品を読むと、台詞がポエトリーのように感じることがあります。ミュージカルの部分など音楽がそのまま聞こえてくるように言葉が入ってくる。マンガから音楽を感じることはありますか?
大串:音楽というよりは、大島弓子さんや萩尾望都さんのような、内面のモノローグが多くある作品、台詞ではなく心象風景としての内面の独白が多いマンガには、ポエトリーというか、詩的なものを感じます。こうしたマンガ家の方たちは、まさに詩人だと思います。
――本当に、そう思います。
大串:歌手やロックが出てくるマンガではないんですけど、音楽が聞こえてきそうなものでは、少女マンガの中ではダンスマンガがけっこう多くて、山岸涼子さんの『アラベスク』(1971〜75年)、槇村さとるさんの『ダンシング・ジェネレーション』(1981〜82年)、あるいは演劇ものの美内すずえさんの『ガラスの仮面』(1976年〜)などでしょうか。ダイナミックなダンスの場面や、変拍子に登場人物が戸惑う場面などを見ると、「なんだろう、この躍動感、聞こえないはずの音楽が自分の脳内で鳴っている」と言うような(笑)、そういう感覚はすごくありました。
――少女マンガではないのですが、『神の雫』(亜樹直著、オキモト・シュウ画、2004〜14年)に“ワインを口にしたらクイーンが聞こえてきた”というシーンが描かれていて、その感覚や表現にしても、ページをめくってからのクイーンの演奏シーンの描かれ方にしても、とても感動したことがあります。
大串:下戸ということもあって読んでいないんですけど、おもしろいんですってね(笑)。
 『萩尾望都作品集17 アメリカン・パイ』萩尾望都著 小学館刊(品切れ、重版未定)
『萩尾望都作品集17 アメリカン・パイ』萩尾望都著 小学館刊(品切れ、重版未定)
――今度、お貸しします(笑)。話を戻すと、萩尾望都さんの『アメリカン・パイ』(1976年)でのドン・マクリーンの大ヒット曲「アメリカン・パイ」や、吉田秋生さんの『カリフォルニア物語』(1978〜81年)でのサイモン&ガーファンクルの名曲「ボクサー」のような、ストーリー内で孤独感や内省的な部分を伝えるために音楽を使うことをどのように思われますか?
大串:基本的には私の場合は、歌詞の方に注目しがちなんです。どうしても言葉を見てしまうのですが、その歌詞が醸し出している雰囲気から、自分の中で「音楽」を再構成する感じです。萩尾さんの「アメリカン・パイ」の中では「さよなら、ミス・アメリカン・パイ〜」という歌詞が実に淋しげなんですが、実際聴いてみると明るい曲調なんですよね。そういうマンガの中だけで聴いていた曲で、自分の想像していた曲の感じと実際の曲とでのギャップがあったのも、また楽しかったりしました。
――私は、『ファイヤー!』はスコット・ウォーカーをモデルにしていたと最近知りましたが、後追いして読んでいた当時は、ドアーズのジム・モリスンをずっとイメージしていました。そういうギャップもおもしろいなと思います。
大串:成田美名子さんの『CIPHER(サイファ)』(1985〜90年)では連載当時のアメリカの音楽がよく出てきました。主人公の女の子を男の子が車で送って行くときに、ラジオからカーズの「ドライブ」が流れる場面があるんです。そこに「君が家に帰る時に誰が送って行くんだろう」という歌詞が書かれていて、それで少年が「君を家に送るのはいつでも俺でありたいよ」と思うんです。その場面と音楽というのが分かち難く結びついてしまって、いまでも「ドライブ」を聴くと漫画の場面を思い出します。その頃は私もラジオをよく聴いていたのですが、マンガで使われた曲を聞く機会もあり、音楽とマンガがいっしょになって記憶に残っています。
――実際、ページの欄外や特別編に、どういった曲をBGMにして描いているかを漫画家の方が手書きで書き込んでいたりして、そこに自分の好きなバンドの名前を見つけては喜んでいました。私はカーズが大好きで、そのギタリストと同じ特製ギターを持っているほどです。読み直してみます(笑)。
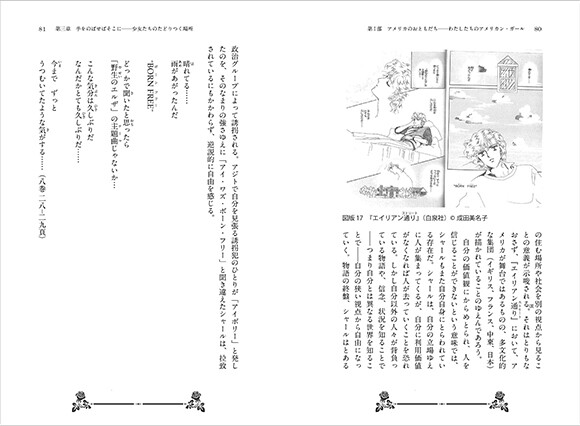 『立ちどまらない少女たち/〈少女マンガ〉的想像力のゆくえ』より、成田美名子の『エイリアン通り』に触れた章で。80年代に入り、観光旅行に加え、留学やホームステイが増えるなど、少女マンガの世界で憧れとして描かれていたものが現実となる。
『立ちどまらない少女たち/〈少女マンガ〉的想像力のゆくえ』より、成田美名子の『エイリアン通り』に触れた章で。80年代に入り、観光旅行に加え、留学やホームステイが増えるなど、少女マンガの世界で憧れとして描かれていたものが現実となる。
---fadeinpager---
音楽が聞こえてくるような少女マンガ、アメリカ女性文学。
――読者に向けて、 少女マンガの中での音楽のお話や、アメリカ文学の中での音楽に関する小説など、オススメの作品があれば教えてください。
大串:水野英子さんの『ファイヤー!』は名作だと思います。当時の少女マンガは高いステータスがなかったと思うんですけど、そのような中で社会問題に切り込むような作品が描けるんだ、ということを示した先駆的な作品ですね。クラシック音楽のものはくらもちふさこさんの『いつもポケットにショパン』(1980〜81年)とか、原ちえこさんの『風のソナタ』(1981〜82年)が好きでした。かっこいい女の子としては矢沢あいさんの『NANA』(2000年〜)もありますよね。
――くらもちふさこさんの漫画は、画風からして大好きでした。音楽が聞こえてくるようなマンガでは何かありますか?
大串:音楽が聞こえてきそうなという意味では岡崎京子さんの『東京ガールズ・ブラボー』(1990〜92年)か『ジオラマボーイ☆パノラマガール』(1988年)です。フリッパーズ・ギターとかポータブル・ロックとか、あの時代の音楽の雰囲気にすごく合っていて、あっけらかんとしているが故に空虚な感じがあったりするような雰囲気がすごく伝わるようなテンポのマンガだと思います。

1989年に刊行されたものが、2010年新装版に。『ジオラマボーイ☆パノラマガール 新装版』岡崎京子著 マガジンハウス刊 ¥1,362
――あの時代は岡崎京子さんの漫画を抜きにしては語れない気がします。アメリカ文学の女性作家ではいかがですか?
大串:中国系アメリカ人作家のエイミー・タンは、彼女自身もピアノの腕前がプロ級で、一時期スティーヴン・キングらとロック・ボトム・リメインダーズというバンドを組んでいましたね。彼女の『ジョイ・ラック・クラブ』(1989年)では、小さい頃ピアノを強制的に習わせられて、親に反抗したけれども、大人になってから子どもの頃に弾いたシューマンの「子どもの情景」の中の「おねだり」という曲を弾くという、ちょっと感動的な場面があります。
――エイミー・タンとスティーヴン・キングがバンドを組んでいたとはビックリです。どんな音楽なのか聴いてみたいです(笑)
*To Be Continued.
※記事中のマンガの発行年については、各作品が雑誌に掲載されていた時期に基づいています。

音楽&映画ジャーナリスト/編集者
これまで『フィガロジャポン』やモード誌などで取材、対談、原稿執筆、書籍の編集を担当。CD解説原稿や、選曲・番組構成、イベントや音楽プロデュースなども。また、デヴィッド・ボウイ、マドンナ、ビョーク、レディオヘッドはじめ、国内外のアーティストに多数取材。日本ポピュラー音楽学会会員。
ブログ:MUSIC DIARY 24/7
連載:Music Sketch
X:@natsumiitoh









