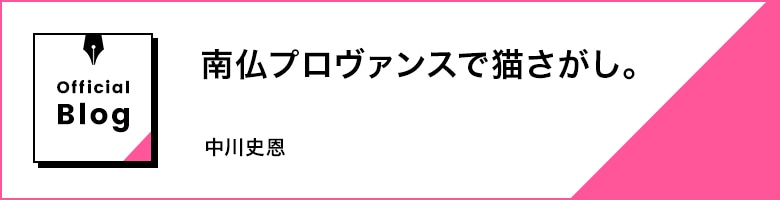
フランス、子どもの名付け事情と、動物病院の看板猫。
私、「この話をしたり聞いたりするとなぜか異様にテンションが上がる。」という大好物の話題がいくつかあるのですが、そのうちの一つが「名前」に関するもの。
(その他は、バスタオルを洗う頻度についての議論とか、人が結婚指輪なくした話とか、基本的に至極しょうもないものです。)
そう、人の「名前」が好きなのです。珍しい名前の人に出合うと、由来だけでなく、家族全員の名前を一人残らず聞き出したくなる衝動に駆られます。
先日、この記事をきっかけに、フランス語学校のクラスで、子どもの名付け方について話をしました。いろんな国出身の学生たちがいるので、各国の名付け事情を聞くのがとにかく楽しくて、興奮で私の顔は赤らんでいたのではないかと思います。
そして、その議論の盛り上がり方からしても、人の名前や、名付け方って、ものすごく文化的なトピックなのだなと改めて感じたのです。
最近、奥様がフランスで出産され、出生届を出したというクラスメイトが驚いていたのが、フランスの出生届にはファーストネーム欄が4つある! ということでした。
先生によると、もともとフランスでは、聖人歴(365日にキリスト教の聖人の名前が当てはめられているもの。例えば、5月30日は聖女ジャンヌ・ダルクの日とか。)から名前をつけるという決まりがあり、それ以外の名前を子どもにつけられるようになったのは、フランス革命後だとか。
つまり昔は、限られた名前しか子どもにつけることができず、それでは同姓同名があまりに多くなるので、役所での管理のために、その子の親の名前や親戚の名前、名付け親の名前などを入れていたと。
今でもいくつもの名前を持っていることは当たり前だけど、役所以外では使わないので本人ですら「なんだっけ。」くらいの感覚だというのには笑わされました。
もちろん、自由に名前をつけられるようになった現在も、決まりや制限はあるようです。例えば、「コカイン」くんは却下。(こういう話、どこの国でもあるのですね……)
もう一つ驚かされたのが、ファーストネームでその家庭の社会的地位がわかる、という話。これ、日本人の私にはピンと来ませんでした。苗字ならなんとなくわかるけど、ファーストネームで?
先生曰く、全ての階級がわかるわけではなく、「社会階級が上位」の家庭しかつけないファーストネームがあるというのです。(詳しく聞きたかったのに、先生があまりに神妙な顔をしてこの事実を語るもので、深く聞いちゃいけない気がして聞けず。無念。)
そして、バカロレア(高校卒業試験)の成績を、名前から分析してル・モンドが記事にしているのもまた興味深し。その記事によると、2018年のバカロレアで最高評価「très bien」を、割合的に一番多くとった名前は、「Garance」。4人に1人のGaranceちゃんが、très bienをとったようです。
えーっと、猫さがしですね、ついでに、みたいになっちゃってあれですが、今日ご紹介したいのは、ミャウがお世話になっている動物病院で働く猫、Pepper。



待合室で、よその猫にも吠える犬にも動じず、日々優雅に受付業務をこなしていらっしゃいます。ペップ、ペッパー、ペプシ、らへんは雄猫につけられる名前のようですね。ええ、猫の名前もいろいろ気になりますね。
ARCHIVE
MONTHLY









