僕の歌と言葉と読書と。尾崎裕哉と本の関係。
Culture 2021.10.20
歌うたいは言葉とともに、自身の人生と未来を奏でる。
彼にとって、本とは? 読書とは?
読書という体験が、尾崎裕哉の音楽に与える彩りについて。

シャツ¥69,000、パンツ¥72,000/ともにルメール(スクワット/ルメール) 中に着たトップ¥25,300/エム エー エス ユー(ソウキ)
---fadeinpager---
たった一行だけでも、いいフレーズに出合うことができれば、本を開いた意味がある。
「僕、正直に言うと、読書は苦手なんですよね……」
少しはにかみながらも、尾崎裕哉が開口いちばんに語った言葉がこれだ。その笑顔には、悪びれた様子はまったくない。
「どうしても活字を見ると、すぐに眠たくなっちゃうんです(笑)。逆に、スラスラと集中して読める時は、すごく調子がいい時。でも本を読みたいという気持ちも、本に対する憧れもあるから、気になる本はとりあえず買ってしまう。そして積読をする。常にそんなサイクルを繰り返しています。だから、大学の図書館に籠って本を眺めてみたり、父親の実家の本棚を漁ってみたりと、昔から本がある場所は好きなほうです」
そうやって、本と付かず離れずの微妙な距離感を楽しんでいる彼にとっては、ただパラパラとページをめくるだけでも、クリエイティビティが刺激されるきっかけとなる。
「音楽もそうですが、必ずしも作品全体を好きにならなかったとしても、一行だけでもいいフレーズに出合うことができれば、本を開いた意味があると思っています。僕は歌詞を書く時に、自分の周りにあるいろんな要素をサンプリングしながら繋ぎ合わせていくことが多いのですが、本の中のフレーズや価値観も、歌詞の世界にインスピレーションを与えてくれます」
少年時代をアメリカで過ごした尾崎が手に取る本は、基本的に海外の作家によるものがほとんどだ。英語で書かれたものであれば、英語のまま読む。それが、本の内容を深く理解するうえではとても重要なことだと彼は語る。幼少期から住んでいた街、ボストンを代表する、H・D・ソローの名著『森の生活 ウォールデン』は、高校時代に課題図書として読んで以来、何度も読み返しているお気に入りの一冊だという。
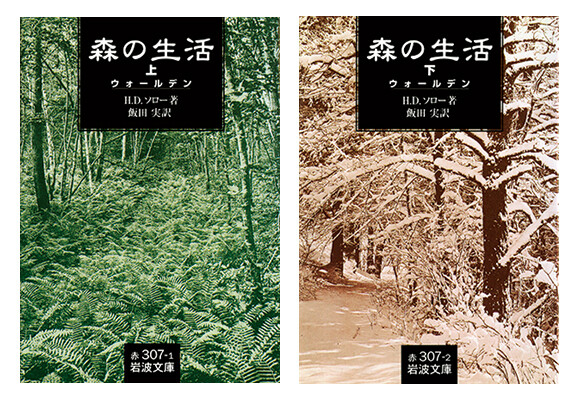
『森の生活 ウォールデン』上・下 1845年の7月4日から、作者がボストンのウォールデン池のほとりに自作の小屋を作り、その中で2年2カ月と2日にわたってひとりで暮らした、自給自足の生活を描いた回想録。自然回帰を通して人間精神、哲学、労働など、あらゆるものごとに思いを巡らせる。生活に必要な最低限のコストを計算してミニマリズムを追求するなど、現代社会に通じる価値観を提唱した。「能動的に他者の知見を学ぼうとする読書は、自分の経験を拡大させてくれる行為だと思います。作中でソローは、ハーバード大学にいた時よりも、山に籠って本を読んでいるほうが、よっぽど勉強になったと語っています」
ヘンリー・デイヴィッド・ソロー著 飯田 実訳 岩波書店刊 上¥924、下¥1,012
「この本は、自分の人生にいちばん大切なことを知るために、世間から隔絶された森の中で、約2年間生活をするという内容ですが、コロナ禍で他人や社会との距離を取るようになり、人生のあり方をあらためて見つめ直す機会が増えた現在の状況と、この本のテーマがぴったりと重なっているように思えるんですよね。美しい自然の中でただひとり、最終的には人と生きることの大切さや喜びに気付かされていくソローの言葉の数々は、会議も飲み会もコンサートも、すべてがオンラインで開催されるようになったいま、誰の胸にも深く染みわたるはずです」
---fadeinpager---
V・E・フランクルの『それでも人生にイエスと言う』は、日本に帰国してから、大学のゼミで輪読をした際に題材として用いたもの。第二次世界大戦下のホロコーストを生き延びたユダヤ系精神科医の著者が、生きる意味について語った一冊だ。

『それでも人生にイエスと言う』 『夜と霧』で世界的なベストセラーを記録し、フロイト、ユング、アドラーらと並び称される、心理学の権威である精神科医のV. E. フランクル。彼が、1946年にウィーンの市民大学で行った3つの講演、「生きる意味と価値」「病を超えて」「人生にイエスと言う」の内容をまとめた一冊。ナチスの強制収容所で過ごした経験を通して、フランクルが導き出した「生きることの意味」。人間の実存を見つめ、精神の尊厳を重視した独自の思想を、一般市民に向けた平易な口調でわかりやすく解説する。「辛い状況に陥り苦悩するすべての人に、人生を肯定する勇気を与えてくれる救いの書です」
V. E. フランクル著 山田邦男・松田美佳訳 春秋社刊 ¥1,870
「本の内容を題材に、他の人と自由に意見を交わす経験をしてから、本を読むことが楽しめるようになりました。『自分が人生に何を期待するのか』ではなくて、『人生が自分に何を期待しているのか』を考えるという発想が、強く印象に残っています。この本も、『森の生活 ウォールデン』も、“いかにして生きるか”という哲学的なテーマですが、約170年前に書かれた前者は個人主義を追求する内容で、後者のベースには世界大戦時の全体主義がある。そして3冊目の『Neo Human ネオ・ヒューマン:究極の自由を得る未来』では、全身が動かなくなる難病を患った科学者が、人類で初めてAIと融合し、サイボーグとして生きる道を選ぶという、近未来的な個人主義が語られています」

『Neo Human ネオ・ヒューマン:究極の自由を得る未来』 AIとの融合は、人類に何をもたらすのか? 年齢、性別、肉体、時間、病、そして死。そのすべてからの解放を目指す科学者ピーター・スコット-モーガンによる、究極の自由を勝ち得るための「人類最大の挑戦」。現在進行形の実話が、既存の哲学や倫理を軽々と超越していく。「いまの価値観では非常識とされることでも、10年後には常識になるかもしれません。いまの技術力では1,000万円するものも、10年後には3,000円になるかもしれません。自分が信じた未来に向けて突き進むためには、ものすごいバイタリティと信念が必要だということを、この本によって思い知らされました」
ピーター・スコット-モーガン著 藤田美菜子訳 東洋経済新報社刊 ¥1,870
---fadeinpager---
大きな時代の流れの中で、個人主義から全体主義、そしてまた個人主義へと戻っていく人間の価値観の変遷を、この3冊から読み取ることができると彼は言う。
「基本的に僕は、何ごとにも“答え”を求める、ある種西洋的な考え方の中で育ってきたから、こういった、大きな問いに向き合う内容の本が好きなんだと思います。でもその半面、作詞表現においては、“キレイ”にまとめることを嫌って、イメージを限定しない抽象表現、もしくはどこか欠け落ちた状態を求めるような傾向もあります。そういったある意味日本的ともいえる感覚を、これからも大事にしていきたいと思っています」
グローバルに生きる若きアーティストは、人生の糧になる価値観や思想を自由にサンプリングしながら、自分だけの答えを探し続けている。その過程で紡ぎ出されていくリリックは、現代を生きる若者たちの、明るい道しるべとなる。
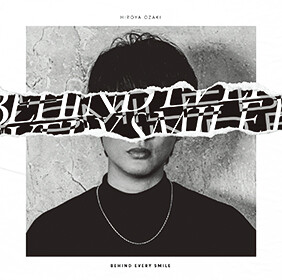
「ビハインド エブリ スマイル」
尾崎裕哉
SME ¥1,600(通常盤)
1stアルバム『Golden Hour』から、約1年ぶりのリリースとなる新作EP。サウンドプロデュースにYaffle、トオミヨウを迎えた新曲4曲を収録。既存のジャンルを超えた自由な表現スタイルは、前作からさらに磨きがかかり、また新たな広がりを見せる。初回盤DVDには、7月に行われたライブから5曲を追加収録。
1989年、東京都生まれ。2歳の時に父である尾崎豊が死去。母とともにアメリカへと渡り、15歳までボストンで暮らす。慶應義塾大学大学院卒。2016年より音楽活動を開始。9月25日から全国ツアー「ONE MAN STAND 2021」がスタート。
スクワット/ルメール tel:03-6384-0237
ソウキ tel:03-6419-7028
*「フィガロジャポン」2021年11月号より抜粋
photography: Masahiro Sambe styling: Nobuyuki Ida hair & makeup: Kosuke Enami interview & text: Shingo Sano









