La boîte à bijoux pour les mots précieux.ーことばの宝石箱 「泣くのならバスの中じゃなく......」フランソワーズ・サガンのスノビズムとは。
Culture 2023.08.03
文筆家・村上香住子が胸をときめかせた言葉を綴る連載「La boîte à bijoux pour les mots précieuxーことばの宝石箱」。今回は彼女とも親交のあった、フランソワーズ・サガンの言葉をご紹介。
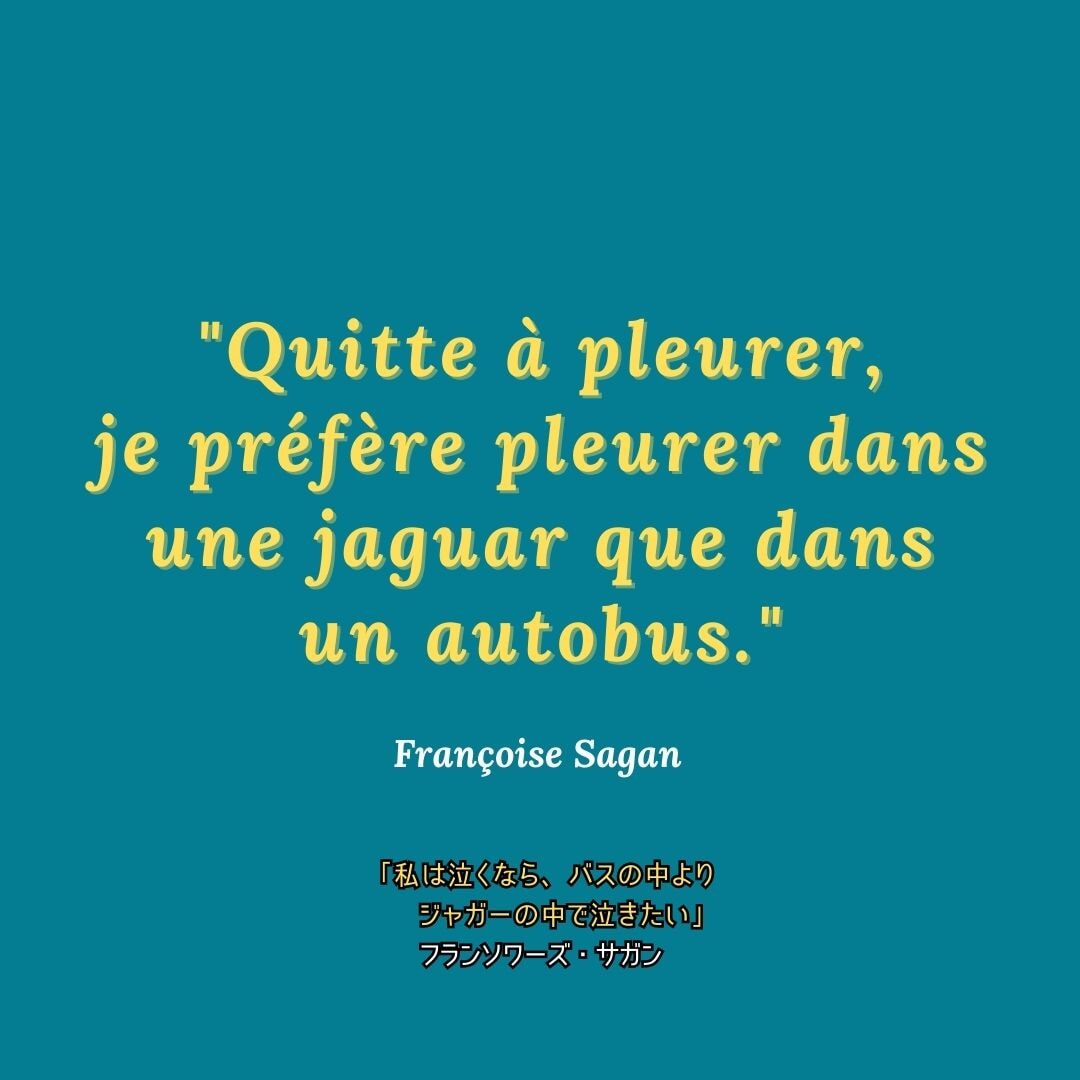
愛車ジャガーで車の事故を起こし、瀕死の重傷を負っても、意識が戻ると「車が大破して駄目になったから、また新しいジャガーを買わなければ」といったというフランソワーズ・サガン。車はジャガーと決めていたようだし、とことんジャガーマニアだった。ポルシェで泣いてもいいところを、私は絶対ジャガーよ、と言っていて、そこにはサガンのこだわりの美学が感じられる。
19歳で書いた小説『悲しみよ、こんにちは』で、世界的なベストセラー作家になり、途方もない印税が入ってきたサガンは、そんな大金をどうしたらいいか分からず、父親に相談すると「そんな泡銭のような金はすぐに使ってしまいなさい」といわれたという。実業家だった父親は、どうやらなかなかの太っ腹な人だったようだ。
マヤ文明でもアステカ文明でも、ジャガー、すなわち豹は力の象徴だし、その豹がいまにも獲物に飛びかかっていきそうなエンブレムの車、ジャガーはいかにもスピード狂のサガンが好みそうだ。シャープな車体が気に入っていたのだろう。
---fadeinpager---
彼女がこのことばを言ったのは1969年、当時はフランスの国道にも華やかな高級車が多く走っていたことだろう。それもパリからリゾート地、サントロペに向かっていたのだから、車に乗っている人たちも相当のおしゃれだったに違いない。
私がパリに住み始め、サガンの家に出入りするようになった80年代後半、彼女は1960年代のその当時のことを、「私がエッフェル塔と同じくらい有名だった頃よ」とユーモアを交えて無造作に語っていた。「だってね、パリに来たら、まずエッフェル塔を見て、それから私に会いに来ていたの。だから家の中には知らない人もいたのよ」
そんな時かもしれない。本当にひとりになれるのは、ジャガーの中だったのかもしれない。車の中だったら、思い切り泣けたのではないだろうか。
余程名女優でない限り、自分の意志で涙を流すのは難しい。それにほとんどは思いがけない場所でついぽろぽろと涙が出てしまうけど、サガンの場合おそらくバスの中でも、メトロの中でもなく、私はジャガーの中でないと泣けない、というところが、スノッブの女王としての貫禄といってもいい。第一彼女はバスやメトロには乗ったことがなかったかもしれない。スノッブはまずスタイルから入っていくので、ジャガーの中で泣いている女、その姿が気に入ったのだろう。
---fadeinpager---
現在私は鎌倉の海辺に住んでいて、黒のポルシェのカブリオレを持っている女友達がいて、それで迎えに来てくれることがある。
そんな時は昔のサントロペを思い出す。するとすっかり周囲もコート・ダジュールに見えてくるようだ。あの頃サントロペのプライベート・クラブ「55」には、すごい車が停まっていたものだ。銀色のバスみたいだったロールスロイスのオープン、フェラーリ、ポルシェ、そしてベンツのオープンも結構素敵だ。海辺では、やはりなんといってもオープンカーが似合う。あの開放感は海辺独特のものだ。帽子は風で飛ばされると分かっていながら、それを手でぎゅっと抑えながら乗っているのが好きだ。あまりフェミニンなものでなく、男物のパナマ帽だと、ぐっとおしゃれにみえるのではないか。
だけど基本的に自分の車の中で泣く、という贅沢には到底及ばない。常に他力本願な私は、いつも他人の車に乗せてもらっているからだ。
スノッブに生きるには、やはり基本的に経済的な支柱がなけばならない、とつくづく。サガンのようなスノッブにはなれないからこそ、彼女の生き方やそのことばに、心惹かれるのかもしれない。

フランソワーズ・サガン
1935年、フランス生まれ。1954年、『悲しみよこんにちは』でデビュー。以降小説、戯曲、随筆など代表作多数。2004年、心臓疾患のため逝去。
フランス文学翻訳の後、1985年に渡仏。20年間、本誌をはじめとする女性誌の特派員として取材、執筆。
フランスで『Et puis après』(Actes Sud刊)が、日本では『パリ・スタイル 大人のパリガイド』(リトルモア刊)が好評発売中。
食べ歩きがなによりも好き!
連載:猫ごころ 巴里ごころ
Instagram: @kasumiko.murakami 、Twitter:@kasumiko_muraka









