ブリジット・バルドー、91歳で逝去。「時代をはるかに先取りした性革命と女性解放のシンボル」
Celebrity 2025.12.28
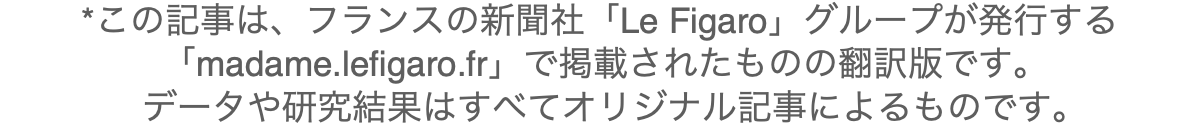
戦後フランスにおいて、ブリジット・バルドーは時代をはるかに先取りした性革命と女性解放を体現していた。彼女のイニシャルであるBBは、生涯を通じて自由を象徴するアイコンだった。彼女は12月28日、91歳で逝去した。

火山よりも熱く、熱狂的で、大胆なマンボに合わせ裸足で踊る。長いブロンドの髪を官能的に撫で、黒いボディスーツと青緑色のスカートを身につけて腰を揺らす。スカートは太ももまでたくし上げられ、細いウエストが露わになる。「人々が踊ることと笑うことしか考えていない国を知っていますか?」と、BBはじっと彼女を見つめる裕福な50代のビジネスマンに言う。時は1956年、彼女は当時の夫ロジェ・ヴァディム監督の映画『素直な悪女』でジュリエット役を演じている。この象徴的なシーンは、サントロペの小さな港町で撮影された。ふくれっ面、威厳のある風格、そして人々の心を掴む夢のような姿に体現された、スキャンダラスな伝説だった。そして12月28日、91歳で彼女はこの世を去った。
ブリジット・バルドーはわずか18歳で、謙虚さや下心など一切なく、戦後の高潔なフランスの常識を覆した。「五月革命」が起きた1968年5月の10年以上も前、彼女はすでに、1970年代に多くの女性が主張することになる「性革命」「女性の解放」そして「心身の自由」を体現していた。彼女は裸足の女神であり、ひとりでも誰とでも踊り、彼女自身の言葉を借りれば「女をイライラさせ、男に刺激を与える」存在だった。
---fadeinpager---
世界に衝撃を与えた身体
1984年、ロジェ・ヴァディムはパリ・マッチ誌に、ある印象的な逸話を語った。彼はロサンゼルスの二大大学のひとつ、南カリフォルニア大学の映画学部でシンポジウムの議長を務めたばかりだった。『素直な悪女』を観た若い学生たちは、ブリジット・バルドー演じるジュリエットのキャラクターの現代性に驚愕しただけでなく、この映画の公開に際し、当時世界中の観客たちが共演者のジャン=ルイ・トランティニャンと不倫関係になったスキャンダルを責め、作品をポルノグラフィだと非難したという事実にも驚嘆した。ヴァディムは学生たちにこう語った。「当時、私たちはエロティシズムに伴う傲慢さとユーモアに慣れていなかった。魅力的な女性であれば、結婚するか公の非難を受けるかのどちらかに値した。性的自由は「レクスプレス」誌やシモーヌ・ド・ボーヴォワールの作品の中で歓迎されていた。善意の有無にかかわらず、知識階級の偽善者、ブルジョワたちは、スクリーンにあふれ出るブリジット・バルドーの快楽に満ちた裸体に抵抗したのだ」
いまではありふれたものに思えるかもしれないこの映画のあるシーンが、すべてを物語っている。それは、バルドーとトランティニャンの結婚初夜のシーンだ。実は、このシーンは昼食時に撮影された。女優はガウン姿で裸足で家族の食卓に現れ、料理の載ったトレーを手に取る。「当時、あんな格好で両親の食卓に現れるなんて想像もできなかった。上映会で受けた衝撃は決して忘れられない」と、1955年の映画『ブリジット・バルドー/恋するレオタード』でバルドーと共演した女優ミレーヌ・ドモンジョは、2021年夏にル・モンド紙に語っている。「そして『素直な悪女』は、登場人物とバルドー自身の人格の境界線が最も鮮明だった作品だ」とヴァディムも述べている。
---fadeinpager---
身体の自由
彼女より前にカメラの前で裸になる女優は他にもいたが、キャリアの初期に彼女がもたらしたのは、大胆で自然なシンプルさ、自発性と陽気さ、屈託のない精神、そして楽観主義であり、戦後の時代には歓迎すべき息抜きだった。パリの高級住宅街のブルジョア家庭に生まれたバルドーは、自分の思い通りに人生を生きることを決してやめたことはなかった。お腹が空いたら食べ、愛し合ったら愛し、気が向いたら行動し、自分の考えをはっきりと口にした。 計算のないフェミニストで解放された彼女は、まさにそれを待ち望んでいた社会にとって触媒としての役割を果たした。彼女は意図せずしてセックスシンボルとなり、何百万もの男性の空想の的となり、同数の苦い女性たちの羨望の的となった。おそらく彼らは、彼女の相次ぐ結婚(ロジェ・ヴァディム、ジャック・シャリエ、ギュンター・ザックス、 ベルナール・ドルマール)と、彼女が惹きつけた情熱と同じぐらい情熱的に彼女を虜にし、次々と愛人(ジャン=ルイ・トランティニャン、ジルベール・ベコー、サシャ・ディステル、サミ・フレイ、 セルジュ・ゲンズブール......)を作ったことを許さなかったのだろう。
バルドーにとって 、セックスは罪と同義ではないのだ。
「ある日、ヴァディムが私の前で、本当に衝撃的なことを言ったんです」と彼女は回想する。「『フランスでは、愛人がいる男性はドン・ファンと呼ばれる。愛人がいる女性は娼婦と呼ばれる』。まるで声が聞こえたかのようでした。そんな考えはきっぱり捨てなければならないと自分に言い聞かせました。そして、私は娼婦にならずとも、女性が男性のような生活を送ることができることを初めて示したのです......。私は、何の意図もなく、女性の自由の象徴となったのです。私は性的自由のおかげで自由な女性なのです」
---fadeinpager---
音色の自由
1975年に映画界を引退し、動物愛護活動に身を捧げた伝説の女優は、1996年に自伝『ブリジット・バルドー自伝 イニシャルはBB』を出版。そこで彼女は仕事での失敗、神経衰弱、屈辱、自殺未遂、そして彼女を執拗に追い回し、人生を阻んだマスコミへの憎悪など、すべてを包み隠さず暴露した。 彼女はいつも通り、気取ったり、慎み深げな態度をとったりすることなく、ありのままの自分を表現した。 元夫のジャック・シャリエを「根っからのブルジョワ」、愛人のひとりを「プレイボーイの嫌な奴」と呼び、ジャンヌ・モローを「野心家で何でもやる」、アラン・ドロンを「ナルシスト」、そしてキャリア初期のカトリーヌ・ドヌーヴを「間抜け」と評した。しかし何よりも、彼女は新たなスキャンダルを巻き起こし、またしても重大なタブー、つまり母親であることを放棄したのだ。
彼女は1960年に息子ニコラスを出産した時のことをこう綴っている。「我が子はまるで体中の腫瘍のようでした......。目が覚めると、まるでお腹にゴム製の湯たんぽを乗せられているような感覚でした。自分の息子だったけど、『ここから出して!』と叫びました。私には母性本能なんてありませんでしたから」。彼女は元夫ジャック・シャリエと息子ニコラスからプライバシー侵害、名誉毀損、中傷で訴えられ、損害賠償を命じられた。後に彼女は、出産時に周囲に巻き起こった集団ヒステリーと、その結果生じたトラウマの矢面に立たされたのは我が子だったと述べている。
ジャーナリストのギユメット・ド・セリニエがマダム・フィガロの長時間インタビューで、バルドーに「母として、そして祖母として......」と尋ねた時、彼女はこう答えた。「私はおばあちゃんなんかじゃない!」
まさに伝説のブリジット・バルドー! 彼女を止めるものは何もなかった。しかし、彼女の過激なスタンスもまた、彼女の伝説の一部である。動物愛護のための闘いを支持するためにとったスタンスは、実際にはさらなる訴訟へと繋がった。「私は何も後悔していません」と彼女は生涯を終えるまで言い続けた。
「良くも悪くも、全ての責任は私が負います。私は常に自由でした」
text: Marion Dupuis (madame.lefigaro.fr)











