JICA Magazine 特別な日の食卓を飾る、世界の「ハレの日」料理を知る。
Travel 2024.03.14
PROMOTION
「食」はその土地の要素をぎゅっと詰め込んだ、いわば国の縮図のようなもの。日常の食卓に並ぶ料理やその材料、調理法などひとつひとつを紐解いてみると、環境や歩んできた歴史、文化、経済、はたまた家庭内における夫婦間のパワーバランスまでも見えてくる。
そんな日常的な「食」を通して、開発途上国のいまとさまざまな課題への取り組みを紹介するのが『JICA Magazine』の連載「今日ナニ食べた?」。この連載で取り上げてきた世界の料理の中から、今回はバングラデシュ、トンガ、ヨルダンにフォーカスし、ちょっと特別な日の食卓を飾る「ハレの日」料理を紹介!
バングラデシュ|港湾都市のごちそうはスパイシーな牛肉料理。

チョットグラムで食べるカラブナがいちばんおいしい! スパイスをたっぷり使って、油で長時間炒める過程で肉が黒ずむその見た目が"黒い炒め物"を意味する「カラブナ」の由来。
バングラデシュ第2の都市チョットグラム(旧名チッタゴン)は、国内最大のチョットグラム港を有する貿易の中心地。古くからイスラム文化が根づく都市であると同時に、歴史的に多様な民族の結節点であったことから、豊かな食文化があります。ヒンドゥー教徒が多数派を占めるお隣のインドとは違って、牛肉を食べる習慣があるのもその特徴です。
代表的な料理のひとつが、"黒い炒め物"を意味する「カラブナ」。その名のとおり黒々とした見た目で、クミンやターメリック、チリ、ニンニク、ショウガなど、たっぷりのスパイスを利効かせて、牛肉を炒め煮にした汁気の少ないカレーです。中までしっかりと味が染みていて、ご飯が進みます。お皿の上でご飯と混ぜながら、手で口に運ぶのが現地流の食べ方。バングラデシュは、肥沃なデルタ地帯での米作が昔から盛んで、白米に合う食文化が発展してきました。一人あたりの白米消費量は日本の3倍以上で、世界1位です。
牛肉は比較的高価なので、カラブナは特別な日のごちそうです。私が初めてカラブナを食べたのは、シップリサイクル産業の現地調査のために、チョットグラムを訪れたときのことです。現地関係者との昼食の際に、名物料理として紹介してもらい、印象に残っています。

地元名物のカラブナを笑顔で紹介する、チョットグラムのシップリサイクル企業関係者。
この「シップリサイクル」とは、老朽化した大型船舶を解体する産業のことで、バングラデシュが世界シェアの約4割を誇ります。解体後のスクラップ鉄はバングラデシュ国内で再利用され、鉄鋼の供給量の約7割を担っており、この国の高度経済成長を支えています。同時に、解体時の有害物質の管理や、労働者の安全確保が国際的に議論されるようになりました。そこで2009年にはそれらに関わる適正なガイドラインを定めた国際条約が日本主導で採択され、バングラデシュもこの条約を23年に批准しました。JICAは、条約に沿った安全・環境面の監督を行う能力強化をサポートするプロジェクトについて、バングラデシュ政府と協議しています。

大型船舶の解体が進められる様子。
さて、そんなバングラデシュ最大の貿易港であるチョットグラム港は、すでに貨物取り扱い可能量の上限を超えており、港湾機能は飽和状態にあります。そこでJICAは、チョットグラム港から約100km南下したマタバリという場所に、新しい港湾を整備開発する事業を円借款で支援しています。さらに、周辺地域の開発にも協力していく予定です。新しい港湾都市マタバリでも、チョットグラムのカラブナのように、地元の名物料理が訪れる人々を魅了する日も遠くないかもしれません。(JICAバングラデシュ事務所 岡本宇弘さん)
---fadeinpager---
トンガ|伝統食材の活用で ヘルシーな食生活を!

左上のバナナ、左下のタロイモの隣3品が「ウム」で、上から「ロイホヌ(亀)」「ロイフェケ(タコ)」「ルーシピ」。生魚の料理「オタイカ」(右上)とムール貝を添えて。
大洋州の国々には、焼いた石の上に葉で包んだ食材を置いて蒸し焼きにする、伝統的な食文化があります。トンガではこの調理法を「ウム」と呼び、タロイモの葉に肉や魚などの具材を入れ、ココナッツミルクを加えて包み焼きにする「ルー」が代表的な料理です。「ルーシピ(羊肉のルー)」「ループアカ(豚肉のルー)」「ルーイカ(魚のルー)」など、バリエーションはさまざま。トンガの主食であるキャッサバなどのイモ類も一緒に蒸し焼きにして食べることが多いです。
手間暇のかかるウムは、トンガでは安息日のごちそう。キリスト教徒の多いこの国では、日曜日は仕事もスポーツもご法度の安息日と定められています。とはいえ、現地の人たちを見ていると、朝早くから起きてウムの準備をし、急いで朝食を食べ、着替えて教会の礼拝に行くといった具合に、安息日といえども意外に忙しそう。近年では、電子レンジやオーブンなどの普及により、ウムは大洋州で徐々に廃れてきているともいわれますが、トンガではこの伝統は健在です。

毎年恒例の農業祭では、地元で採れた農産物がお披露目される。
トンガ人は、『ガリバー旅行記』に出てくる巨人国のモデルになったといわれるほど大柄な人が多いのですが、過去の写真を見ると筋肉質で引き締まった人が多かったのに比べ、現在のトンガは世界有数の肥満大国。その大きな要因は、食生活の変化です。昔はイモ類やココナッツミルク、魚介類を主体とした栄養バランスの取れた食事だったのですが、1980年代後半頃から加工品やファストフード文化が国外から輸入され、急速に普及していきました。コンビーフやフライドチキン、食パンなど、手軽においしいものが食べられるようになり、食卓が様変わりしたのも事実です。今では肥満に加え、糖尿病や高血圧など、NCDs(非感染症疾患)と呼ばれる生活習慣病が、深刻な社会問題になっています。
これまでJICAでは、栄養士や看護師などの協力隊員派遣や、研修員事業などの協力を行ってきました。そのひとつがブレッドフルーツを有効活用する、東京農業大学を中心とした草の根技術協力事業です。ブレッドフルーツは伝統的な主食のひとつで、食物繊維が豊富な健康食材でもありますが、収穫期には食べきれず8割ほどは廃棄されていました。そこで、小麦粉のように使える粉に加工し、その粉でマフィンを作るなど、有効活用を試みています。伝統食材を現代の食卓に生かすこうした取り組みを進めて、トンガの人々の収入向上につなげるとともに、健康維持にも貢献していきたいと思います。(JICAトンガ事務所 新関三保子さん)

JICAの協力により健康的な地元食材ブレッドフルーツを有効活用。
---fadeinpager---
ヨルダン|水不足を解決して、貴重な食文化を守る。

大皿に山盛りのマンサフ! 西部の街カラクはマンサフの本場といわれ、新鮮なジャミードでつくられる味は格別。
中東の国ヨルダンには、炊き込みご飯の「マクルーバ」、ひよこ豆のコロッケ「ファラフェル」など、おいしい料理がたくさんありますが、実は周辺のアラブ諸国をルーツとするものがほとんどです。
そんななか、ヨルダンの伝統料理であり国民食といえるのが「マンサフ」です。新鮮な羊肉をジャミードと呼ばれる羊やヤギの乳を発酵させたヨーグルトとともにホロホロになるまで煮込み、香辛料を入れて炊いた米や薄焼きパンの上にのせてアーモンドやパセリを散らしたら、最後に上からジャミードのソースをかけて食べるのが一般的。コクがありながらも羊臭さはまったくない逸品です。
このマンサフ、アラビア半島に広く住むベドウィンの伝統料理といわれています。砂漠の遊牧民である彼らは、人をもてなすときや祝い事のあるときに、保存食であるジャミードと家畜をさばいた肉を用いてマンサフをつくったといいます。大皿に盛り付けて皆で分け合うため、部族間の争いを緩和する役割も果たしていたそうです。

「ジャミード」は世界最古のヨーグルトといわれている。

ジャミードを溶かした真っ白な煮汁で肉をホロホロになるまで煮込む。
マンサフの材料のもととなる羊の飼育には大量の水が必要なのですが、ヨルダンは今、水不足の問題に直面しています。国土の75%が砂漠でもともと水が少ないうえに、周辺国からの難民受け入れによる人口増加で水の需要が急増し、供給が不足。羊を育て、ジャミードをつくる農家たちは、必要な水を確保するために多くの負担を強いられています。
ヨルダンの国民一人あたりの年間使用可能水量は245㎥といわれています。これは一般的に水不足と定義される基準である年間1,000㎥を大きく下回り、「世界で最初に水が枯渇する国」と指摘されるほどです。とりわけ内戦により多くのシリア難民が流入した北部地域では、衛生状況の悪化を含む、水を巡る諸問題が一気に噴き出し、状況は深刻化しています。
この問題に対しJICAでは、国連機関と連携しながらさまざまな協力を行っています。老朽化した配水管を更新して漏水を削減し、配水管を新設して配水区域を拡大。さらに取水地から標高1,000m近い高地にあるアンマンまで水を運ぶポンプも整備。多くのベドウィンが暮らす南部には水道事業を支援する日本人の専門家を派遣しました。
水不足問題の解決は、そこに住む人々の平和と生活の安定に寄与するのはもちろん、ヨルダンという国の風土が育んだ貴重な食文化を守ることにもつながるのです。(JICAヨルダン事務所 不動田朋浩さん)

新しく設置された水道メーター。これで使用量が視覚化でき、貴重な水の管理が可能に。
---fadeinpager---
連載「今日ナニ食べた?」では、このほかにも世界の食事情とその背景に潜む課題、そして普段知ることのできない途上国でのJICAの活動を紐解いている。
『JICA Magazine』はウェブサイトでオンライン版を無料公開中。さまざまな視点から、世界の開発途上国への理解を深めてみては。
※所属先は取材当時
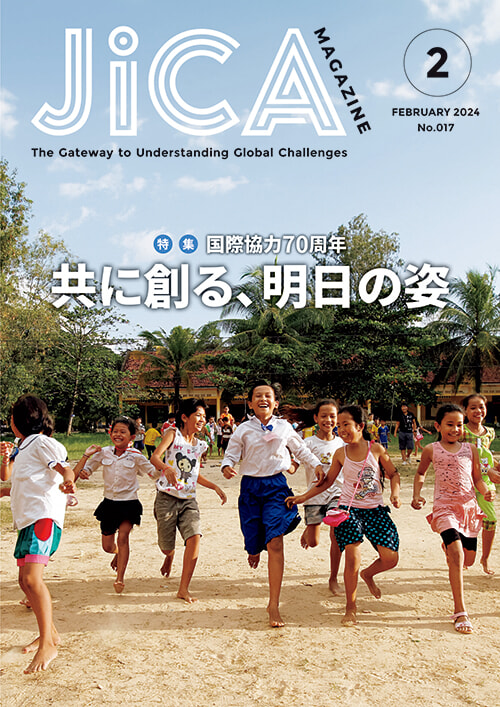
JICA Magazine
https://jicamagazine.jica.go.jp
世界の開発途上国のいまと、現地で活躍する人々の様子をお届けするJICA広報誌『JICA Magazine』。毎号さまざまなテーマに沿った特集、JICAの活動のレポート、連載コンテンツなどが掲載されている。本誌は隔月発行、ウェブサイトでは過去のアーカイブ記事も閲覧可能。









