
フェルメールを生んだ17世紀のオランダ☆
パリの1枚。

パリ?ボーヌ?ボルドー?東京?どこで撮ったのか思い出せないノエルなウィンドー。
Dans un rêve(夢中、夢の中)♡
*******
先日の原田マハさんによるヨハネス・フェルメールについての講演会「フェルメールとは誰か 画家の視点・小説家の視点」に続き、ドイツ文学者で西洋文化史家、翻訳家の中野京子さんのトークイベント「17世紀オランダとフェルメール」を拝聴してきました。
(関連ブログ→ https://madamefigaro.jp/paris/blog/keico/post-946.html )
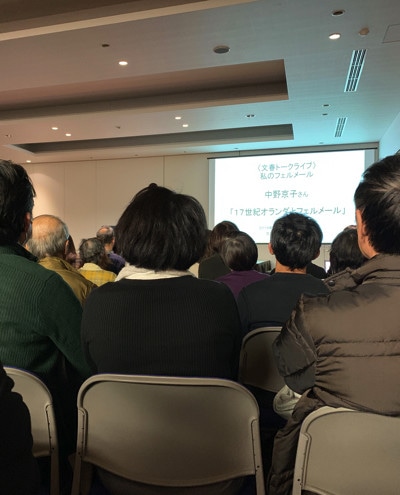
今回の講演も文藝春秋社主催。
中野京子先生の作品も大好きで、ほぼほぼ読んでいる私としてはトーク後のサイン会も楽しみに出かけました。(サイン会撮影禁止)
1時間半、大変興味深いお話を伺って、オランダ絵画に対して、フェルメールに対して、そして何よりオランダという国に対して興味が増しました!
フランスから、パリから案外近いのですね〜。

講演内容は長くなりますのでここで全ては語れませんが、一部の紹介された作品とNetherlands Tourism公式サイトの画像(←長崎ハウステンボスじゃないよ…)とともに。
ヤーコプ・ファン・ロイスダール「風車」(↓)

知ってましたか?(知りませんでしたよ!)純粋な「風景画」は17世紀のオランダで生まれたのです。(アジアには古くからありました)
とにかく空が広い、そして雲がドラマチック。
オランダのシンボル的な風車が描かれてますが、風車は「干拓」のためのもの。
土地が低く狭いオランダにとっては干拓はとてもとても重要で、風車の風景は愛すべきもの。

そんな干拓の苦労と絵画好きな国民性からこんな言葉があるそうです、
「人間は神が作った。オランダはオランダ人が作った。」
「オランダ人は生れながらに皆画家。」
余談ですが、ここ10年でオランダは北欧を抜いて世界一の長身国になったそう。
その理由は色々研究される中で、一説は成長ホルモンを与えた家畜のお肉を食べていたからだと?!(びっくり)

メインデルト・ホッベマ「ミッデルハルニスの並木道」(↓)
こちらも空が広く、典型的遠近法で描かれたポプラ並木道。
ポプラの葉と枝はトップしか残さないのは下の用水路を護るため。(なんとも実務的…)

そもそも並木道は、お城や教会に続く道で王侯貴族たちの為のもの。19世紀に至っても王侯貴族の支配する他のヨーロッパ諸国では一般庶民が通るのは時間帯が制約されていたそう。
でもこのオランダの並木道は市が作ったもので、一般庶民が普通に通ることが可能でした。
17世紀のヨーロッパと言えば、ハプスブルク家、ブルボン家、スチュワート家などをはじめ各国は絶対君主制の世界。そんな中でオランダは、スペイン・ハプスブルク家から独立後、絶対君主不在、王侯貴族なしで商人国家として発展し、プロテスタント的実利主義の社会を形成したところが他のヨーロッパと大違いだったのです。

ガチガチの社会的階級がなく、稼いだ人がそれなりに豊かに暮らせるあたり、どこかの国に似てませんか?
一億総中流と感じる国民意識を持った日本(かつて?)です。
国土の狭さは、山がちな国で鉱物資源の自給率が低いどこかの国に似てませんか?
日本です。
海洋国家だったり、宗教に比較的寛容であったりする点も日本との共通点だそう。

レンブラントの「テュルプ博士の解剖学講義」(↓)
レンブラントの出世作とも言われる集団肖像画。
これまでの肖像画とは違い、それぞれが動きのあるポーズの肖像画は斬新。
しかも集団なので費用は「割り勘」。

そう、割り勘といえばオランダ!?
英語でも“go Dutch”と言う表現あるけれど、オランダには古くから割り勘習慣ありました。
ところでこの絵は外科医の解剖学講義のシーンなのですが、この時代の外科医は医師としての地位は低く、理髪師さんと同カテゴリーだったそう。
なぜなら人の肌にじかに触れる職業はなんというか、そう偉くはないお仕事。(これまたびっくり)
そんな彼らが自分たちの地位向上のために割り勘で依頼したのがこのような集団肖像画なのだそう。
(自信の表れ?レンブラントのサインが作品の真ん中に)

講義をしているチュルプ博士はチューリップ好きが高じて、自ら「チュルプ」に改名したお方…。(ちょっと笑える)
そんなチュルプ博士からもすぐに連想できるのが、オランダと言えば!なチューリップ。

ヤン・ブリューゲル 「チューリップバブル」(↓)
世界史でもお馴染みのオランダのチューリップバブル。
ヤン・ブリューゲルは、そのバブルの経済的混乱を人を猿に置き換えて見事に表現。

当時そのバブルとは、どんなものだったのか?というと、
大工さんの年収が250ギルダ、中流商人が1,500ギルダ、もう売れっ子画家だったレンブラントの代表作「夜警」が1,600ギルダに対して、バブル期絶頂のチューリップ球根が(何と!)1個5,200ギルダ…!
「今がお買い得!」とばかりに勧めるお猿さん。細かく見ていくとこの絵にはバブルの悲喜交々が描かれています。

どんな花が咲くかもわからぬ球根、そもそもは数百ギルダぐらいだった球根の値がこんなに釣り上がるなんて、想像を絶するバブルです。
バブルが崩壊する前に売り抜けた人は儲けただろうけど、最後は…。ババ抜き的なバブルって怖い。

対になっていると言われるハブリエル・メツー「手紙を書く男」(↓)
甘いマスクで画中画にヤギ=好色が描かれることからも、この男がモテ男で女性好きなことが推察されます。

そんな男性からの手紙を受け取ったのが、もう一方のハブリエル・メツーの「手紙を読む女」(↓)
女中さんがめくった画中画は、嵐の航海=この恋は波乱万丈、やめとけ…な感じです。
ところで、ちょっと違和感があるのは女性の額の広さ。
これは当時のトレンドで、額をやや剃り上げることで顔のパーツが下に集まるように見せる=童顔、若々しいに近づけるためだったそう。。

このように画中画はわかりやすいメッセージや教訓として示されることが多い中、フェルメールの絵はそうではなく、なかなか謎めいていて、解釈も色々。
今回来日している「牛乳を注ぐ女」を見てみましょー。
ミルクを注いでいるにも関わらず、音のない静寂感、微妙な光加減が素晴らしい一枚。

ちなみに絵画の中で窓が左に描かれることが多い理由は、画家が右利きだから。
当時の女中さんの仕事にはセクハラ事情込みだったそう…。
そんなことからことから、ミルクツボは女性器、ミルクは男性のアレを表現している!?なんて説もあるそうで。(私にはどうにもこじつけに思えるけれど)

「真珠の首飾りの女」についても単にネックレスをつけているシーンではなく、これは「受胎告知」シーンと唱える人も。
なぜなら、ネックレスをつけるにしては鏡の位置遠く、視線も遠い。
何より広げた手の形は、多くに見られるマリア様の受胎告知の驚きと慎み深いジェスチャーにそっくりでしょ、と。
なのでもしかしてプロテスタントだったフェルメールはカトリックに改宗してたんじゃ…な説も。

いかようにも解釈できる、のりしろが広いところがフェルメール作品の魅力の1つだと改めて知った講演会でした。
そして小さな国でありながら、圧政をはねのけ干拓という努力を重ね、経済発展を遂げて海外進出、ほかのヨーロッパにない文化を築いた歴史を持つオランダ、知れば知るほどにユニークで、革新的且つ合理主義、質実剛健、倹約思考な国だと。

日本と重なる部分も多い反面、全く異なる部分も合わせ持っているらしいので日本人としては共感とそうでない部分の共通点と相違点が面白そう。
この秋にフェルメール展に行ったことをきっかけに、原田マハさん、中野先生のお話から興味関心がうんと増したチューリップと風車のネーデルランドです。
ARCHIVE
MONTHLY









