奇才チリー・ゴンザレス、最新作『Solo PianoⅡ』について語る①
Music Sketch 2012.08.16
大ヒットしたピアノ小品集『Solo Piano』(2004年)以降も、多岐にわたる活躍をしてきた奇才チリー・ゴンザレス。そして今夏、待望のピアノ小品集の続編となる『Solo PianoⅡ』をリリースすることになった(日本は8月22日発売)。2年前、『Ivory Tower』発表後にコンサート来日した際にインタビュー記事を掲載したが、今回は電話取材を行うことができたので、発売に少し先駆けてご紹介したい。曲作りやピアノという楽器についての魅力など、短い時間ながら、チリー・ゴンザレスは饒舌に語ってくれた。
「僕はアルバムのために曲を書くということはあまりしない。音楽を書いて、それがその時やっているプロジェクトにちょうど合う時もあるし、プロジェクトとプロジェクトの間の時期だったら、まだ音楽を探索中で、それがどのように発展するのかわからないという時もある。音楽を書いてそれが何かに発展する時もあるし、発展しなかったら僕の頭の中から消えていく。また、ピアノを弾くたびに戻ってくる音楽というのもある。そういうのは記憶に留めておくんだ。そういう音楽は、ファイスト向けの音楽にはならないし、ボーイズ・ノイズとのコラボレーションにも使われない。ピアノ上でのみ存在する音だからだ。それ以上は何も求めてこない。僕は大量の音楽を作る。それは何も大それたこととして捉えていない。毎日やるようにしているし、毎朝、起きて朝食を取って、トイレに行くというような日常の一部なんだ。その方が、一定の時期にプレッシャーを感じるということがないからね。音楽はそういう日常のなかで徐々に形成されていき、数ヵ月、数週間、集中力がある時は数日間で完成する。"よし、このアルバムのために曲を作ろう!"と言って曲を作り始めることはほとんどないんだ」
----そうなんですね。
「アルバムを作るということが決まっていたら、多少そのアルバムに向けて集中することはあるが、それ以外の場合は、特に何の為か決まっていないが、毎日音楽を作るよ。そのうちのほとんどは二度と演奏することはない。たまに、繰り返し僕の手に戻ってくるメロディが幾つかある。キャッチーだったり、感情に触れるようなメロディだったり、ね。そういうものは、僕は何かしらの意味があるんだと思って、徐々に発展させていく。完成するまでに数カ月かかる時もあるが、ある瞬間に何の努力もなしにその曲が完成されていたりする。もともとそのメロディをいつ、思いついたのかは全く覚えていないんだけどね。100個の小さなメロディがあったというのは、短いものばかりで、10秒のものもあればコードが幾つか弾いただけというのもあった。そのメロディをどのピアノで発見したかというのは大抵の場合覚えている。"ツアー中にミラノのテレビ局でピアノを弾いた時だ"とか"サウンドチェックの時にこの部分を思い付いた"とかね」
----凄い記憶力ですね! 『Solo Piano』はスケッチを思わせるような素晴らしいメロディが詩的に演奏されているようで、とても好きでした。そのスタイルには、どこかエリック・サティを彷彿させるような部分もありました。個人的な感覚ですが、『Solo PianoⅡ』ではスケッチというより、どの楽曲も小品として完成している気がしました。チリーさんとしては、今回の『Solo PianoⅡ』に対して意識した部分(たとえば選曲やテイストなど)はありますか?
「『Solo Piano』から8年が経過して、僕は自分の得意とするピアノ演奏の専門性をさらに高めていった。『Solo Piano』はピアノを再発見する喜びという感じのアルバムだったが、偶然の産物ともいえる作品だ。当時の僕のピアノ演奏はベストなコンディションではなかったから、多少単純な作品だったと思う。だから単純さが作品に表れている。それ以降の8年間、僕は、ピアノを自分の時代の楽器にするという夢に向かって励んできた。毎年、少なくとも100回はパフォーマンスをして、それを8年間続けてきた。だから今では、達成しようとしていることの範囲がより広く、大きくなった」
----そうなんですね。
「だから今回の楽曲は、君の言う通り、スケッチではなく、よりまとまりのある、完成された楽曲になっていると思う。ファーストアルバムにあった極めて高い親密性というものをスタート地点として、そこからさらに先へ進みたかった。このアルバムは『Solo Piano』が終了した地点から始まっているが、『Solo Piano』よりもポップな要素や、『Ivory Tower』の一面でもあったミニマル音楽のような近代的な影響も含んでいる。単純さを装うことは不可能だ。僕はもう単純ではない。僕はすでに、ピアノを大きく、深く人々の心に刻みつけるという道を歩んでいる。だから単純さを装うことはもうできないんだ。できるのは、『Solo Piano』の終了地点から、その先へと進んでいくということなんだ」
「抽象的なテーマを決めて曲を書くということはしない。僕は音楽的な材料と、ピアノを弾く相手を元に音楽制作をする。例えば、僕のコンサートで出会う人達などだ。具体的な誰、というのではなくて、どんな人達で普段何を聴いているのか、などを考える。僕は、ヴィジュアル的な要素を音楽的に解釈する、というような作業はあまりしない。映画、絵画、小説などにインスパイアされて音楽を創ることもない。自分がピアノを弾いている時に生じる音楽的材料にインスパイアされることが多い。自分が初めてピアノを弾く瞬間などに、何か発見がある。タイトルは自分がピアノを弾いている"手"を見て思いつく場合が多い。だけど抽象的世界や詩的世界には、あまり入っていかないな」
----というのは?
「僕が考えているのは、人々や、人々に感情を伝達すること、そしてその人達が、曲の中に存在するコントラストに対して共感してくれるのを期待している。曲には、大きな音と小さな音や、長調と短調、ピアノの上の部分と下の部分、というようなコントラストが絶対に存在する。その両方を行き来することにより、感情的なコントラストが生まれる。例えば、暗いものと明るいもの。人々はそういう概念に共感すると思う。複雑な感情で、まるでその2つが同時に存在していると感じることが誰にでもあるからだ。その2つはお互い競い合っていて、どちらの方が自分の真の感情で、どちらの方が悪の囁きなのか、わからない時がある。心理的や精神的な状況を音楽で描写しているんだ。音楽は感情を描写するもので、船(物)や色は描写しない。感情を非常にストレートに描写するものだ。僕は、ピアノの前に座り音楽を聴くと、描写したい感情を発見することができるんだ」
「曲のタイトルは、僕が音楽を覚えておけるようにその場ですぐに決めることが多いね。だから曲の音楽的材料と関連するタイトルを付ける。例えば『Othello』はスチールドラム演奏者のオセロ・モリノウ(Othello Molineaux)からきている。僕の右手の部分がスチールドラムみたいだと思ったから。すると『Othello』と自分のノートに書くんだ、後でそれがどの曲かすぐにわかるようにね。そんな感じでタイトルを決めているよ」
----一種の記号のようなものですね?
「でも、時にはタイトルを即座に決めてしまい、後になってそのタイトルが嫌になることもあるよ。馬鹿げたタイトルの時もあるからね(笑)。『Kenaston』という曲はもともと『ブライアン・フェリー』〔注釈:元ロキシー・ミュージックのヴォーカリスト。現在ソロで活躍中〕という名前を付けていた。でも、『ブライアン・フェリー』という名前の曲なんて欲しくなかった。曲自体もブライアン・フェリーにインスパイアされたというわけでもなかったし、だけど、曲が完成した時にブライアン・フェリーと呼んでしまったんだ。その後、時間をかけて、この曲が自分にとってどんな感情的意味合いがあるのかということを模索して『Kenaston』というタイトルを付けた。『Kenaston』は僕が子どもの頃に住んでいた通りの名前なんだ。ノスタルジックで子どもっぽい雰囲気の楽曲だからこのタイトルにした。だから、最終的にタイトルのついた曲が出来上がっても、もともとのタイトルを使うのは半分程度だ。『Escher』なんかはそのまま使った。『Othello』もそう。とっさに付けたタイトルだが、後になっても曲としっくりくる。それ以外のものは、タイトルが曲に合わなくなってしまったり、ダサすぎるタイトルだと感じてしまうことが多いね」
----今回のアルバムで、他に曲名を後から変えたものはありますか?
「例えば、『Quietly』というタイトルの曲があって、そのタイトル自体は悪くないと思うんだけど、ピアノ演奏者なら誰でも『Quietly』という曲が作れそうだなと思った。それよりはもう少し特別なのを作りたいと思って、『Epigram in E』という名前にした。名前の響きがEやIをたくさん含んでいて気に入ったし、『Quietly』と呼んでしまっても素敵だと思うけど、それならリチャード・クレイダーマンの曲にもありそうだと思ったんだ。曲のタイトルには個性を持ってほしい。僕のユーモアのセンスを人々に思い出してもらうのは、タイトルという部分だと思った。今回のアルバムでは、僕のユーモアのセンスを全面に出していないけど、例えば『Evolving Doors』というタイトルを見ると、ゴンザレス流ユーモアが垣間見えてくるよ〔注釈:Evolving doors(=進化ドア)はRevolving doors(回転ドア)をもじった冗談〕。普段ならクレイジーなステージパフォーマンスをやったりラップしたりして、そのユーモアは表現できるけど、今回のアルバムでは音楽的な部分かタイトルにユーモアが存在しているんだ」
続きは次回に。
 今年で40歳となるチリー・ゴンザレス。© 2012 Alexandre Isard Gentle Threat All right reserved
今年で40歳となるチリー・ゴンザレス。© 2012 Alexandre Isard Gentle Threat All right reserved
「僕はアルバムのために曲を書くということはあまりしない。音楽を書いて、それがその時やっているプロジェクトにちょうど合う時もあるし、プロジェクトとプロジェクトの間の時期だったら、まだ音楽を探索中で、それがどのように発展するのかわからないという時もある。音楽を書いてそれが何かに発展する時もあるし、発展しなかったら僕の頭の中から消えていく。また、ピアノを弾くたびに戻ってくる音楽というのもある。そういうのは記憶に留めておくんだ。そういう音楽は、ファイスト向けの音楽にはならないし、ボーイズ・ノイズとのコラボレーションにも使われない。ピアノ上でのみ存在する音だからだ。それ以上は何も求めてこない。僕は大量の音楽を作る。それは何も大それたこととして捉えていない。毎日やるようにしているし、毎朝、起きて朝食を取って、トイレに行くというような日常の一部なんだ。その方が、一定の時期にプレッシャーを感じるということがないからね。音楽はそういう日常のなかで徐々に形成されていき、数ヵ月、数週間、集中力がある時は数日間で完成する。"よし、このアルバムのために曲を作ろう!"と言って曲を作り始めることはほとんどないんだ」
----そうなんですね。
「アルバムを作るということが決まっていたら、多少そのアルバムに向けて集中することはあるが、それ以外の場合は、特に何の為か決まっていないが、毎日音楽を作るよ。そのうちのほとんどは二度と演奏することはない。たまに、繰り返し僕の手に戻ってくるメロディが幾つかある。キャッチーだったり、感情に触れるようなメロディだったり、ね。そういうものは、僕は何かしらの意味があるんだと思って、徐々に発展させていく。完成するまでに数カ月かかる時もあるが、ある瞬間に何の努力もなしにその曲が完成されていたりする。もともとそのメロディをいつ、思いついたのかは全く覚えていないんだけどね。100個の小さなメロディがあったというのは、短いものばかりで、10秒のものもあればコードが幾つか弾いただけというのもあった。そのメロディをどのピアノで発見したかというのは大抵の場合覚えている。"ツアー中にミラノのテレビ局でピアノを弾いた時だ"とか"サウンドチェックの時にこの部分を思い付いた"とかね」
----凄い記憶力ですね! 『Solo Piano』はスケッチを思わせるような素晴らしいメロディが詩的に演奏されているようで、とても好きでした。そのスタイルには、どこかエリック・サティを彷彿させるような部分もありました。個人的な感覚ですが、『Solo PianoⅡ』ではスケッチというより、どの楽曲も小品として完成している気がしました。チリーさんとしては、今回の『Solo PianoⅡ』に対して意識した部分(たとえば選曲やテイストなど)はありますか?
「『Solo Piano』から8年が経過して、僕は自分の得意とするピアノ演奏の専門性をさらに高めていった。『Solo Piano』はピアノを再発見する喜びという感じのアルバムだったが、偶然の産物ともいえる作品だ。当時の僕のピアノ演奏はベストなコンディションではなかったから、多少単純な作品だったと思う。だから単純さが作品に表れている。それ以降の8年間、僕は、ピアノを自分の時代の楽器にするという夢に向かって励んできた。毎年、少なくとも100回はパフォーマンスをして、それを8年間続けてきた。だから今では、達成しようとしていることの範囲がより広く、大きくなった」
----そうなんですね。
「だから今回の楽曲は、君の言う通り、スケッチではなく、よりまとまりのある、完成された楽曲になっていると思う。ファーストアルバムにあった極めて高い親密性というものをスタート地点として、そこからさらに先へ進みたかった。このアルバムは『Solo Piano』が終了した地点から始まっているが、『Solo Piano』よりもポップな要素や、『Ivory Tower』の一面でもあったミニマル音楽のような近代的な影響も含んでいる。単純さを装うことは不可能だ。僕はもう単純ではない。僕はすでに、ピアノを大きく、深く人々の心に刻みつけるという道を歩んでいる。だから単純さを装うことはもうできないんだ。できるのは、『Solo Piano』の終了地点から、その先へと進んでいくということなんだ」
OTHELLO from SOLO PIANO II. Presented in PIANOVISION from Chilly Gonzales on Vimeo.
『Solo PianoⅡ』の収録曲から「Othello」 ----演奏している時は、到達すべき情景を思い浮かべているのでしょうか? それとも、自分の中の情感を解き放ってリリースしていく感じなのでしょうか? テーマを決めて書いている、演奏していることもあるのですか?「抽象的なテーマを決めて曲を書くということはしない。僕は音楽的な材料と、ピアノを弾く相手を元に音楽制作をする。例えば、僕のコンサートで出会う人達などだ。具体的な誰、というのではなくて、どんな人達で普段何を聴いているのか、などを考える。僕は、ヴィジュアル的な要素を音楽的に解釈する、というような作業はあまりしない。映画、絵画、小説などにインスパイアされて音楽を創ることもない。自分がピアノを弾いている時に生じる音楽的材料にインスパイアされることが多い。自分が初めてピアノを弾く瞬間などに、何か発見がある。タイトルは自分がピアノを弾いている"手"を見て思いつく場合が多い。だけど抽象的世界や詩的世界には、あまり入っていかないな」
----というのは?
「僕が考えているのは、人々や、人々に感情を伝達すること、そしてその人達が、曲の中に存在するコントラストに対して共感してくれるのを期待している。曲には、大きな音と小さな音や、長調と短調、ピアノの上の部分と下の部分、というようなコントラストが絶対に存在する。その両方を行き来することにより、感情的なコントラストが生まれる。例えば、暗いものと明るいもの。人々はそういう概念に共感すると思う。複雑な感情で、まるでその2つが同時に存在していると感じることが誰にでもあるからだ。その2つはお互い競い合っていて、どちらの方が自分の真の感情で、どちらの方が悪の囁きなのか、わからない時がある。心理的や精神的な状況を音楽で描写しているんだ。音楽は感情を描写するもので、船(物)や色は描写しない。感情を非常にストレートに描写するものだ。僕は、ピアノの前に座り音楽を聴くと、描写したい感情を発見することができるんだ」
KENASTON from SOLO PIANO II from Chilly Gonzales on Vimeo.
『Solo PianoⅡ』の収録曲から「Kenaston」 ----では、曲のタイトルはどのようにして、どのタイミングで決めるのですか?「曲のタイトルは、僕が音楽を覚えておけるようにその場ですぐに決めることが多いね。だから曲の音楽的材料と関連するタイトルを付ける。例えば『Othello』はスチールドラム演奏者のオセロ・モリノウ(Othello Molineaux)からきている。僕の右手の部分がスチールドラムみたいだと思ったから。すると『Othello』と自分のノートに書くんだ、後でそれがどの曲かすぐにわかるようにね。そんな感じでタイトルを決めているよ」
----一種の記号のようなものですね?
「でも、時にはタイトルを即座に決めてしまい、後になってそのタイトルが嫌になることもあるよ。馬鹿げたタイトルの時もあるからね(笑)。『Kenaston』という曲はもともと『ブライアン・フェリー』〔注釈:元ロキシー・ミュージックのヴォーカリスト。現在ソロで活躍中〕という名前を付けていた。でも、『ブライアン・フェリー』という名前の曲なんて欲しくなかった。曲自体もブライアン・フェリーにインスパイアされたというわけでもなかったし、だけど、曲が完成した時にブライアン・フェリーと呼んでしまったんだ。その後、時間をかけて、この曲が自分にとってどんな感情的意味合いがあるのかということを模索して『Kenaston』というタイトルを付けた。『Kenaston』は僕が子どもの頃に住んでいた通りの名前なんだ。ノスタルジックで子どもっぽい雰囲気の楽曲だからこのタイトルにした。だから、最終的にタイトルのついた曲が出来上がっても、もともとのタイトルを使うのは半分程度だ。『Escher』なんかはそのまま使った。『Othello』もそう。とっさに付けたタイトルだが、後になっても曲としっくりくる。それ以外のものは、タイトルが曲に合わなくなってしまったり、ダサすぎるタイトルだと感じてしまうことが多いね」
----今回のアルバムで、他に曲名を後から変えたものはありますか?
「例えば、『Quietly』というタイトルの曲があって、そのタイトル自体は悪くないと思うんだけど、ピアノ演奏者なら誰でも『Quietly』という曲が作れそうだなと思った。それよりはもう少し特別なのを作りたいと思って、『Epigram in E』という名前にした。名前の響きがEやIをたくさん含んでいて気に入ったし、『Quietly』と呼んでしまっても素敵だと思うけど、それならリチャード・クレイダーマンの曲にもありそうだと思ったんだ。曲のタイトルには個性を持ってほしい。僕のユーモアのセンスを人々に思い出してもらうのは、タイトルという部分だと思った。今回のアルバムでは、僕のユーモアのセンスを全面に出していないけど、例えば『Evolving Doors』というタイトルを見ると、ゴンザレス流ユーモアが垣間見えてくるよ〔注釈:Evolving doors(=進化ドア)はRevolving doors(回転ドア)をもじった冗談〕。普段ならクレイジーなステージパフォーマンスをやったりラップしたりして、そのユーモアは表現できるけど、今回のアルバムでは音楽的な部分かタイトルにユーモアが存在しているんだ」
続きは次回に。
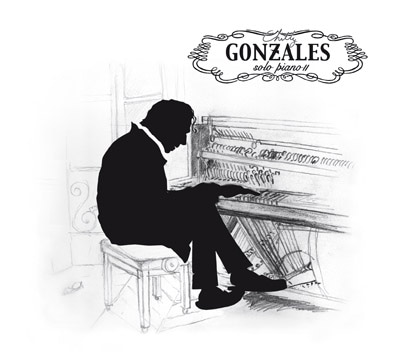 チリー・ゴンザレスの最新作『Solo PianoⅡ』。珠玉のピアノ小品を日本盤は全15曲収録。 8月22日発売。
チリー・ゴンザレスの最新作『Solo PianoⅡ』。珠玉のピアノ小品を日本盤は全15曲収録。 8月22日発売。

音楽&映画ジャーナリスト/編集者
これまで『フィガロジャポン』やモード誌などで取材、対談、原稿執筆、書籍の編集を担当。CD解説原稿や、選曲・番組構成、イベントや音楽プロデュースなども。また、デヴィッド・ボウイ、マドンナ、ビョーク、レディオヘッドはじめ、国内外のアーティストに多数取材。日本ポピュラー音楽学会会員。
ブログ:MUSIC DIARY 24/7
連載:Music Sketch
X:@natsumiitoh
BRAND SPECIAL
Ranking









