新作『ザ・ザ・コルダのフェニキア計画』の公開が近い、ウェス・アンダーソン監督。そのユニークなカメラワーク、作り込まれた構図や色彩は唯一無二で、いちど見たら忘れがたい。あの魅力的な世界を創るのに重要な人物が、実はドイツ、ベルリンにいるという。その名は、ジーモン・ヴァイセ。10年来ウェス・アンダーソン監督作品の小道具やジオラマを作っているミニチュア工房を率いる。

photography: Gianni Plescia
ヴァイセ工房は、大通りの奥にあるガレージの一角に隠れていた。重たい鉄の扉が開き、招き入れられた空間には、小さな作業台が並び、壁には町並みのジオラマや人形などが所狭しと並んでいる。キッチンのカウンターには、救急箱の隣に映画『ザ・ザ・コルダのフェニキア計画』で重要な役割を果たす手榴弾が、さりげなく置かれていた。

photography: Gianni Plescia
南仏、モンペリエでアートを学んだヴァイセ氏は、スチールフォトグラファーだった父について、偶然映画の世界に足を踏み入れた。小道具や特殊効果の部署で働くようになったヴァイセ氏が、初めてミニチュアを作ったのは1988年、テリー・ギリアム監督の映画『バロン』でのことだ。しかしその後、1990年代前半CGが始まり、何でもかんでもCGを使い、わざわざお金や時間をかけてミニチュアを作る必要はないという風潮が広まったのだという。
「しかしCGで本当にいいシーンを作るには案外お金も手間もかかる。いままた、多くの若い映画監督たちがアナログでしか実現できない世界の魅力を再発見しているように思います」とヴァイセ氏は言う。


©Atelier Simon Weisse
その筆頭がウェス・アンダーソン監督だ。
彼とアンダーソン監督の出会いは2014年のこと。ベルリンの映画スタジオで『グランド・ブダペスト・ホテル』を撮影していた監督が、ドイツに誰か伝統的なミニチュアを作ることができる職人はいないか?と尋ねたことがきっかけだった。
映画『グランド・ブタペスト・ホテル』を観たことがある人なら、幕開けの山頂に立つピンク色のホテル、そしてその入口までガタゴトと上がっていくケーブルカーのシーンをよく覚えているだろう。あのホテルが、ヴァイセ氏がアンダーソン監督のために作った初めてのミニチュアだったのだ。
「ミニチュアと言っても幅4メートル、高さは2メートルもの大きなもの。ケーブルカーを斜めに走らせるのが難しくて苦戦しました。結局カメラの方を傾けて、斜めに走っているように見せているんですよ。」

©Atelier Simon Weisse
アンダーソン監督はほかの監督と違い、構図やイメージ、どういうふうに物語を見せるのかが全シーンきっちりと決まっている。彼のストーリーボードはなんとアニメーション動画なのだ。
「カメラの位置も決まっているので、極端なパースをつけて作ったりもします。画面のなかでは水平線の彼方まで続く長い線路......に見えるけど、実際は30センチくらいしかなかったりね」
(このシーンはNetflix『ヘンリー・シュガーのワンダフルな物語』で配信中!)
最近ではアンダーソン監督以外でも、ミニチュアにしかできない表現をと、オファーが来る。最近ではルカ・グァダニーノ監督の『クィア/QUEER』は、夢のような世界がヴァイセ氏が作ったミニチュアの街並みでビジュアライズされた。
最近は忙しすぎて、実際の制作よりもプロデューサーとの話し合いや、多くの職人たちの指揮を取る方が多くなっているのがちょっと寂しいと語るヴァイセ氏。作ったモデルは撮影現場に搬入されてしまったら、もう彼の手元に戻ることはない。場合によっては壊されてしまうこともある。

©Atelier Simon Weisse
「でもアンダーソン監督は巨大な倉庫を持っていて、保存しておいてくれているのがうれしいです。今年はアーカイブの展覧会が企画されており、パリやロンドンなんかを巡回するんですよ!」
9月からは、次の大きなプロジェクトに向けての作業に取り掛かるという。まだなんの映画かは秘密だというが、かなり大掛かりなもののようだ。まずは、『ザ・ザ・コルダのフェニキア計画』で、ヴァイセ工房で作られた小道具やミニチュア、模型がきらりと光るアンダーソン監督の世界を、じっくりと堪能したい。

©Atelier Simon Weisse
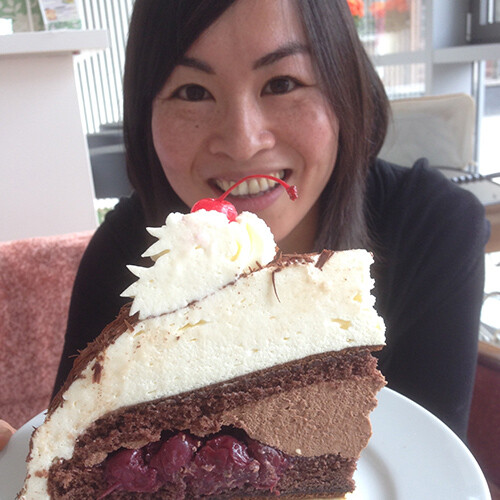
河内秀子
ライター。2000年からベルリン在住。ベルリン芸術大学在学中に、雑誌ペンなど日本のメディアでライター活動を始める。好物はフォークが刺さったケーキ、旧東ドイツ、マンガ、猫。ドイツでも日本でも「そとのひと」。 twitter:@berlinbau










