朝井リョウと清水奈緒美、 コロナ禍で読んだ本について語る!
Culture 2021.10.21
作家の朝井リョウとスタイリストの清水奈緒美。プライベートでも親交が深い読書家のふたりに、2020年4月の緊急事態宣言下から現在までに読んだ本について話を聞いた。
――おふたりの出会いについて教えてください。
朝井 インタビューなどでメディアに出る時、着る洋服をずっと気にしていなかったのですが、友人で小説家の柚木麻子さんが「私は友だちに選んでもらっているよ」「とても素敵な人だよ」と紹介してくださったのが清水奈緒美さんでした。3人で服をたくさん買いに行ったのがきっかけです。ちなみに今日着ているこのシャツも、そのとき選んでもらったやつ。お話ししてみると、食べ物の趣味や、これを食べたいと思ったときの執着の度合いが似ているなと感じて、ここ数年は「これを食べました」という謎報告を送り合ったりしています。
清水 知り合ってすぐ、私の好きなプロレスにお誘いしたんです。それもお互いを知るきっかけだったかなと。かなりアンダーグラウンドな団体のものだったのですが、朝井さんならきっと楽しんでくださるという謎の確信がありました。
朝井 それが人生初のプロレス観戦だったのですが、その団体の名前をプロレス好きの小説家の西加奈子さんに話したら、「何で、人生で初めてがそれなん!?」と驚かれました。プロレス好きな西さんでさえ、段階を踏んでから行こうと思っていた団体らしいです。あと清水さんはほかの誰も観ていない映画を映画館で観ていたりするからおもしろいです。こうやってちゃんと本の話をするのは、今日が初めてかも。
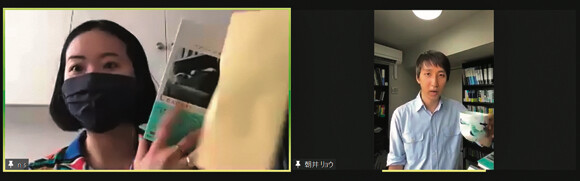
――2020年から現在にいたるまで何を感じ、どんな本を手に取られましたか。
朝井 人との接触が減って半年も経ってくると、目的はないんだけど人と何かをしゃべっていたいという、言語化しづらい寂しさ、孤独というのを感じるようになりました。で、2020年の秋頃から、孤独をもっとカジュアルに扱う、と決めたんです。これまでの人生であまりやってこなかった長電話などをするようになって、孤独や寂しさってもっとカジュアルに扱ってもよかったんだ、と気付きました。私にとっては大きな発見。
清水 スタイリストは基本的に対面でないと成立しない仕事なので、去年の4月から5月にかけてずっと、自宅で過ごしていました。次の仕事が徐々に始まるまでのその期間は、フリーランスになって初めて、働かずに部屋に籠もっていた時間でした。そもそもインドアなタイプですが、自らの意志ではなく強制的に部屋にいなければいけない状況にストレスを感じました。生産的なことが何もできなくなり、一日がどんどん短くなっていきました。そんな中で、普段まめに連絡を取らないけど心は近くに感じるような方たちに、「どう過ごしていますか?」とそっと尋ねてみたり。緊急事態宣言というきっかけがなければ連絡することもなかったと思うので、自分では思いがけない変化でした。私が住んでいる場所はいわゆる繁華街なのですが、街から人々が誰もいなくなって、一時期はまるでゴーストタウンのようでした。
朝井 全然違う世界になった感じがしましたよね。普段は何も感じなかったのに、決まった時間に流れる区の放送を聞いて、初めての種類の怖さを感じたり。私は1回目の緊急事態宣言の時に、『となり町戦争』を思い出して、読み返しました。戦争というと、いわゆる空襲のような光景をイメージすると思うんですけど、この本で描かれている世界では、普通に暮らしているのに、自分の全然知らないところで確実に戦争が進んでいるんです。町内報に日々、増えていく死者が記録されていく。主人公が町役場の人間として見えない戦争に関わっていく話なのですが、すごくいまの状況と似ているなと。ウイルスは目に見えないのに、感染者数は右肩上がり。でも、行こうと思えば、おいしいパンケーキとかは食べに行ける状況。緊急事態宣言という字面と並行して、スーパーに買い物に行ける日常がある。そんなギャップを受け止めてくれたのがこの本でした。
ある日、突然に始まった隣接する町同士の戦争。公共事業として戦争が遂行され、見えない死者は増え続ける。現代の戦争の狂気を描く傑作。第17回小説すばる新人賞受賞作品。
三崎亜記著 集英社刊 ¥704
---fadeinpager---
清水 何もできないまま一日を過ごしているうちに、途中から時間の流れが速く過ぎるようになって。時の概念がここまで変わるのかと不思議に感じていました。そんな時に、『モモ』を読み返してハッとしました。いまの状況にリンクするような本を読むとそこだけにとらわれてしまいそうな気がして、好みの本をひたすら読みました。籠もるしかない生活の中で、自分のもともとの「好き」をふと見つめ直したくなったのでしょうか。学生の時によく読んでいた本を読んだり、あらためて触れることで平静を保つという感じでした。小説を好きになるきっかけとなった、『彼岸先生』も何年振りかに読み返しました。ずっと好きな作家である倉橋由美子さんの『暗い旅』もあらためて読みました。恋人を突然失った主人公が、当てもなく彼を探して旅に出る話です。大事な人の喪失を描いた小説が好きで、最初に読んだ学生の当時、この本の心情にかなり影響を受けた記憶があります。大人になったいま読み返すと、随分ナルシスティックな少女小説で、それでもちっとも嫌になれず、何だか幼かった当時をリアルに思い出して気恥ずかしくもなりました。いまでもやはり私にとって大事な一冊です。
時間に追われ、人間本来の生き方を忘れてしまっている現代の人々に、風変わりな少女モモが時間の真の意味を気付かせてくれる。1974年ドイツ児童文学賞受賞作品。
ミヒャエル・エンデ著 大島かおり訳 岩波書店刊 ¥1,870
『彼岸先生』
不思議な恋愛小説を書いている小説家の先生は川の向こう岸に住んでいる。ロシア語を学ぶ19歳のぼくと37歳の先生の奇妙な師弟関係を描いた平成『こころ』。泉鏡花文学賞受賞作。
島田雅彦著 新潮社刊 ¥692
『暗い旅』
恋人であり婚約者である“かれ”の突然の謎の失踪。“あなた”は失われた愛を求めて、過去への暗い旅に出る。壮大なる恋愛叙事詩として文学史に残る、倉橋由美子の初の長編作品。
倉橋由美子著 河出書房新社刊 ¥770
――創作活動において、何か変わったことはありますか。
朝井 単純なことでいうと、小説を書く時にコロナがある世界を舞台にするのか、書き手は皆一度悩んだと思います。時代時代をそれぞれの目線で切り取っていくという仕事なのに、この現実をないものとして、自分にとって都合のいいフィクションを書き続けていくのかと私も悩みました。そういう時、私は度々、谷崎潤一郎のことを思い出すんです。当時の戦時下で小説を書き続けるって想像することも難しいのですが、世の中の動乱の中、書くことで自分の世界を守り抜いたのかなと思ったりもするんです。あらためて『春琴抄』を読み直したんですが、谷崎にとって外の世界なんて関係なかったんじゃないだろうかと思わせる強さがあるというか。でももしかしたら、世の中が大変な中、こんな自分の興味関心に基づいたことばかり書いてていいのかという葛藤があったかもしれない。戦争があった頃に小説を書いていた人たちのことを思うと、5年や10年のスパンで物事を考えてもどうにもならなくて、その時に何を書いたかという意義や価値は100年や200年経ってみないとわからないこともあるんじゃないかと考えさせられます。いまの社会の状況の中で小説家として何を書くべきか、みたいなことに悩みすぎた時は、趣味全開! みたいな作家の本を読みたくなります。
9歳の頃に眼病で失明した全盲の三味線奏者である春琴と、彼女に献身的に使える丁稚の佐助の愛の物語。被虐趣味を突き抜け、思考と官能が融合する美の陶酔の世界を繰り広げる。
谷崎潤一郎著 新潮社刊 ¥407
---fadeinpager---
清水 今後書いていきたいテーマを伺わせてください。
朝井 いまは男性同士のコミュニケーションに興味があります。コロナ禍で人との関わりが減る中で、そもそも大人の男性って、理由もなく誰かに電話をかけたりランチをしたりっていうコミュニケーションが少ないな、と。目的がないと会わない習性というか。雑談も下手なんです。女性は、友だちとの電話もランチもカジュアルにこなすイメージ。
清水 確かに。私、吉野家や松屋は男性にとってのカフェみたいなものなのかと思っています(笑)。
朝井 ほんとだ!(笑) 会話もいらないですしね。男性同士って何で年齢を重ねるほど雑談が下手になるんだろうってずっと思っていて。だから、コミュニケーションのハードルを下げるような男性同士の関係性を書いてみたいなと思っています。私からすると、女性は男性に比べて繋がりを求めることに恥ずかしさや照れを感じていないように見えて、羨ましいんです。私ももっと友だちと甘いもの食べに行ったりしたい。そんな中、最近読んだのがこちら。『パフェが一番エラい。』っていう本です。
東大卒、日本で唯一のパフェ評論家である斧屋(おのや)がディープに語る、見てうっとり、読んで深まるパフェ本の決定版。人生が華やぐパフェの世界を、より楽しむための指南書。
斧屋著 ホーム社刊 ¥1,980
清水 何というタイトル! 読みたいです!
朝井 今日絶対これ清水さんに薦めようと思ってました! いろんな思索に富んだコラムが載っているんですが、どんな入口のコラムでも出口が必ずパフェなんです。そして最後にそのパフェの写真が載っている。読みながら、自由に動き回れるようになったらどれを食べに行こう、とワクワクしました。
清水 パフェを気兼ねなく食べられた日常が恋しい……。
朝井 あと、金原ひとみさんの……
清水 『アンソーシャル ディスタンス』ですね! 私も今日の対談でぜひ挙げられたらと思っていた一冊です。
パンデミックに閉塞する世の中で、生への希望だったバンドのライブ中止を知った時、ふたりは心中することを決めた。いま追い詰められている人々の叫びが響きわたる。P51でも紹介。
金原ひとみ著 新潮社刊 ¥1,870
朝井 コロナのことも出てくるんですけど、コロナに影響されて生まれた小説ではないと感じられるくらい、文章が濃厚! 世間の渦がちっぽけなものに感じられるくらい、描かれる人間の心の渦が巨大。時速500キロくらいで文字が爆走していくイメージ。実はコロナに関係なく存在する人間の心の禍々しさが、キリッと屹立していますよね。コロナはあくまでそのスパイスとして存在している感覚で。金原さんは、ある種、現代の谷崎潤一郎だと感じました。同時代にいろんなものが同時に存在し、混在している健全さに触れられる本だな、と。
---fadeinpager---
清水 私は仕事において美しいものを創ることに関わっていますが、美しさは元来、清濁併せもったものだと思うんです。ファッションは、その裏にいろいろな表層があって成り立っていて、まったく単純ではない。もともと物事を多面的に見るようにしているのですが、コロナ禍で起きている普通ではない変化や混乱を、仕事や日常、そして自身の中にどう受け入れていくのか、反映させていくのか、さらに考えるようになりました。
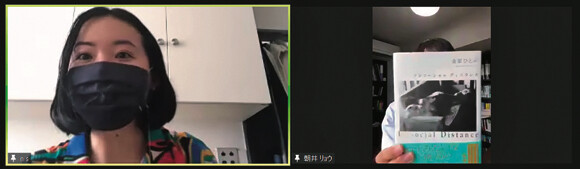
――コロナ禍で、新しく出合った本はありますか?
朝井 私は人生で初めて、この手の本に興味を持って読んでみました。『シリーズ人体 遺伝子 健康長寿、容姿、才能まで秘密を解明! 』 『一万年の進化爆発 文明が進化を加速した』 『性淘汰 ヒトは動物の性から何を学べるのか』。ウイルスが変異して、人間が攻撃され続けるというこの状況の中で、人類の進化とか、生物学的観点から見た人間みたいなものを知りたくなったんです。読み終わって感じたのは、多様な人間がいるからこそ、人類は生き延びているということ。全人類が、ある種の理想的で健康的な生活をしていたとすれば、ひとつのウイルスに淘汰されてしまうかもしれないけれど、実際はあらゆる環境で生きる多様な人間がいるから、人類という種が絶滅しないで済んでいる。そう考えると、多様性という言葉の持つ意味が、これまでの百倍くらい巨大に感じられました。
「人体の設計図」遺伝子の秘密が驚異のスピードで解明される。これまでの常識が180度変わる最先端の研究報告を世界各地に取材し、まとめた一冊。
NHKスペシャル「人体」取材班編 講談社刊 ¥1,760
『一万年の進化爆発 文明が進化を加速した』
人類の生物学的進化は4~5万年前に終わったという従来の学説を否定して、1万年ほど前から人類の進化が加速していると論じた本。人類の進化の新しいイメージが語られている。
グレゴリー・コクラン、ヘンリー・ハーペンディング著 古川奈々子訳 日経BP刊 ¥2,420
『性淘汰 ヒトは動物の性から何を学べるのか』
進化と行動生態学の視点から読み解く配偶システム、性行動、つがい外交尾、オーガズム、同性愛……、常識を覆す動物の性行動の数々を掘り下げる。
マーリーン・ズック著 佐藤恵子訳 白揚社刊 ¥3,850
清水 朝井さんの新刊『正欲』にも多様性というワードが出てきますが、また思いがけない多様性の側面ですね。興味深いです。私がコロナ禍に出合って衝撃を受けたのは、遠野遥さんの『破局』。まさにこういうのが読みたかった……、と脳に電撃が走った作品です。近年追いかけたい作家がいなくて寂しく思っていたのですが、どっぷりとはまってしまいました。最新作の『教育』が、文藝2021年秋季号に掲載されているのですが、もったいなくて実はまだ読めていません。好きな作家の新作が読めるのは至上の喜びだと思っています。遅く取る予定の夏休みで、じっくり読みたいと思います。
平成生まれの小説家。2009年、『桐島、部活やめるってよ』(集英社刊)で第22回小説すばる新人賞を受賞しデビュー、同作が映画化。13年に『何者』(新潮社刊)で第148回直木賞を受賞。作家生活10周年記念の書き下ろし長編小説『正欲』(新潮社刊)が発売中。
ファッション誌の編集者を経て、2010年よりスタイリストとして活動。モード誌を中心に、CM、アーティストなどのスタイリングを手がける。
*「フィガロジャポン」2021年11月号より抜粋
interview & text: Hioka









