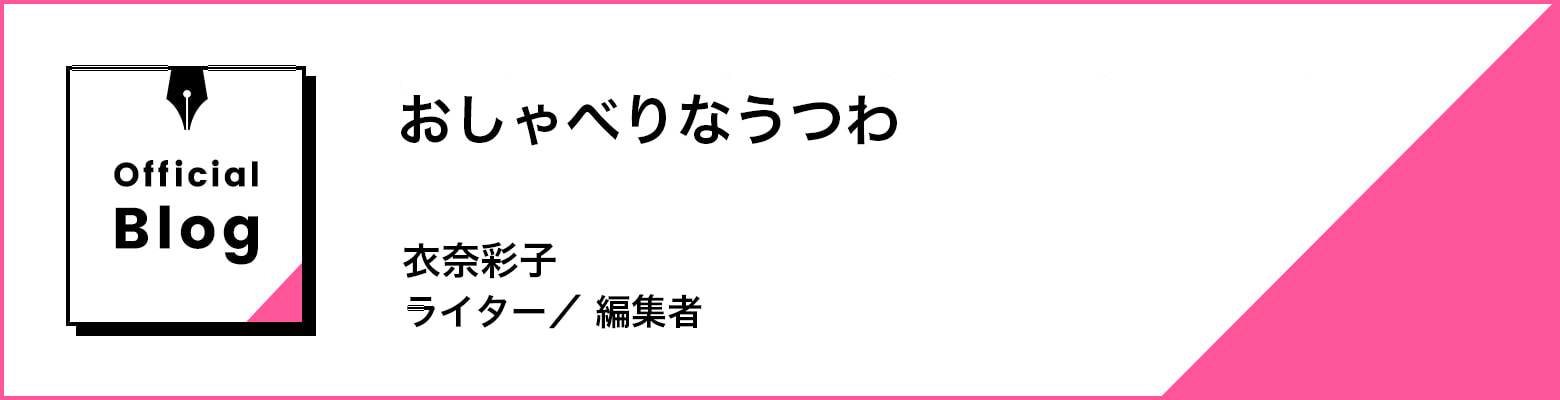
白という色の広がりを知る、広瀬陽さんのうつわたち。

これは、広瀬陽さんの七宝のうつわ。
七宝というと、博物館や寺院に収蔵された壺、香炉、装身具、イコンなどに見られる絢爛豪華な極彩色のものを思い浮かべる人が大半だと思う。しかし広瀬さんのそれは、白一色(もしくは、赤や黒一色)。なぜ? 七宝焼とは、金属にガラス質の釉薬を焼き付けて装飾する技法をいい、加飾の工程で金属に直接華やかな色をのせても綺麗に発色しないため、一面に白い釉薬をかけ、いわば色をのせるためのキャンバスを作るという。釉薬は粉状で金属面に振りかけたときに厚みやムラがでてしまうことがあるのだけれど、その不均等な白が、広瀬さんにはとても魅力的に見えたというのだ。(詳しくは、うつわディクショナリー#49 古物のような佇まい、広瀬陽さんの七宝のうつわ)。
うつわの表面を注意深く見ると、ムラや青みなど変化に富んでいて愛おしい白。穴あきのプレートとフリルの小皿、円柱の蓋物を愛用しているけれど、銅の板をひたすら叩いて成形する鍛金の技法をおもに用いて、硬い金属をこれほどやわらかなフォルムに落としこんでしまう広瀬さんの技術と形へのこだわりが、七宝をこれまでにない新しい工芸に仕立てている。
とはいえ金属なので、道具として存分に使い倒してやるのが私の使命。穴あきのストレイナーは、中国茶の茶盤に見立てたり、野菜の水切りに使ったり、フリルの小皿は、フルーツや深夜のおやつに、塩昆布がのることさえある。生活のいろいろなところで活躍中。

林拓児さんの石皿にちょうどぴったりで思いがけず中国茶用の茶盤になった。急須は三笘修さん。

ただの天ぷらがちょっと素敵になるわけです。

金属とは思えないやわらかなフリルに感銘を受けて。私、これ眺めながら一杯呑めます。

普段はここにいます。

作り手:広瀬陽
年代:2019年、2024年
購入場所:白日
ARCHIVE
MONTHLY












