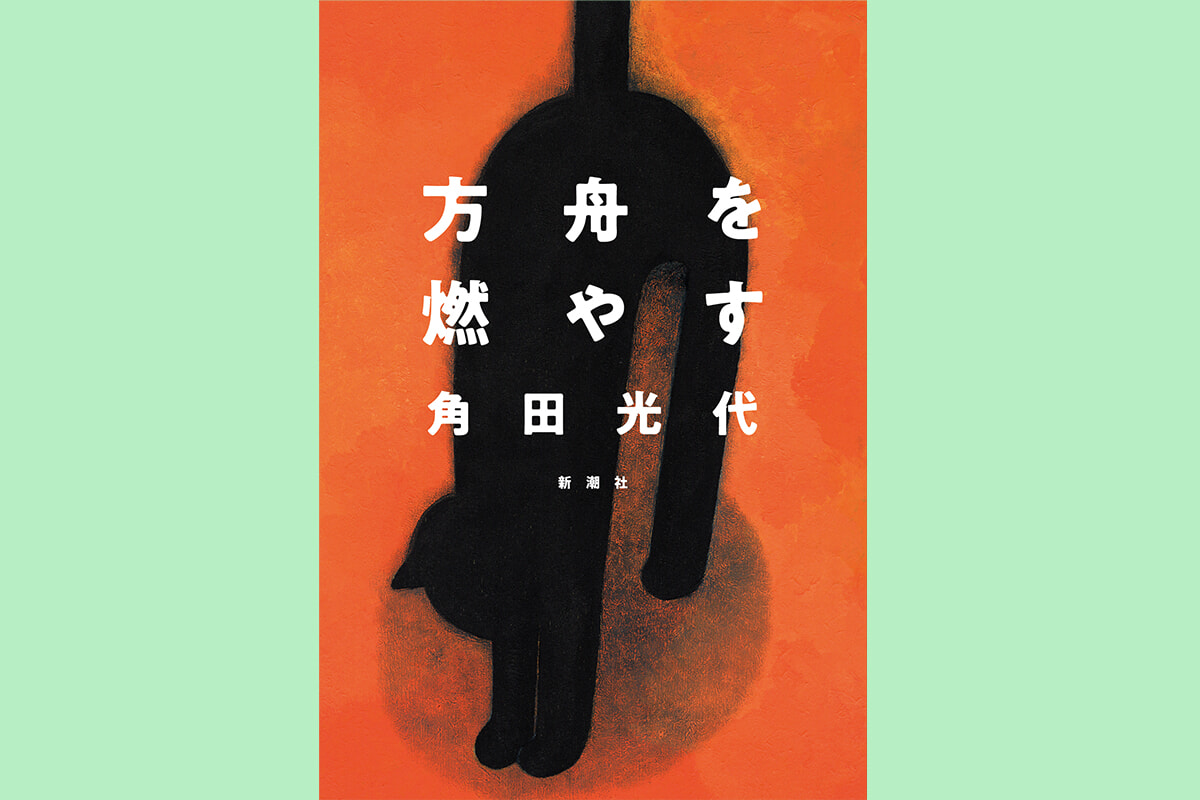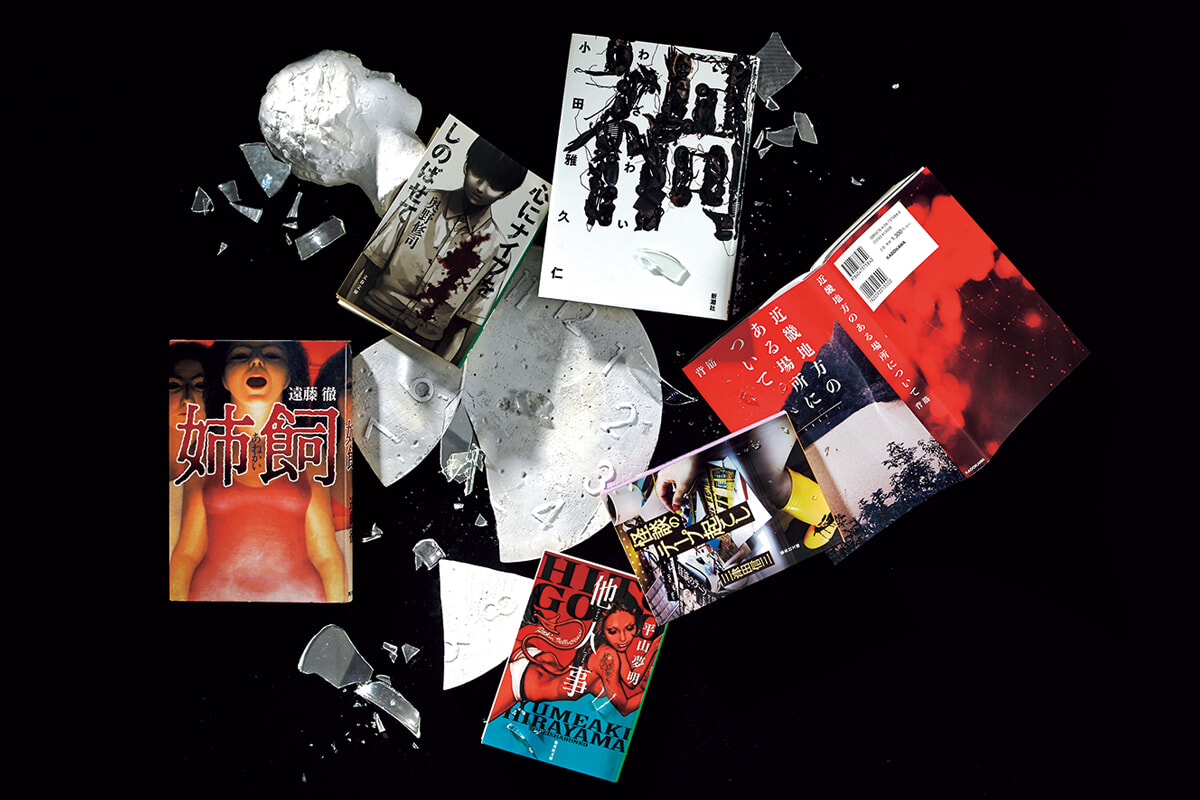角田光代が「ひとり旅のおとも」に選ぶ6冊の本。【いま知りたいことを、本の中に見つける vol.5】
Culture 2025.08.21
知りたい、深めたい、共感したい──私たちのそんな欲求にこたえる本を26テーマ別に紹介。各テーマの選者を手がけた賢者の言葉から、世界が変わって見えてくる贅沢な読書体験へ!
vol.5は「ひとり旅のおともに」をテーマに、作家・角田光代が選んだ6冊を紹介。ふと読み返した時、ひとり旅の記憶が本とリンクし、かけがえのない一冊になるかもしれない。
選者:角田光代(作家)
ひとり旅のおともに。
ひとり旅にはかならず本を持っていきます。たいてい、その旅先が舞台の小説やエッセイを選びますが、ぴったりのものが見つからない場合は、「旅」を描いた作品を選びます。今回選んだ六冊は、ミランダ・ジュライ以外、みな旅に取り憑かれた作家たちの作品になりました。ミランダ・ジュライの一冊は、旅ではないけれど、でも、旅を強く想起させるドキュメンタリーです。それぞれの作家にとって旅とはなんなのか。それぞれの作家と会話しながら旅ができると思います。旅を終えて帰ってきたとき、実際に目にした光景と、作家の描いた光景が混じり合っていることがあって、そのささやかなカオスも、私の旅の一部です。

1. 『アジア無銭旅行』
金子光晴著 角川春樹事務所刊 ¥1,100
金子光晴の描く旅の光景は本当にすごい。自然も人も、生々しくて色彩にあふれています。私は若き日に、この本を貪るように読みながら旅したのですが、いまだに、書かれた異国の光景と、私の旅の光景が、ごっちゃになって記憶に残っています。旅しながら、詩人が目にした、約百年前の旅の光景も、ともに味わうという、贅沢ができます。
2. 『林芙美子紀行集
下駄で歩いた巴里』
立松和平編 岩波文庫 ¥880
二十七歳のとき、列車を乗り継いでパリまでいった林芙美子は、元祖バックパッカーだと思っています。異国が、住むことで自分のテリトリーになり、そうするとまた移動したくなる、旅に取り憑かれた作家の日々。この作家が切り取る、人ばかりでなく、もの、風景、空、空気、季節、旅での一期一会のいとしさは、私たちのすべての旅にもあてはまります。
>>Amazonでの購入はこちら
3. 『あなたを選んでくれるもの』
ミランダ・ジュライ著 岸本佐知子訳 新潮社刊 ¥3,080
旅をすることとは、常識の外に出ること、「私」という狭苦しい檻からの脱出だと私は思っています。この本はまさに、常識の外に広がる世界そのものが登場します。あるフリーペーパーの「売買広告」に品物を出す人たちを著者が訪ねてインタビューするという作品ですが、こんなにも人は多様で、孤独で、ゆたかなのかと思い知らされます。この人間たちの奥深さこそ、世界の広さのように思います。
>>Amazonでの購入はこちら
4. 『われらの時代・男だけの世界
─ ヘミングウェイ全短編 1 ─』
ヘミングウェイ著 高見浩訳 新潮文庫 ¥990
旅を愛した作家が、初期に書いた短編小説集。簡潔で平易な言葉で、光景と人生の一部を切り取る技に感服します。人生は旅だというのは、気の利いたたとえでもなんでもなく、事実なんだと思わされます。旅は、あるいは人生は、ときに過酷で理不尽ですが、時代を選べずに生まれてきた私たちは、それをただ受け入れるしかない。ひとり旅にはとてもふさわしい一冊のように思います。
>>Amazonでの購入はこちら
5. 『ブローティガン 東京日記』
リチャード・ブローティガン著 福間健二訳 平凡社刊 ¥1,430
一九七六年、詩人は一か月半、東京に滞在し、目にしたもの、感じたことを、詩にしています。どこまでもちいさなもの、弱いものに目線を合わせる繊細な詩人が見る東京は、私にとっては再発見の東京でした。詩人の言葉は、私たちのひとり旅にも寄り添って、ものの見かたやおもしろがりかたや、忘れたくない記憶の保存方法を、そっと教えてくれる気がします。
6. 『ロマネ・コンティ・一九三五年』
開高健著 文春文庫 ¥715
開高健の文章は非常に凝っていて、忙しい日常だとなかなか読み進められないことがあるけれど、旅のさなか、とくに日本語の聞こえてこない異国の旅だと、こってりした作家の言葉がするする入ってきます。旅を愛し、人間を嫌いつつ愛したこの作家の、世界を見つめる目線の鋭さが、異国ならばするりと理解できる(ように思えます)。短編小説の持つ余韻に打ちのめされる一冊です。
>>Amazonでの購入はこちら
1967年、神奈川県生まれ。90年『幸福な遊戯』(角川文庫)で海燕新人文学賞を受賞しデビュー。近著に『晴れの日散歩』(新潮文庫)、『韓国ドラマ沼にハマってみたら』(筑摩書房刊)などがある。
紹介した商品を購入すると、売上の一部が madameFIGARO.jpに還元されることがあります。
*「フィガロジャポン」2025年9月号より抜粋