「管理しない、故に我あり」 昇進を拒む30代が生み出す、新たなワークスタイルとは?
Society & Business 2025.08.18
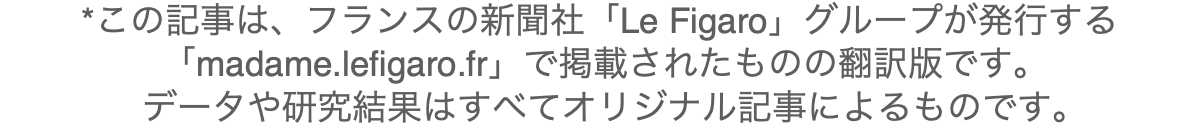
昇進して管理職になることを拒む若い世代がこれまでの企業の常識を覆し、新たなライフワークバランスを問いかける。

「人を雇いたいと思っている?」
出版社を経営する30歳のヴィクトワールにそう聞くと吹き出した。
「絶対にイヤ! 自分で会社を立ち上げたけれど、誰も雇いたくない。業務量も仕事内容も、ひとりで回せるように考えた」
最近、「コンシャス・アンボッシング(conscious unbossing)」、すなわち、管理職になることを敬遠する風潮が25〜35歳の間で広がりつつある。そのことは数字にも表れている。ロバート・ウォルターズ社の2024年調査によれば、30歳未満の若手社員の2人に1人は管理職になりたくないと思っている。さらに衝撃的なのは、この年齢層の16%が、なんらかの管理業務を伴う立場なんてまっぴらと思っていることだ。
コスパが悪い。
そう思うのも理由がある。まずは彼らが目の当たりにしている現実だ。管理職は24時間メール対応に追われ、相矛盾する目標と上層部からの圧力に翻弄されて疲弊している。
「いろいろな上司がいたわ。毒上司、細かすぎる上司、なにもしない上司......だからリーダーシップやマネージメントに良いイメージはまったくない」とヴィクトワールは言う。
そして彼女自身、一度は管理する側になったものの「うまくいかなかった」そうだ。
「責任が伴い、時間もエネルギーも適応力もすごく必要で疲れ果てた。そのまま我慢し続けるには自由を求める気持ちが強すぎた」
---fadeinpager---
こうした計算をするのは彼女だけではない。ますます多くの若者が勤務時間や費やすエネルギー、求められる創意工夫等の企業への貢献と、その見返りに受け取る報酬、評価、ワークライフバランスをさっと天秤にかけている。
ロバート・ウォルターズ社の調査によれば、若い世代の69%は、得られるメリットと比べて仕事の負担や制約が大きすぎると考えている。つまり、いくら給料が良くても個人的な犠牲が伴うならば見合わないと思っているのだ。
31歳のロミーは幼児2人の母親だ。フランスの大手銀行の営業職として働いていたが、業務量を減らして自分の時間を増やすために同業他社のスイスの銀行へ転職、プライベートバンカーのアシスタントとなった。
「これが私の選択。いまのところ出世には興味がない。ちゃんと暮らしていけるだけ稼げれば、あとは子どもたちとの時間を増やす方が大事」と語る。
大切なのは自分
「この世代が気まぐれなのではありません。ポリクライシス時代に対応した結果なのです」と語るのは、IESEG経営大学院の教授であり、『Z世代のマネジメント』(Dunod刊)の著者でもあるエロディ・ジャンティナだ。
「若い世代は責任そのものを拒否しているわけではありません。個人の犠牲を出世の前提とするピラミッド型組織に組み込まれることを拒んでいるのです。ライフワークバランスを守れるのならば違う形で責任を取ってもいいと考えています」
若い世代が信奉するのは効率、(働く時間や場所等の)柔軟性、自律性。今も影響が残るパンデミックの副産物と言ってもいい。フランス国立工芸院の社会学者、マエルジグ・ビギは、次のように語る。
「コロナ禍は人々の考えを大きく変えました。在宅勤務が導入された影響が大きい。ですが、それもいまでは平均週2日まで縮小されています。管理職たちは出社方式に戻って元のように働こうとしましたが、もう遅かった。任される自由を味わった若い世代は後戻りしたくないのです」
---fadeinpager---
理想主義だと批判されようと、この世代は常に対応や過剰生産性が求められるシステムに歯向かおうとしている。旧来の働き方に戻ろうとする動きに対して、25-35歳が出した答えは重心を変え、自分の人生を中心に据えることだった。
31歳のジャンヌはパリ在住のフリーランスフォトグラファー。彼女はまさにそのように生きている。いまの仕事が気に入っているのは「報酬もいいし自分で自分の時間を管理できる」からだ。「働くのは人生を充実させるため」と言う彼女は本屋経営に憧れるものの、人を雇わないといけないと思うと気持ちが揺らぐそうだ。
「きっとうまく行くとは思うけれど、自由な日々への影響が大きすぎる。友人のなかには、ひどい上司のせいで長時間労働をさせられ、ボロボロになっている人もいる。彼らを見ていると人生にはもっと別な選択肢があると思う」
違う形の野心
エロディ・ジャンティナも「Z世代にも野心はあります。ただ違う形なのです」と言う。エムリーンは「もっと大きな顧客がいないか、おもしろい仕事がないか」と思っている一方で、出世には興味がない。フォトグラファーのジャンヌも、建築写真撮影のスキルアップや人脈づくりのために自由な時間を確保している。
エロディ・ジャンティナはこの現象を次のように分析する。
「かつてキャリアは一直線だと考えられていました。何年か経験を積めばチームリーダーになり、次は部長へ......というふうに。でもいまの若い世代は、"10年後に自分がどこにいると思う?"と聞かれても答えられません。彼らは管理職になるよりも自分の専門性を高めたいと考えています。多様な課題を経験し、その瞬間を生きたいのです」
そういう年齢だから? それとも大きな価値観の転換なのだろうか? 今後子どもが生まれて家を買おうという年齢になり、経済的な問題に直面した時にも彼らは「コンシャス・アンボッシング(conscious unbossing)」を継続するのだろうか? やがて答えは出るだろうが、企業側には従来の考え方を多少なりとも改め、対応することがすでに求められている。
「これまでの世代は仕事が最優先で、あらゆるものの中心にありました。いまの若者たちは、"群島型企業"を望んでいます。それはコミュニティの形成を促進し、余暇や休憩にも十分な時間を取り、従業員のメンタルヘルスやウェルネスにも配慮するような企業です。現在のような経済、政治、社会、環境が不安定な環境においては、とりわけ重要になってきます」とエロディ・ジャンティナは分析する。
---fadeinpager---
企業は従来モデルから脱却し、変わらなくてはならない。それにはフレックスタイムの促進や週4日勤務、あるいは数カ月間の「リフレッシュ休暇」などの導入が考えられる。リフレッシュ休暇ではやりたいことに取り組むのもよし、ただひたすら休むのもよしだ。こうした施策が従来型のリーダーシップモデル、ひいては長時間労働や出社を是とし、上司に気に入られることが重要になる風潮を改めることとなる。
エロディ・ジャンティナはさらに、「管理職の職務も再定義すべきでしょう。社員を監視する存在ではなく、ファシリテーターや親切なコーチ役が求められているのです」と指摘した。
いくつかの企業はすでに「縦」ではなく「横」のキャリアパスを設定しはじめている。
「ある営業職の女性は管理職を志願していましたが、実際には自分の専門性を高めて現場で活躍したい気持ちも大きいことに会社は気付きました。そこで、職務範囲と権限を拡大し、アシスタントをつけたのです」
フランスのシンクタンク、モンテーニュ研究所の調査によれば30歳未満の若者の60%が5年以内にいまの会社を辞めたいと考えている。企業へのメッセージは明確だ。対応しなければ有能な人材は去るだろう。そして10年後の彼らの姿を見てみたいもんだと鼻で笑う上の世代も、こう問いかけられれば心がざわつくはずだ。自分を犠牲にして得た成功は真の成功なのだろうか。
From madameFIGARO.fr
text: Ségolène Forgar (madame.lefigaro.fr)












