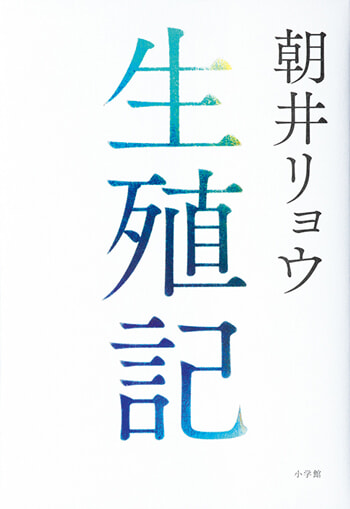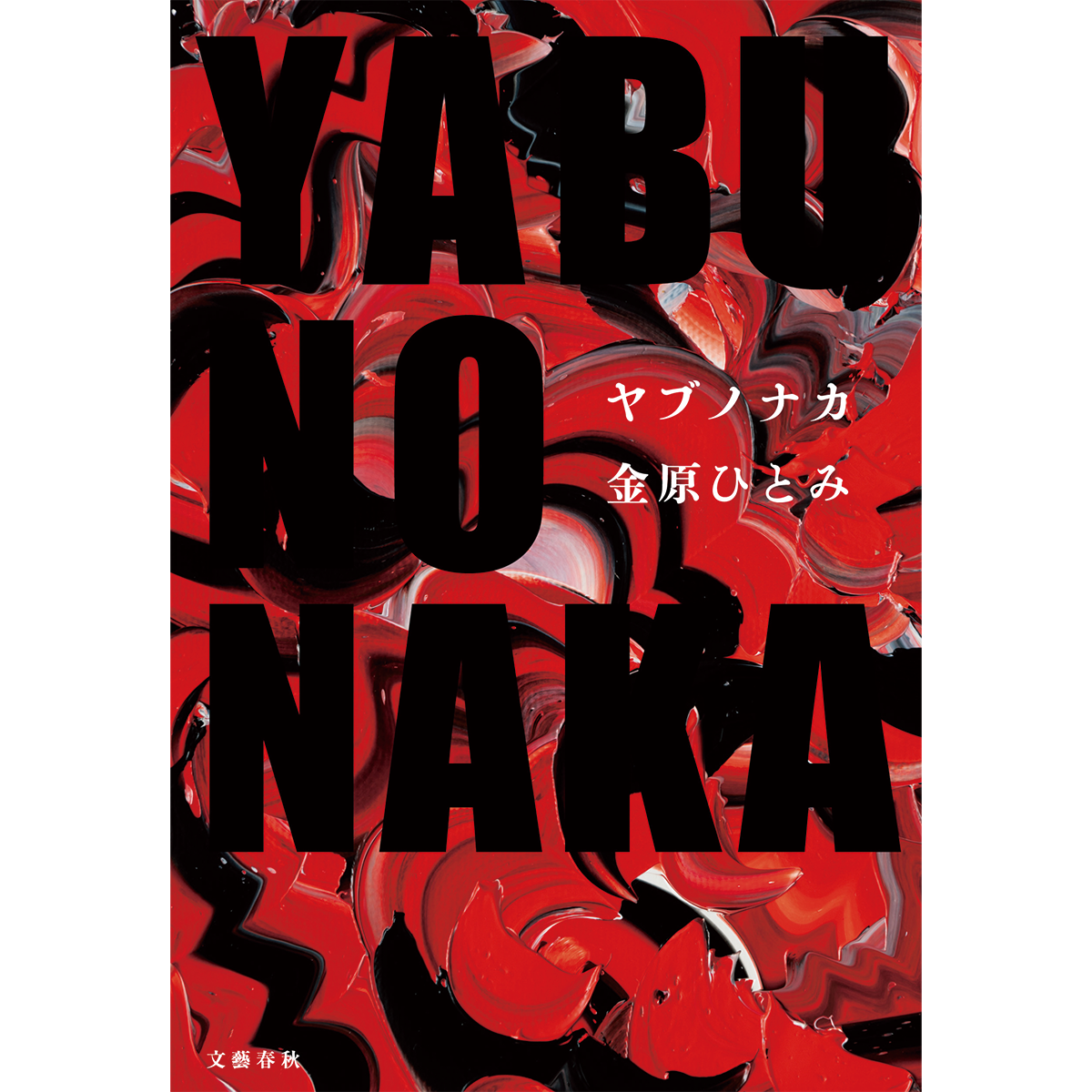朝井リョウと辻村深月、私たちが小説を書く理由。
Culture 2025.08.08
小説って、実はいまを生き延びるための最強のツールかもしれない。読むことを書く力に変えてきたふたりが語り合う、小説がいまできること。
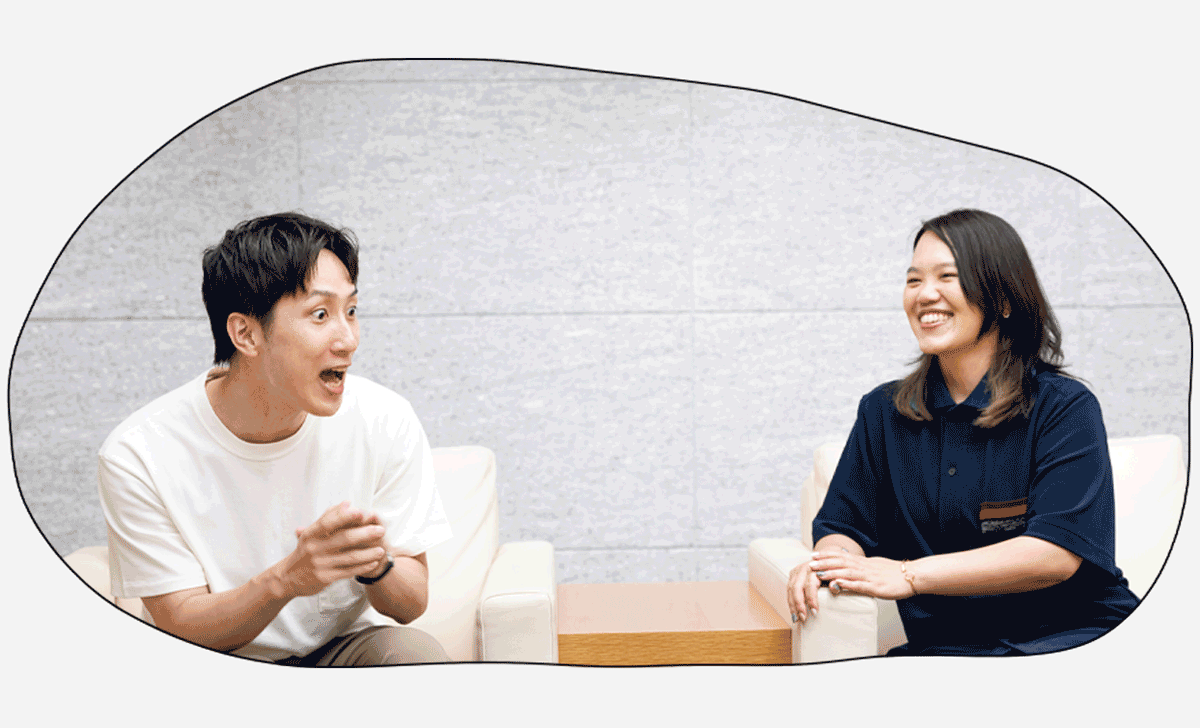
1989年、岐阜県生まれ。2009年『桐島、部活やめるってよ』で小説すばる新人賞を受賞しデビュー。13年『何者』で直木賞、14年『世界地図の下書き』で坪田譲治文学賞、21年『正欲』で柴田錬三郎賞を受賞。
1980年、山梨県生まれ。2004年『冷たい校舎の時は止まる』でメフィスト賞を受賞しデビュー。2011年『ツナグ』で吉川英治文学新人賞、12年『鍵のない夢を見る』で直木賞、18年『かがみの孤城』で本屋大賞を受賞。
(※辻村深月のつじの字は二点しんにょう)
辻村 朝井さんっていま、デビューして何年目ですか。
朝井 二十歳の時に『桐島、部活やめるってよ』でデビューしたので、いま、16年目です。辻村さんは来年デビュー22周年記念作品として上下巻の『ファイア・ドーム』が出るんですよね。
辻村 はい! しかし、朝井さんがまだ16年目なんてびっくりです。それだけ書かれてきた軌跡が濃い。
朝井 ずっと新人ぶってるんで(笑)。
辻村 『生殖記』も凄かったし、新刊が出るたびに話題作になって、次は何を書くんだろうって楽しみです。
朝井 辻村さんなんて15年目で『傲慢と善良』ですよ、びっくりです!
辻村 振り返ると、15年目くらいまではがむしゃらに目の前の作品だけに向き合えていた気がします。だんだん自分という作家が何が得意かがわかるようになってきちゃうと、つい得意な方に行きそうになるんですよ。でもそれだとつまらないし、自分で自分の二次創作をしないようにするにはどうしたらいいんだろうって。その時期にした対談とか見ると、すべての相手にそのことを相談しているんです。
朝井 前を歩いてる人にいろいろ聞きたくなりますよね。私はいまがそうです。
辻村 そうしたら宮部みゆきさんが、自分にもそういう時期があって、その時に編集者に言われたという言葉を教えてくださったんです。「轍にはまるかもしれないと思っている人は、はまらないから大丈夫」と。
朝井 小説みたいな名言が現実で!
辻村 すごく心強い言葉ですよね。以来、得意な道と得意じゃない道があったら、得意じゃない方を選ぶようにて書き続けてきた気がします。
---fadeinpager---
小説の良さって、他者になれること。
自分の問題でいっぱいいっぱいの時でも、
他者のことで心が動くと、自分から自由になれる。
─ 辻村深月
小説を書きたい衝動って、爆弾魔とちょっと似てる。
辻村 初めて小説を書いたのは小学3年生の時なんですけど、朝井さんは?
朝井 私も小3の時に一太郎がやってきて、長い作品はそこからです。それまでは手書きで落書きみたいな感じ。
辻村 私はずっと手書きで、授業中に書いていました。当時は作家になりたいとか投稿を考えていたというより、小説を書きたいという気持ちが先にあった感じです。
朝井 最も純粋な衝動だ。もはや爆弾魔みたいなものですよね。
辻村 そうそう。密かな欲望ってとても強いですよね。
朝井 十代の頃って、書くものがめっちゃ変わっていきませんか。
辻村 変わってくる。朝井さんはジャンルとしては最初に何を?
朝井 その頃は当時読んだものをひたすら真似ていました。小学校の頃は、図書館で借りた『きいろいばけつ』という童話を真似て『あおいばけつ』を書いたり。パクりすぎですよね。
辻村 児童文学から入ったんですね。
朝井 中学生の時に綿矢りささんと金原ひとみさんが芥川賞を受賞されて。そこで一度純文学に憧れたんですけど、高校生になると大衆小説も読むようになって、その路線の作品を新人賞で拾っていただけたという感じです。
辻村 中学高校くらいで書いていたのは、自分の生活とわりと地続きのものが多かったんですか?
朝井 いや、『バトル・ロワイヤル』を真似てクラス全員殺し合う話とか、間違った純文学憧れで退廃的な少年少女の性と死、みたいなのを書いていたのですが、読んだ姉が「気持ち悪い」と。
辻村 身内が書いてると思うとね(笑)。
朝井 「背伸びせずもっと身近な話にしたら」と言われて、高校生の時に学校に隠れて住んでいる子たちの話を書いたんです。そしたら、それまで箸にも棒にも引っかからなかった新人賞で初めて一次選考を通過して。自分はこっちの方が向いてるんだ、といまの方向性の決定打になりました。
辻村 じゃあ『桐島、部活やめるってよ』が最初の投稿じゃないんですね。
朝井 中学生くらいから紙でもネットでもずっと何かしらに投稿していました。感想が欲しくて。当時はブログも書いてたんです。さくらももこさんが大好きで浴びるように読んでいたので、完全にそれに憧れちゃって、岐阜県のバレーボール部員の高校生ということだけ明かしていろんなエピソードを面白おかしく投稿していました。そしたら結構アクセス数が伸びて、ランキングとかに載るようになって、調子に乗ってたら当時の岐阜県の高校生が出入りする掲示板に片っ端から晒されました。この世の終わり。絶望。
辻村 ええっ。もうSNSの洗礼を⁉
朝井 ネットの怖さを知りましたね。
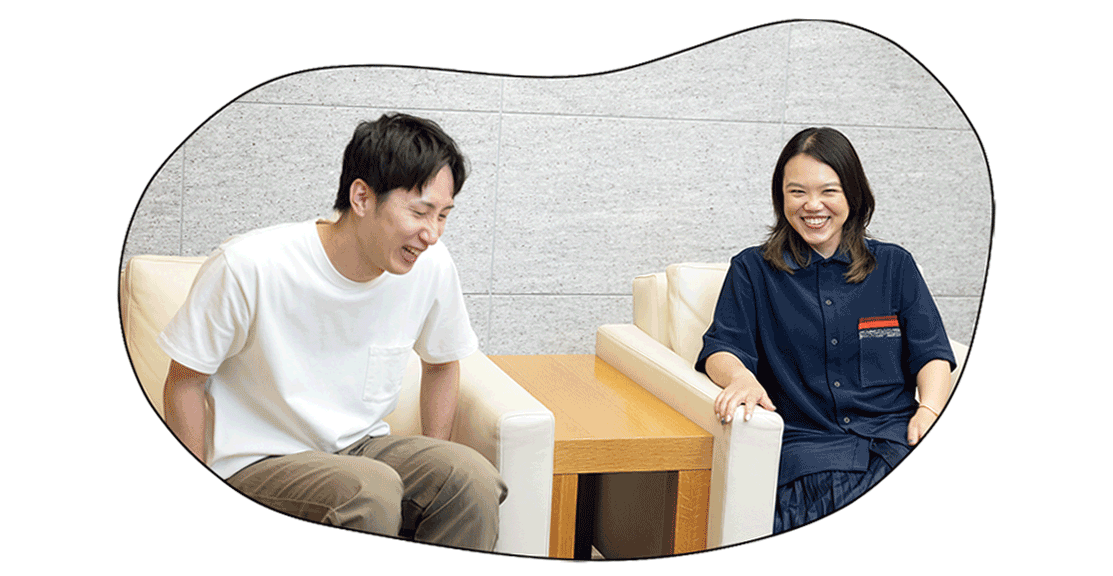
---fadeinpager---
辻村 やっぱり十歳違うとネットの環境が全然違うんだなと。私が十代の頃は、ネットに気軽に投稿できる近さではなかったから。小学生の時は、クラスメイトたちの間で小説書くのが流行っていたんです。
朝井 クラスメイトたちの間で小説書くのが流行るなんて世界が!?
辻村 みんな、折原みとさんの『ティーンズハート』の小説が大好きで、その影響で交換日記とかに好きな男子と自分の話を書いたりしていたんです。それで、私も書き始めた。『学校の怪談』がすごく好きで、最初に書いた話もそういうテイスト。見えている世界だけじゃなくて、自分たちの日常の世界と地続きに、あの角を曲がったらその先に違う世界があるかもしれないと考えるとワクワクしてくる。当時からそういう感覚がすごく好きで、いま書いている小説とも繋がっている感じがします。『ドラえもん』もそうですよね? 畳の裏が宇宙と繋がっていたりして。
朝井 確かに近いですね!
辻村 中学生くらいになると今度はファンタジーを書き始めたんです。小野不由美さんの『十二国記』に大ハマりしてそこからまたいろいろ読んで、ファンタジーを書き始めると何が起こるかって言うと、完結できないんですよ、一大サーガになるから。
朝井 まずは地図をつくるところから、みたいな規模のやつだ。
辻村 本当にそういう感じ。何編の次は何編を書かなきゃって、大学ノート10冊分くらいになって、タイトルはちょっと恥ずかしくて言えない(笑)。
朝井 ミュージシャンも昔組んでたバンドの名前言わないですからね(笑)。
辻村 朝井さんはお姉さん以外に誰かに読んでもらったりしていましたか。
朝井 基本、ネットでしたねえ。
辻村 ネットか。私は友達に読んでもらっていたんです。
朝井 長編を読んでくれる友達の存在、尊い。そもそも顔の見える人に読んでもらうって発想がなかった気がする。
辻村 高校生になると綾辻行人さんの『十角館の殺人』に衝撃を受けて本格ミステリーにハマったことで、異世界ファンタジーではなく現実の延長っぽいものを書くようになったんです。デビュー作の『冷たい校舎の時は止まる』も二作めの『子どもたちは夜と遊ぶ』も三作めの『凍りのくじら』のもとになった小説も全部、高校生の時に書いて、クラスメイトたちが読んでくれました。でもうまいとかヨイショみたいなことは言ってくれないの。
朝井 厳しいんですね、そこは。
辻村 ちょうど『名探偵コナン』と『金田一少年の事件簿』が流行っていた頃で、謎解きしながら読んでくれるんだけど「ここは納得できない」とか言われちゃう。授業中に書いてるから、休み時間になると隣のクラスの友達が「進んだ?」ってとりに来て。
朝井 怖い編集者だ! やめて!
辻村 「うまい」とか褒められるより「続きが読みたい」って言われたのがうれしくて、初めて「あ、プロの作家になれるかもしれない」って思いました。だからずっと書き続けてはいたんですけど、怖くて投稿できなかったんですよね。これを投稿して否定されたら絶対に立ち直れない気がして。
朝井 デビュー作の『冷たい校舎の時は止まる』って上下巻ですよね。
辻村 1300枚くらい。大学生になっても続きを書いていて、この小説の決着をつけないことには書き続けてしまう。ダメならダメで結論が出た方がいいと思って徹底的に直して送ったらもう、抜け殻ですよ。
朝井 凄い、それで一本釣り!
辻村 当時あの枚数を受けつけてくれるのがメフィスト賞しかなかったから。
朝井 デビュー作にはすべてがあるとよく言われますが、私の場合もそんな気がします。高校から大学に進学した時、こんなに別の世界になるんだとびっくりしたんです。すし詰めの教室で全員同じカリキュラムで、誰かが少し動いただけでも10メートル先の何かに影響があるみたいな、あの中高特有のぎゅうぎゅう詰めの機微を標本みたいに残しておきたくなったんですよね。いまでも、「この立場の人が何かを成す姿を書きたい」というより、「いまのこの感覚を忘れないうちに紙の上で再現しておきたい」というようなモチベーションで小説を書くことが多いのですが、『桐島、部活やめるってよ』はその原点だったなとあらためて思います。
---fadeinpager---
こういう気持ちってあっていいんだ、
こういう気持ちを抱いている人がほかにもいるんだ
っていう気付きって、
思った以上の喜びになると思うんです。
─ 朝井リョウ
なかったことにされている感情にどうしたら光を当てられるのか。
辻村 朝井さんの小説を読んで、毎回凄いなと思うのが視点なんです。これをこの視点から描くのかって。どの作品も真ん中に違和感があって、なかったことにされてる感情が描かれているんだけど、誰かの話じゃなくて、全体の話になってる。
朝井 視点、本当に難しくないですか。書こうとしている世界にどこから光を当てるのか、それを決めるのに一番時間がかかります。どこにライトを置けば書きたいことを照らせるのか、と。辻村さんはどうしていますか。
辻村 私の場合は、とりあえずこの辺を照らそうみたいな感じで書き始めて、「あ、いたーっ!」みたいな。
朝井 それで「あ、いなかったー!」にならないのが凄いんだよなあ。
辻村 いままでもいたんだから、きっといるはずと信じて書き始める。だから小説を書きたい人で、全体が見えないと不安で書き出せない人もいると思うんですけど、とりあえずまずは書き始めてみてほしい。その1シーンから広がることがあるかもしれないから。
朝井 ベストよりベター、ですよね。私の場合、日常の中で頭の中に「あ、いま、一万字流れたな」って瞬間があるんです。その場では空気を停滞させないために簡単な言葉でやり過ごすんだけど、これは本当は一万字言葉を尽くさないと語れないことだなと思うことがあって、それが構想の起点になってくれることが多いです。
辻村 書く時、怖くないですか。
朝井 めっちゃ怖いです。この問題とかこの言葉に対するこういう感情って、紙の上に引きずり出してもいいんだろうか。ないふりしていた方が世の中は回るんじゃないかっていつも怯えるんですけど、結局書かないと次に進めないんです。でも、そういう作品ほど想定外の反響がある気がします。
辻村 朝井さんの作品はいつも、書くの、勇気要ったろうなと思います。
朝井 自分を隔離することが必要だから、感想とか書評も見ないようにして。
辻村 わかります。
朝井 最近、届く感想が書き手によって全然違うっていう話で同業者と盛り上がったんです。私に届く読者の手紙って、小説の感想はほぼゼロで、「読みました。私は......」って即その人の秘密大公開が始まるんです。辻村さんってどんな手紙が多いですか?
辻村 朝井さんだからそういう手紙が集まるんだよ。それって才能だよ。私に来る手紙も、たぶん朝井さんほど全暴露ではないけど、やはりみんなの「自分の話」が書いてあったりするから、そういう手紙は深く印象に残ります。
朝井 残る感想ってありますよね。この間、辻村さんの『この夏の星を見る』を拝読しまして、あれってコロナ禍が一番混沌としていた2020年から1年間ほどの中高生の話じゃないですか。読者の感想で「これ04年生まれの子たち絶対読んで!」ってコメントがあって。「私たちが感じていたことが、この本の中に全部あるから」って。
辻村 わぁ、うれしい!
朝井 あの時の自分たちの感情を書いてくれている小説がなかったんだろうなって。その感想からあの本の存在がその子たちにとってものすごく大きかったことが伝わってきました。
「これを読んでること、誰にもバレちゃダメだ」
って思うくらい、自分の隠したい部分にも
手のひらを添えてもらえる。
─ 朝井リョウ
辻村 本の良さって何だろうってあらためて考えた時に、本って真空パック度が髙いと思ったんです。本を開いて物語の中に入れば、そこに流れていたことがたちどころにその時のままの鮮度で自分に還ってくる。
朝井 うんうん。こんな気持ちを抱いてるのって自分だけじゃないかって、特に十代の頃は思いますよね。こういう気持ちってあっていいんだ、こういう気持ちを抱いている人がほかにもいるんだっていう気付きって、思った以上に喜びになると思うんです。『この夏の星を見る』の感想を書いたあの子も凄く嬉しかったんだと思います。
辻村 サイン会に来てくれた人から「自分は職場で本を読めと言われて、これまでビジネス書とか自己啓発本ばかり読んできたけど、あなたの小説を読んで初めて小説ってこういうものかと思いました」って言われたことがあるんです。その時一緒にいた編集さんが「ヘレン・ケラーがウォーターって言った時と同じような感動がありました」って言ってくれたんです。私の本じゃなくてもいいから、そういう1冊と出会ってほしい。まだ出会っていないだけでこれから出会うかもしれないし、大人になってからでも全然遅すぎるってことはないと思うんです。
朝井 出版業界の中にいると、小説が持つパワーみたいなものを自然と共有している前提で考えてしまいますけど、社会は意外とそうではないですよね。
辻村 ビジネス書とか何かの指南書は自分に還ってくるものだけど、小説の良さってなかなか読む前は伝わりにくいから。でも良さの一つとしては、まず他者になれること。自分の問題で頭がいっぱいの時でも、本を読んで他者のことで涙したり、心が動いたら、目の前の問題から一時離れて、ほかのことを考えられる隙間が生まれる。自分から離れて自由になれる時間っていうのは意外に悪くないものだよって。
朝井 他者の時間を過ごすことって、自分を含めた世の中を見つめる視点を増やすことでもありますもんね。あと小説ならではだと思うのは、「これを読んでること、誰にもバレちゃダメだ」って思うくらい、自分の隠したい部分にも手のひらを添えてもらえること。十代の頃図書館の片隅で村山由佳さんの『BAD KIDS』を読んでいた時の時間は、いまでも忘れられません。
---fadeinpager---
本当に凄い小説って、
それを読んだ人たちの共通言語になる。
秘密を共有するみたいにわかちあうことができる。
─ 辻村深月
本当に凄い小説って何だろう、書き続けるためにできること。
辻村 朝井さんは、金原ひとみさんの『YABUNONAKA ヤブノナカ』は読みましたか。
朝井 まだ途中なんです。金原さんの「情熱大陸」はすぐに観ました(笑)。
辻村 凄い本。眠いのに止められなく て、本を置くことが出来なかった。
朝井 金原さんの本って耳元で怒鳴ってくれる。ラッパー金原ひとみ!
辻村 文学界で起こった性加害を軸に進む話だけど、ストーリーだけでは語り切れない。視点が変わるたび、その人の気持ちが憑依するように入ってくるし、人の数だけ立場と正義があるから、『ヤブノナカ』というタイトルを振り返って痺れる。本当に凄い小説って、それを読んだ人たちにとって共通言語になりますよね。それを知った者同士だけがわかりあえることを、秘密を共有するみたいにわかちあうことができる。「早く読んで」「早くこの小説の話がしたい」って言いたくなります。
朝井 Webで連載を読んでいるんですけど、中村うさぎさんの『「失われた私」を探して』がいまの私にとってのそれかもしれません。いま67歳の中村さんがあらゆる種類の依存症を経験してきた自分の人生を振り返っているんです。ホストのこと、性産業で働いていた時のこと、薬で依存症になった人を逆に匿っていた時のこと......。"生きる"を選ばせてくれるドーパミンは人それぞれで、それがたまたま犯罪と規定されているものに向いちゃう人もいて、それを断罪せず書いている姿勢が好きで色んな人に薦めちゃっています。本になるのが待ち遠しいです。
辻村 読者からベスト作を更新してもらえる作家になりたいですね。私、作家の綾辻行人さんに魂レベルで影響を受けているのですが、自分の中の綾辻さんのベスト作は『十角館の殺人』で、出会った時の衝撃もあるからこの先も更新されないだろうなと思っていたんです。ところが『Another』が出て更新された。大好きな作家がリアルタイムに新作で自分のベストを塗り替えてくれたことへの感動があり、なんてかっ こいいんだろうと。だから挑戦し続けたい。朝井さんが出してくる視点とテーマと描き方にも、こういうことが毎回できるようになりたいんだよって刺激をもらっています。
朝井 本当にフレッシュで在り続けたい! 子どもの頃に読んだ佐藤多佳子さんの『一瞬の風になれ』が大好きで、テーマとかメッセージとか関係なく、ただ夢中で読んだっていう一点の最強さってあると思っているんです。そういうものを書きたい自分と、恐れ多すぎますが夏目漱石の『こころ』みたいな、ずっと分析され続けているのに底が見えない、でも強烈に人間が描かれているっていう、解けない謎みたいな小説をいつか書きたい気持ちもあります。同一作者が書いたとは思えないくらい空気が違う作品を書く人に憧れがあるんです。最近ちょこちょこ人前で踊る機会があるんですけど、そういうことも含めて、次に何を繰り出すかわからない書き手になるのが理想です。
対談で登場した本
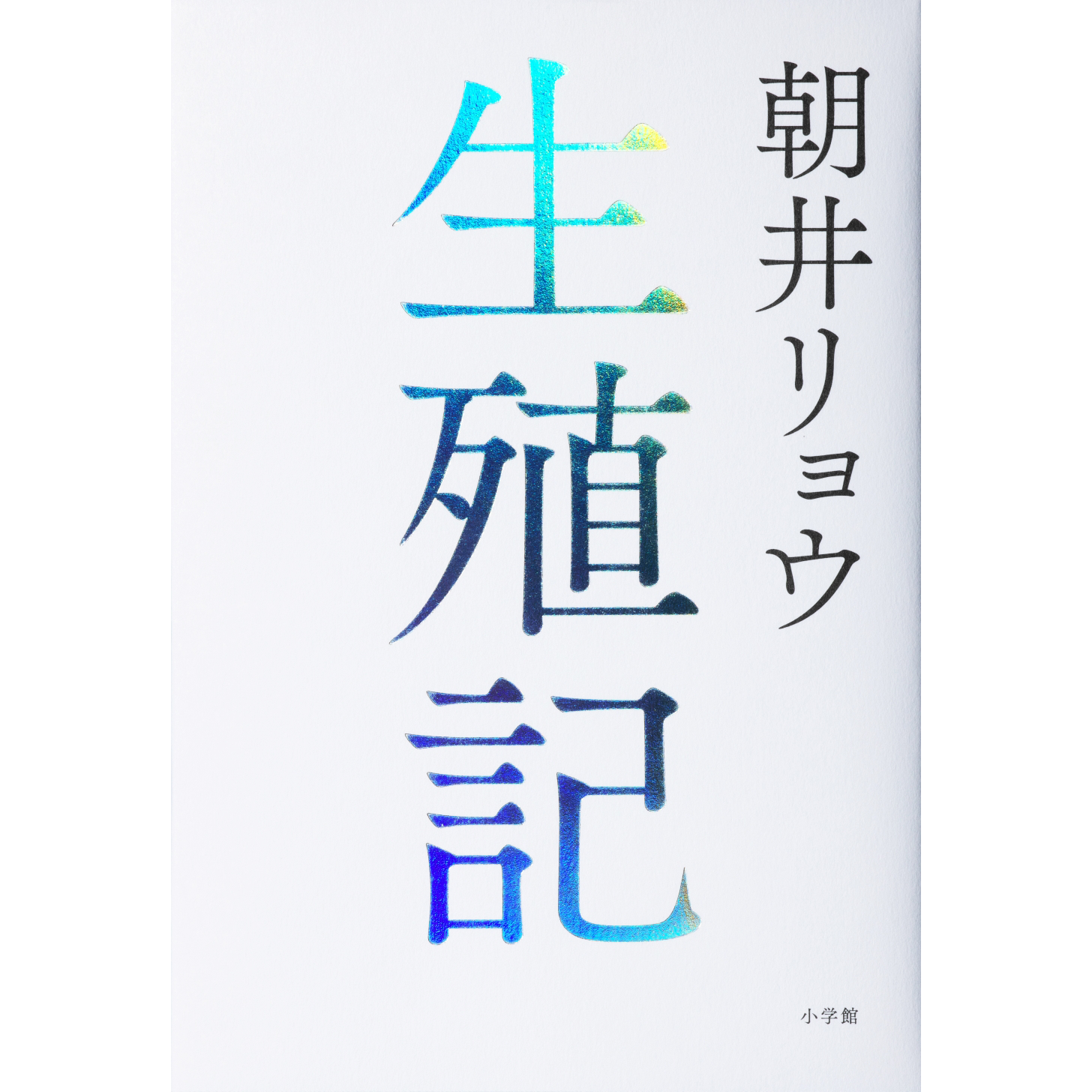
家電メーカーの総務部で働く達家尚成の日常を驚くべき視点から赤裸々に語り尽くす。マジョリティではない人間の反撃であり、日々遭遇している生きづらさの告発をシニカルでポップな手口でやってのけた最新作。
●朝井リョウ著 小学館刊 ¥1,870
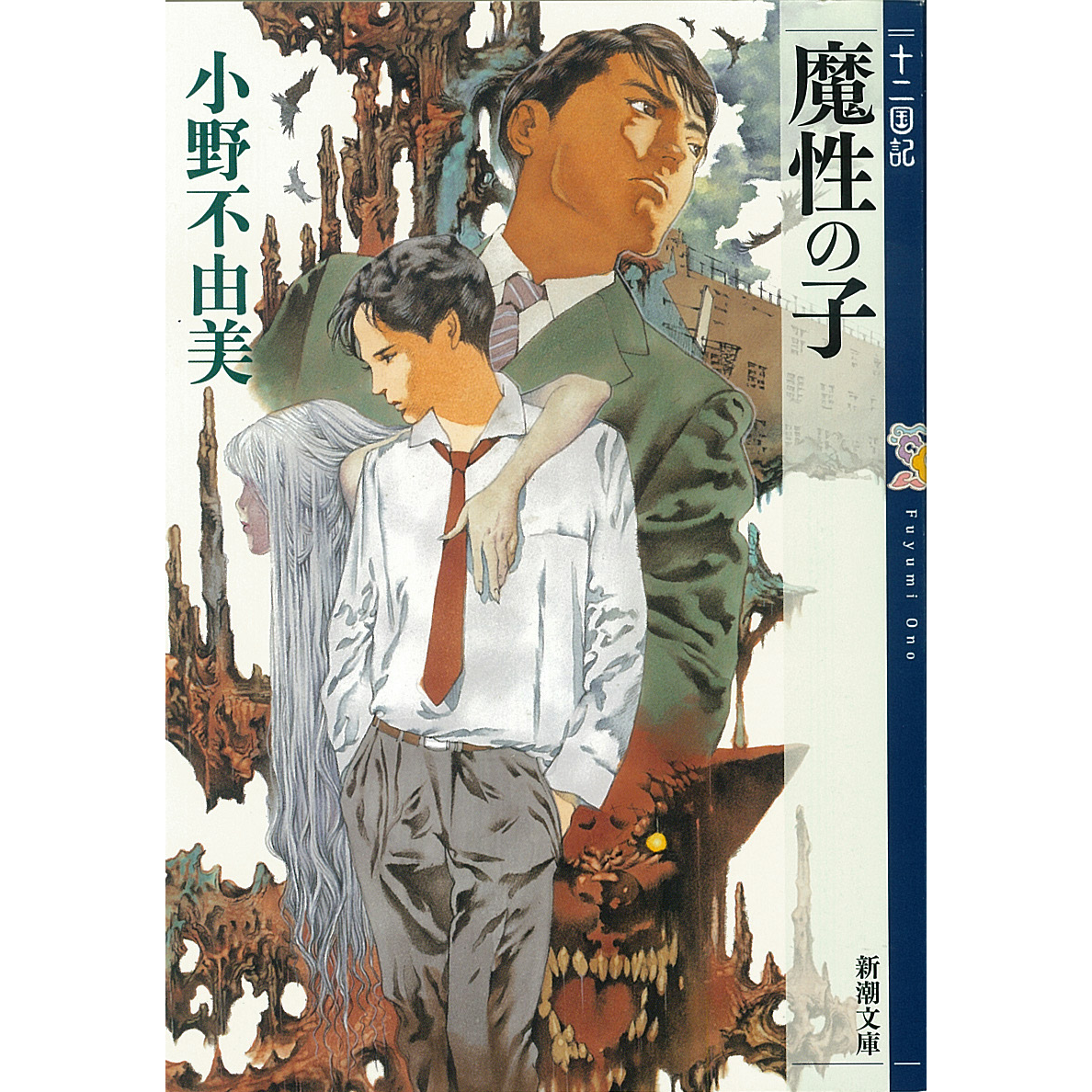
謎の男ケイキに異世界に連れ去られ、女子高生の陽子の過酷な旅が始まる。1991年に刊行され、累計1000万部を超える『十二国記』シリーズ。本作はエピソード0にあたる。容赦ない展開が待ち受けるホラーの名作としても名高い。
●小野不由美著 新潮文庫 ¥935
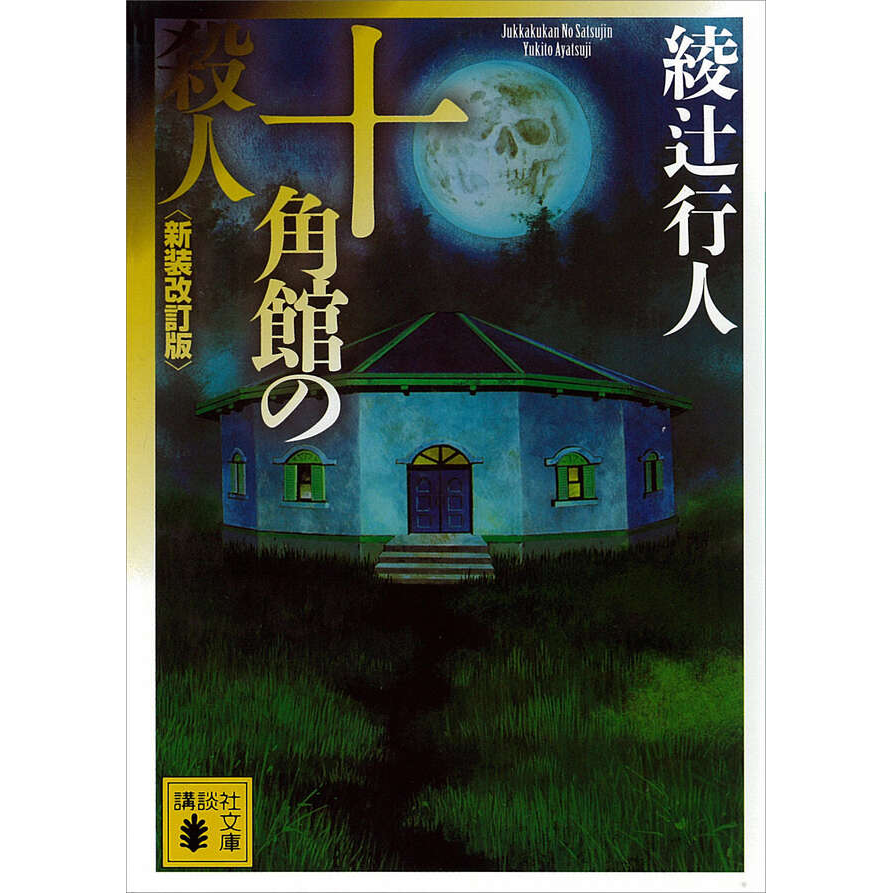
十角形の奇妙な館が立つ孤島を訪れたミステリー研究会の7人がひとり、またひとりと殺される。「館シリーズ」の幕開けとなった綾辻行人の代表作。1987年の刊行以来、衝撃は色褪せず、本格ミステリーブームはここから始まった。
●綾辻行人著 講談社文庫 ¥946
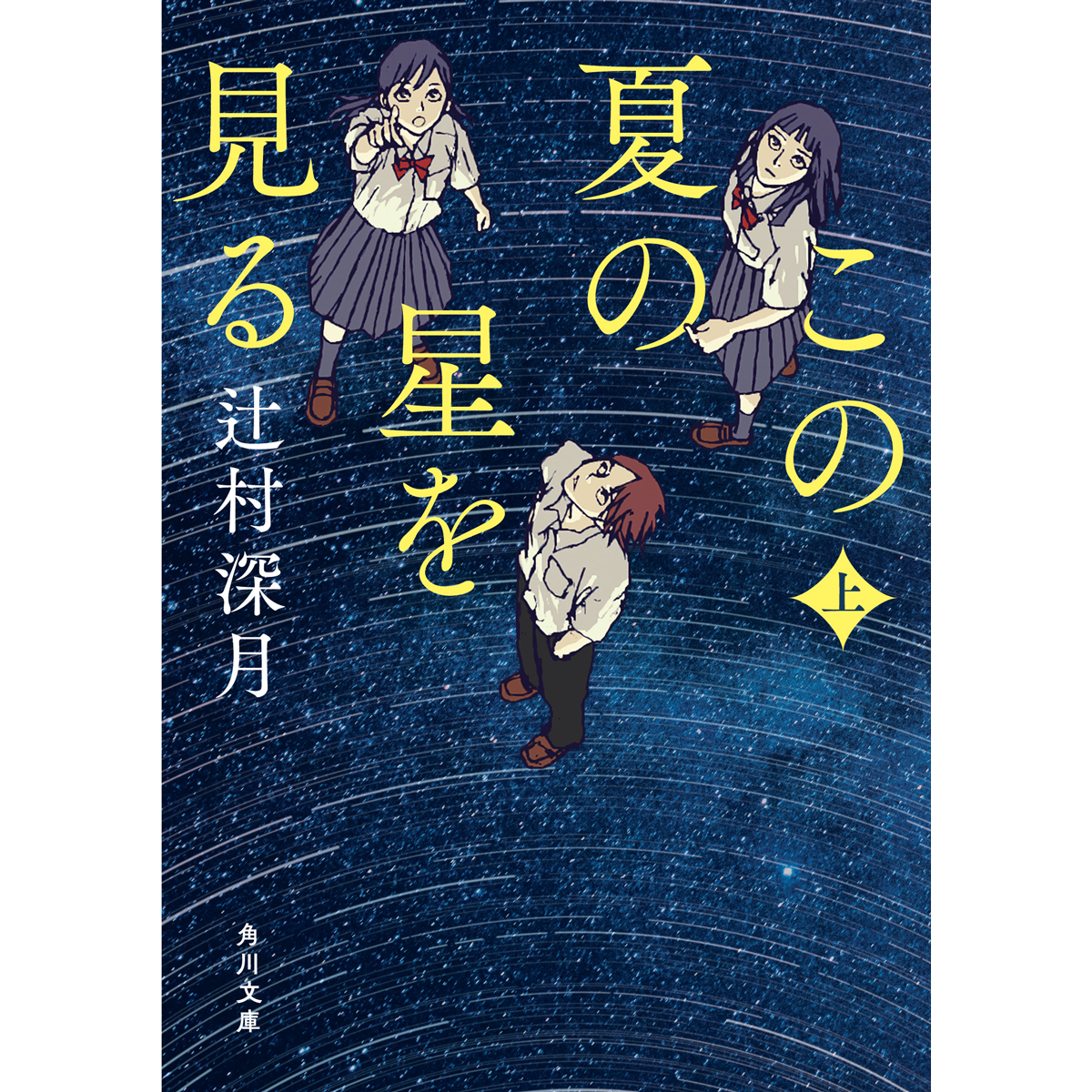
主人公は2020年の学生たち。楽しみにしていた合宿はコロナ禍で中止になり、友だちにも会えない。絶望を突き崩し、希望に変えてみせる言葉にハッとさせられる。星空の下、オンラインで繋がる彼らのただ一度きりの夏の物語。
●辻村深月著 角川文庫 上下巻各¥902
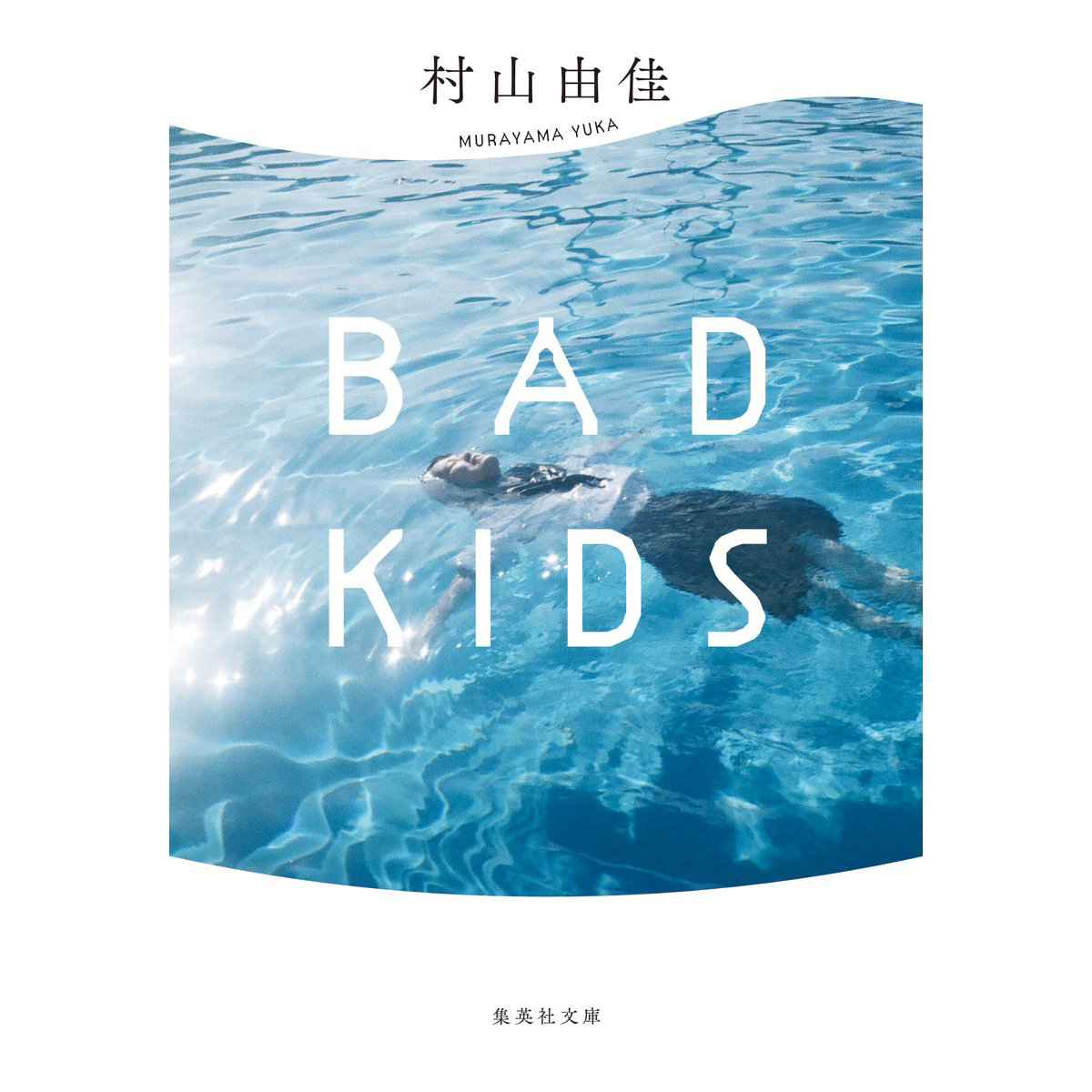
恋をするということは、既存のモラルやルールの外に出て、ごまかしようのない自分を知ることなのかもしれない。人には言えない想いを抱える姿が痛々しくもせつない。愛と性に揺れる18歳の葛藤をみずみずしく描く1994年初版の青春小説。
●村山由佳著 集英社文庫 ¥682
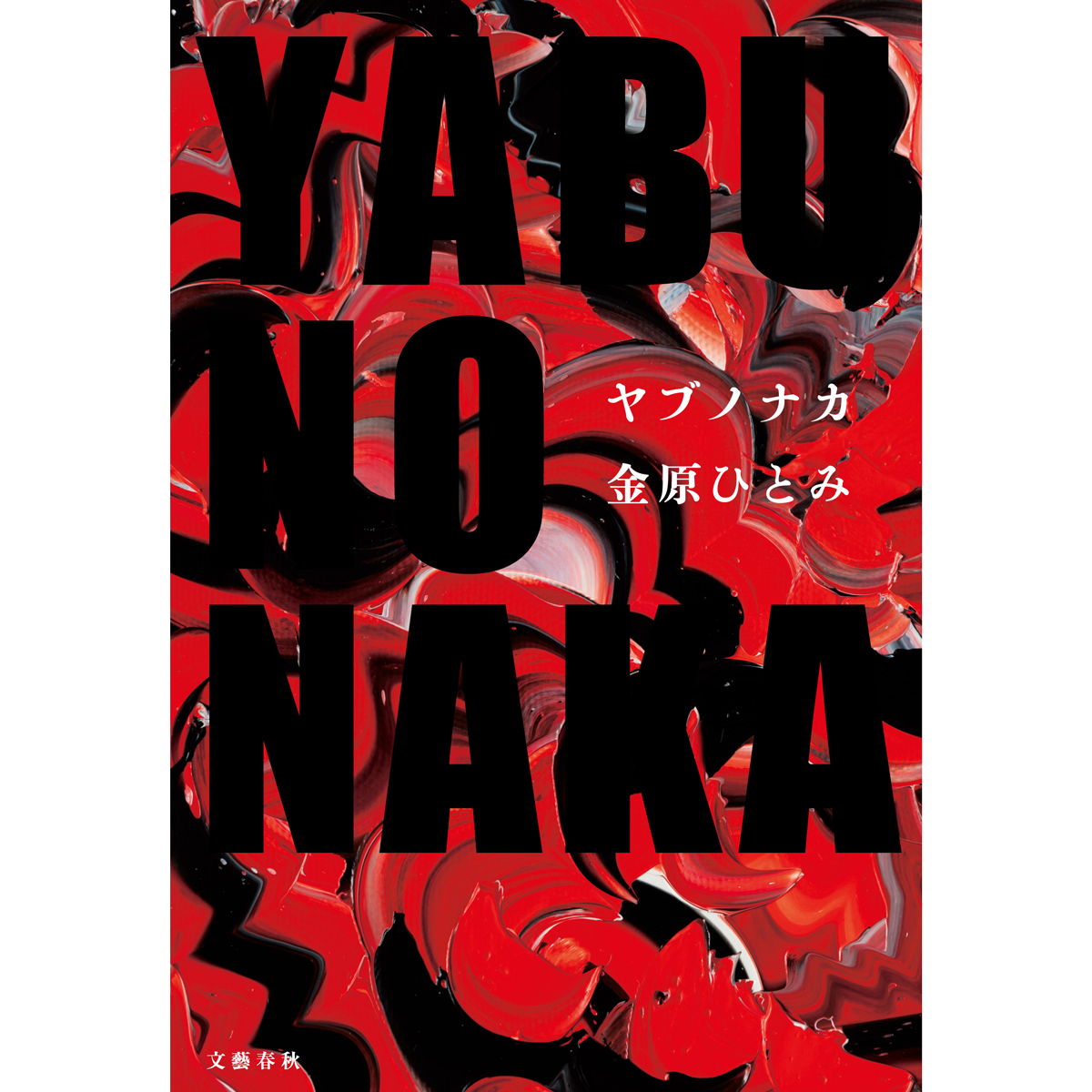
ある女性が、文芸誌の元編集長から性的搾取を受けていたと告発。加害者、被害者、その家族や周囲の人々の日常は一変する。現実を的確な言葉でえぐり、叩きつけるようなファイティングスタイルの文体に圧倒される。
●金原ひとみ著 文藝春秋刊 ¥2,420
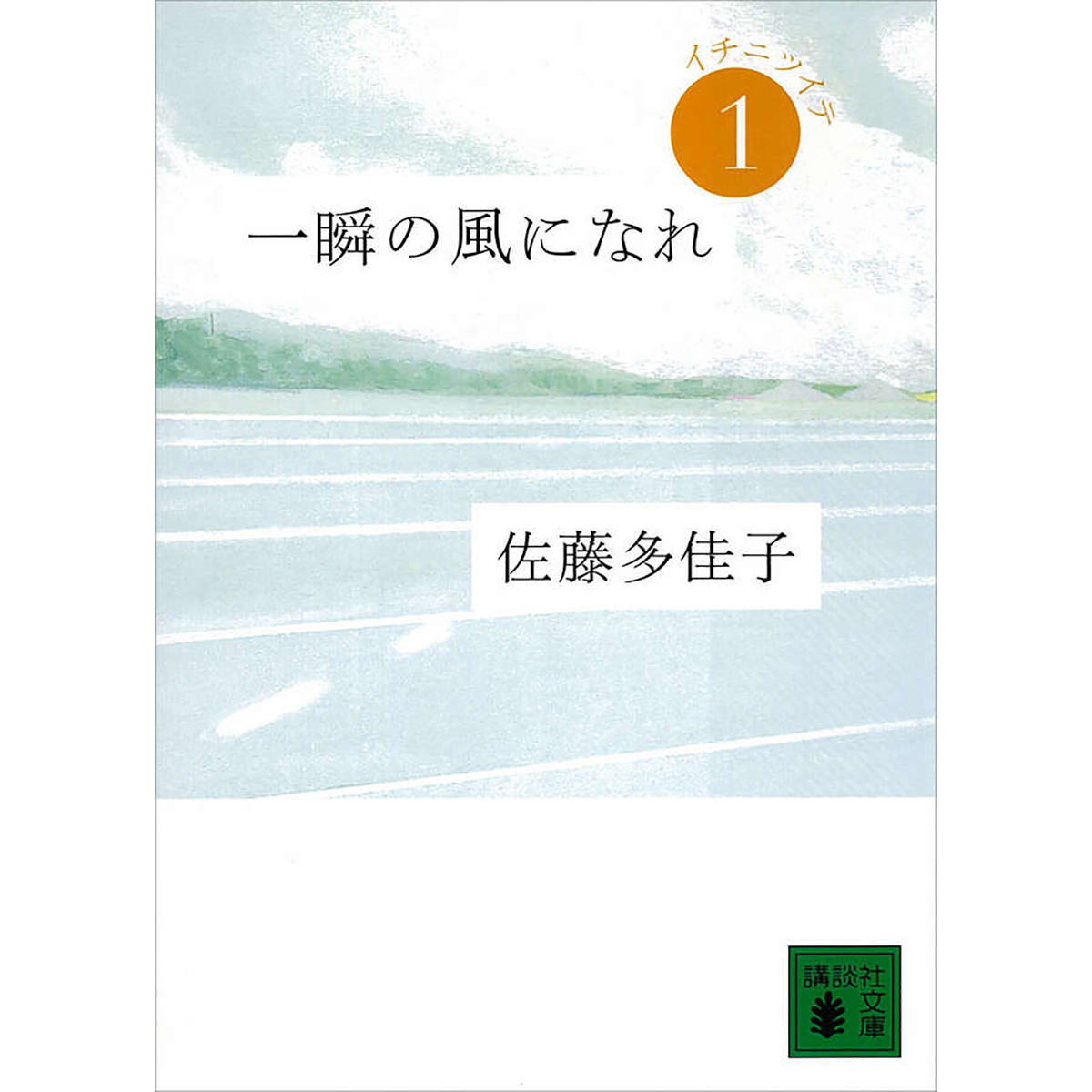
サッカーに打ち込んできた神谷は、自分には才能がないと高校で陸上部に転向。幼なじみの天才スプリンター、一ノ瀬連の走りに魅了され、走る楽しさに目覚めていく。これぞ青春小説の決定版と言える殿堂入りの名作。
●佐藤多佳子著 講談社文庫 第一部¥660 第二部¥704 第三部¥902
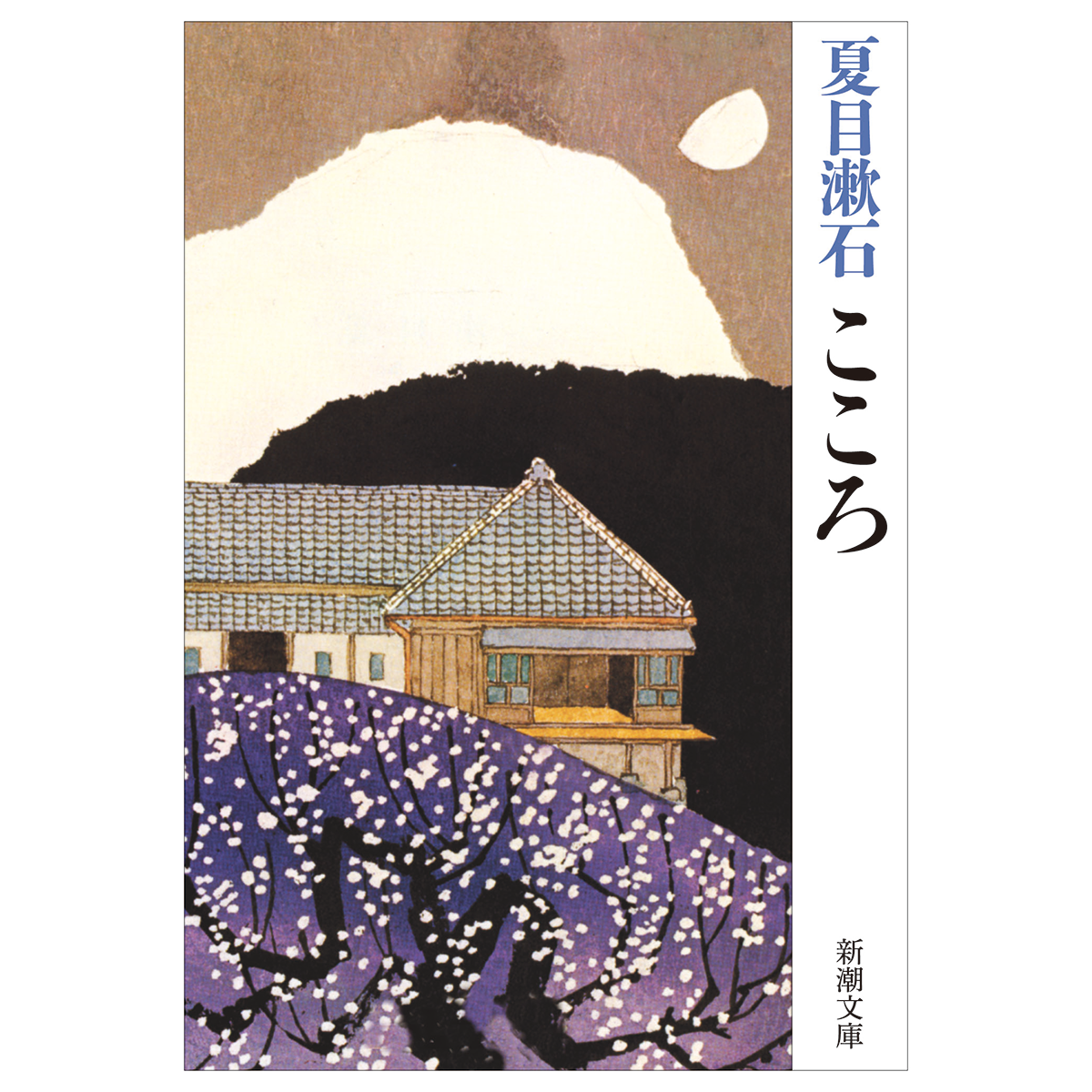
私が「先生」と呼んで慕うその人とは、かつて鎌倉で出会った。先生の人を寄せつけない態度の理由がおぼろげにわかってくる。自分の心を貫く自由と裏腹に突きつけられた孤独。夏目漱石が描き続けたテーマはいまも色あせない。
●夏目漱石著 新潮文庫 ¥473
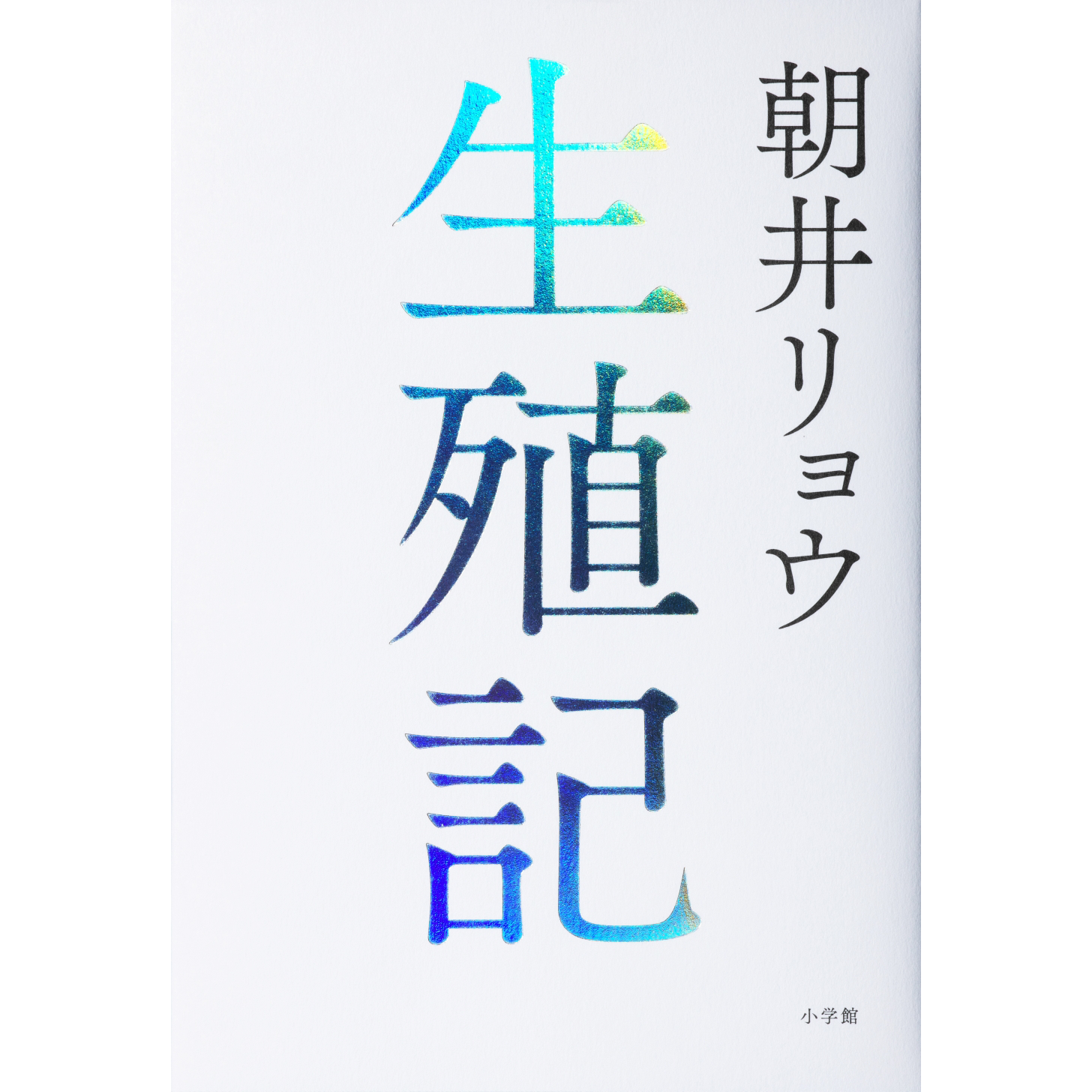
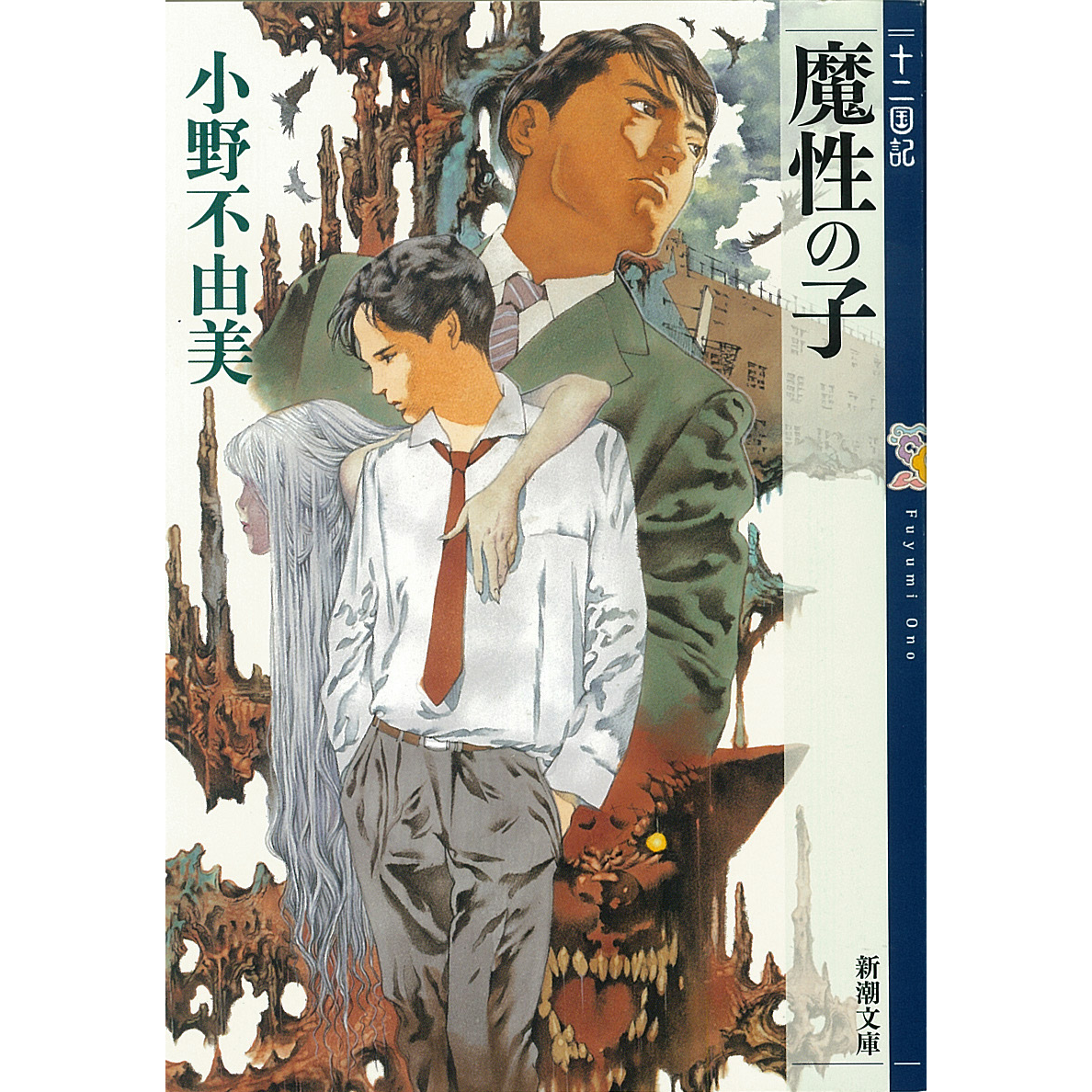
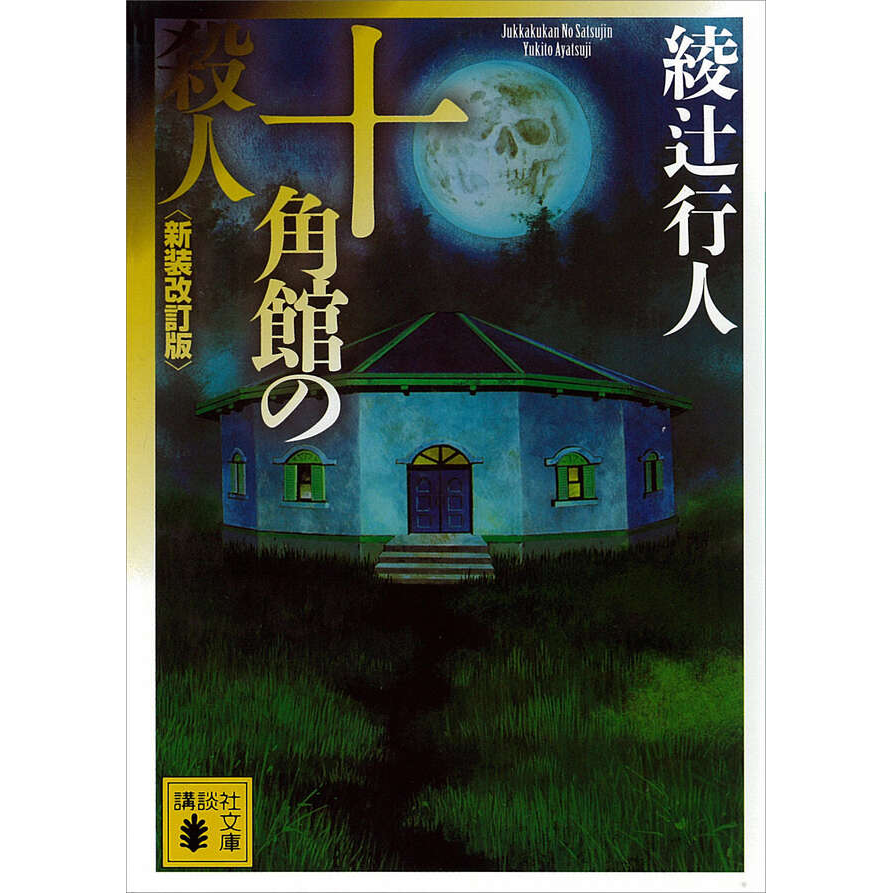
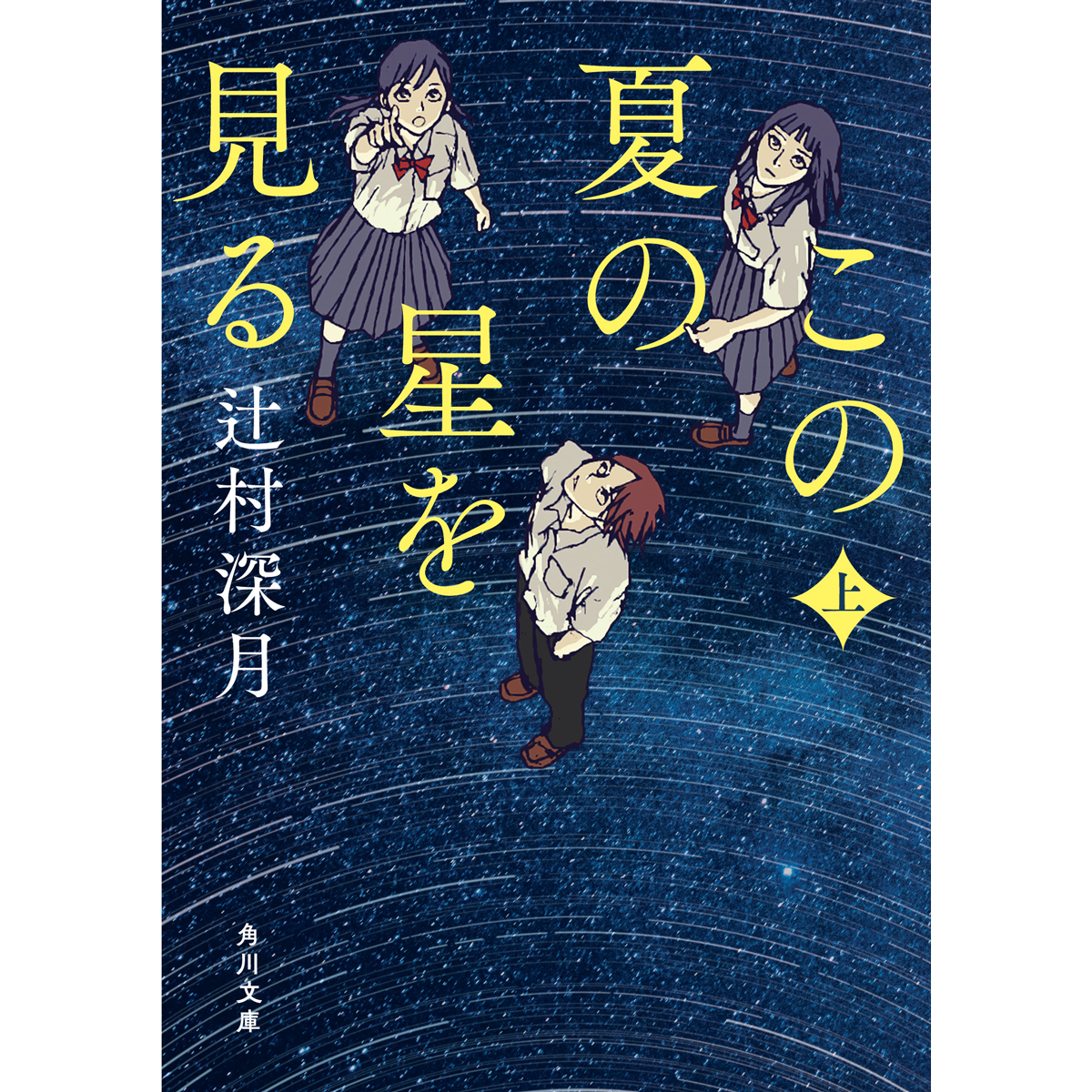
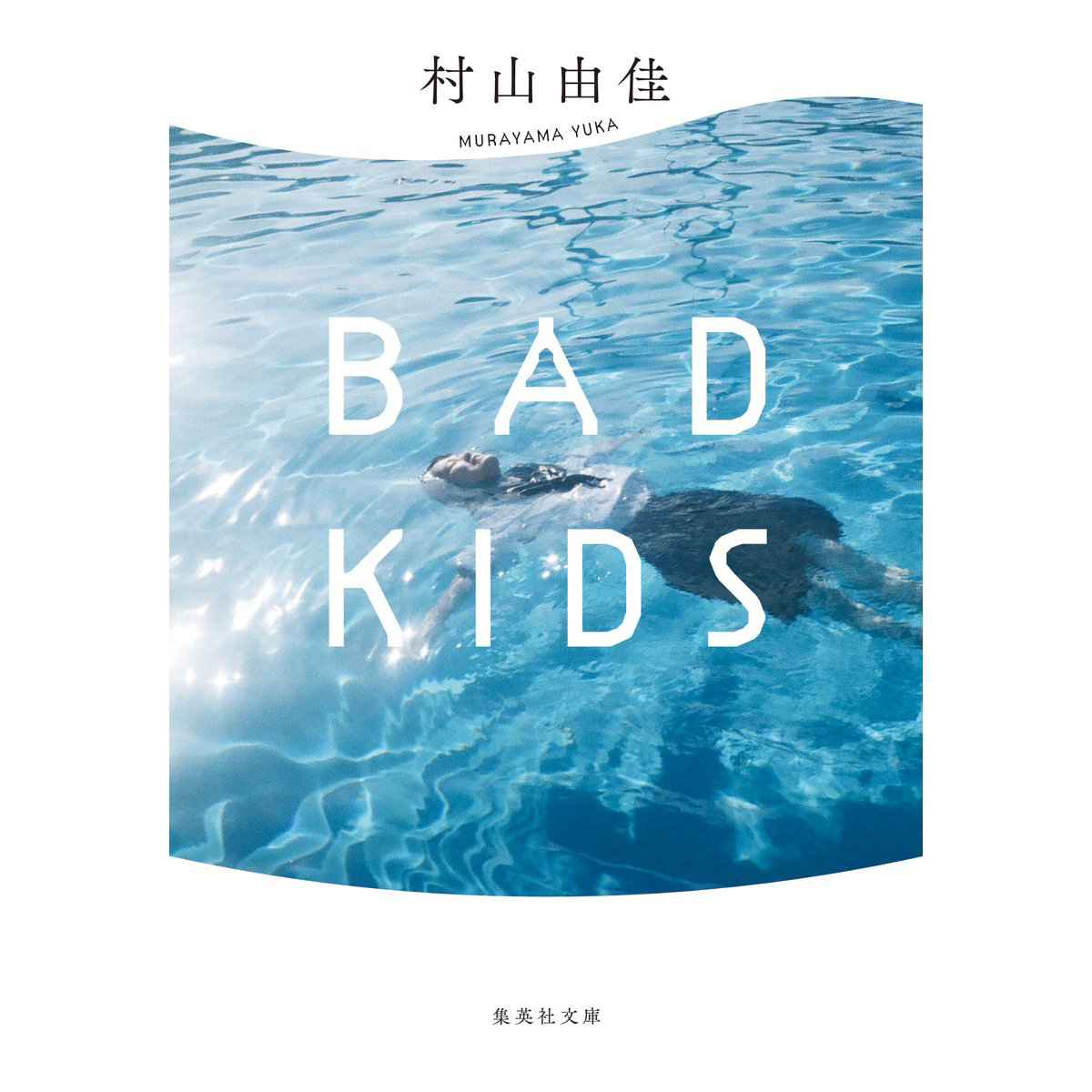
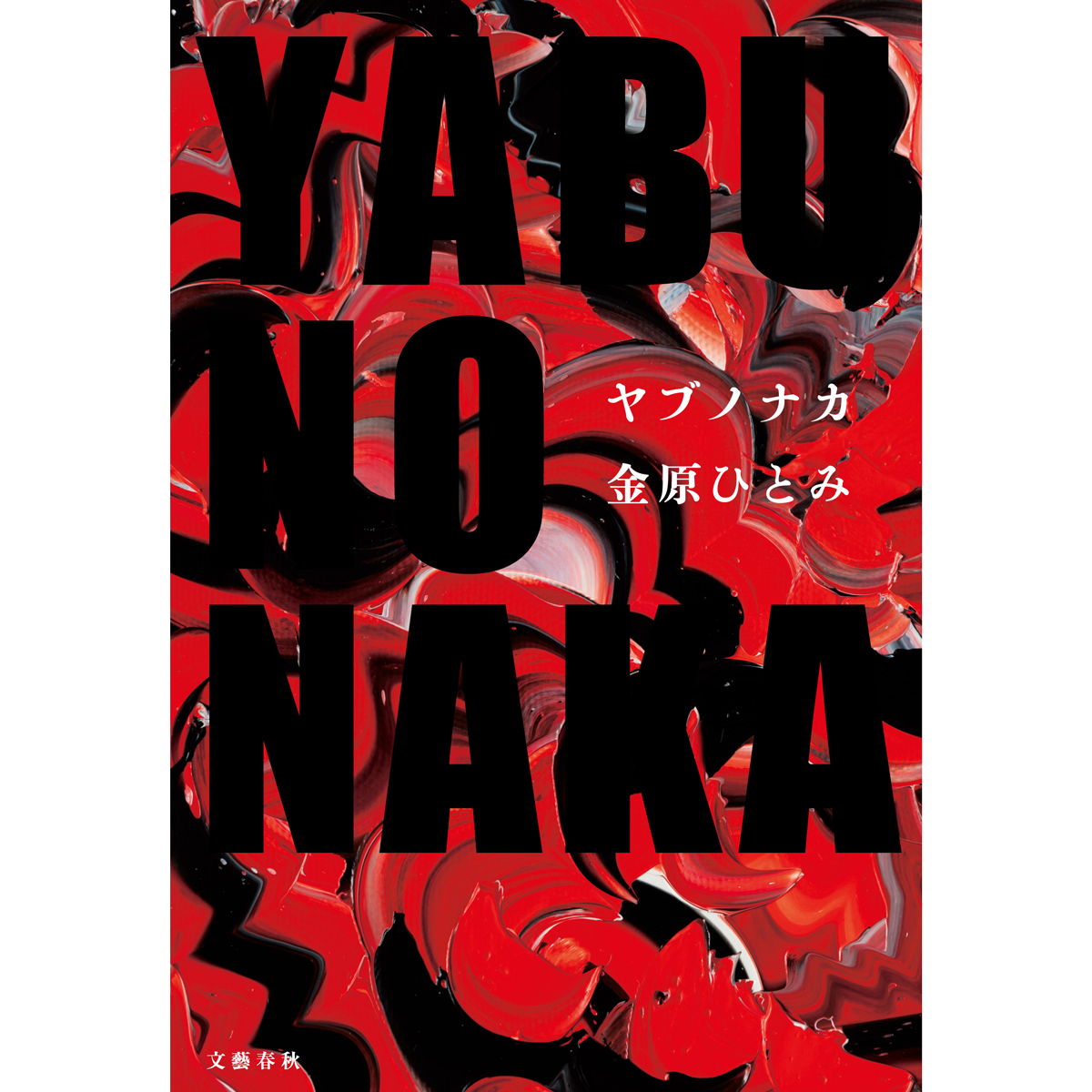
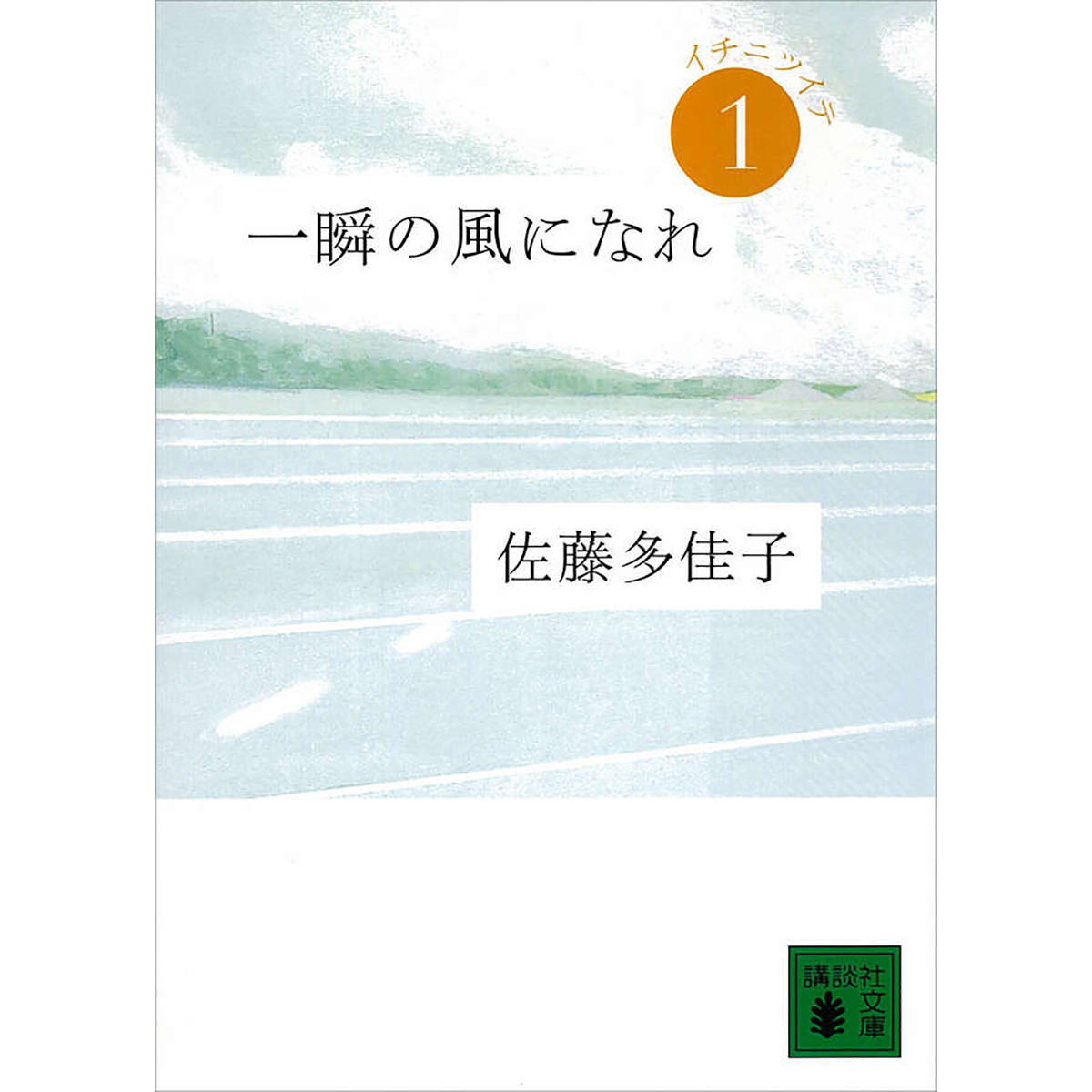
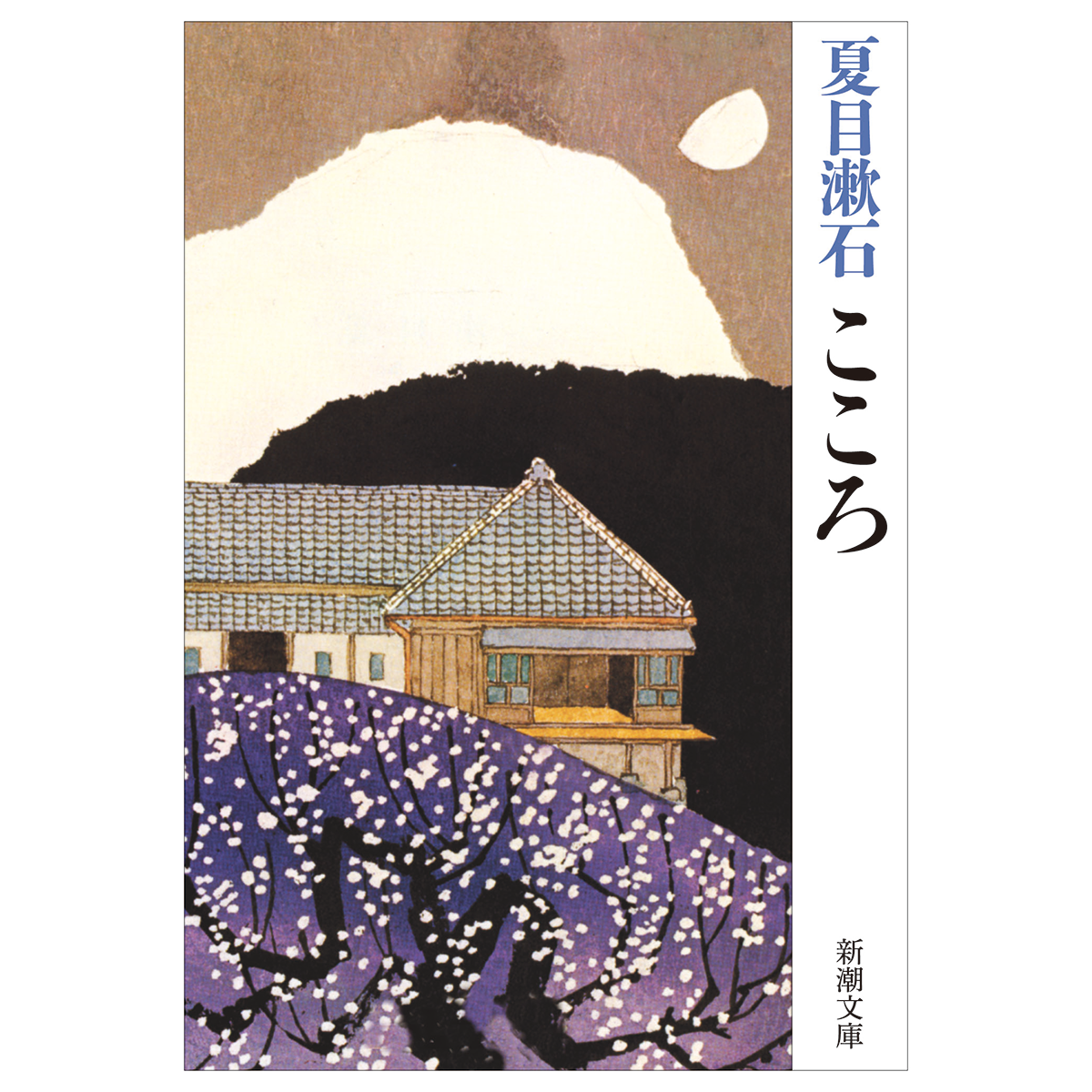
*「フィガロジャポン」2025年9月号より抜粋
photography: Yayoi Arimoto interview & text: Harumi Taki